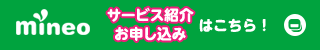入菩薩行論 第五章 正智の守護 (1)
戒を守ろうと願う人は、努めて心を守らねばならぬ。動きやすい心を守らないでは、戒を守ることはできない。
はつ情した野生の象がこの世で惹き起こす災厄は、放任された心の象が無間地獄等で惹き起こす災厄に遥かに及ばない。
しかし心の象が念(スムリティ)の縄で全く縛られれば、一切の危難は去り、すべての安穏が得られる。
トラ、ライオン、象、熊、蛇、すべての敵、すべての地獄の獄卒、鬼女および羅刹――これらすべては、ただ私の心一つが縛られれば、すべてが縛られる。そして私の心一つの調御によって、すべては調御され終わる。
なぜなら、すべての危難および類なき苦しみは、ただ心より生ずると、真実を説く人(仏陀)によって説かれているからである。
地獄の刃は誰が努力して作ったか。地獄の熱い鉄の床は誰の作か。また地獄の魔女はどうして生まれたか。
これらは皆、自分自身の悪心より発生すと、聖者は唱えたもうた。それゆえ、三界において心より他に恐るべきものはない。
もしも世界から貧困を実際に取り除くことが「布施の完成」だとするならば、現在世界が貧困である以上、過去の救済者たちは「布施の完成」を成就していなかったことになってしまう。
「布施の完成」とは、すべての衆生に対して一切の自己のものを、布施の結果の功徳と共に、施捨する心から生ずると説かれている。ゆえに、それは心に他ならない。
それを私が殺さないようにするために、魚などの生き物は、どこに連れて行かれればいいというのだろう。そうではなくて、殺生(などの悪業)を停止する心が得られれば、それで戒の完成は成立する。これが(真実を知る人の)意見である。
天空のように無数に存在する敵を、私はすべて殺、すことができるだろうか。
ただ私の怒りの心が殺されれば、すべての敵(という概念)は殺される。
大地をすべて覆うことのできる皮が、どこにあるだろうか。それはどこにもありえない。
ただ皮の靴を履くことによってのみ、大地はすべて覆われる。
これと同様に、私は外界の存在物を制することはできない。私は自分の心を制しよう。どうして他を制する必要があるだろうか。
精鋭な心があればそれだけでブラフマンとの合一などを勝ち得ることができるが、心の働きが鈍ければ、言葉と体に助けられても、それらを得ることはできない。
長期にわたってあらゆるマントラを唱え苦行をなしても、心が他に走り鈍重であれば効果はないと全智者は説かれた。
苦しみを滅ぼし安楽を得ようと、彼ら(衆生)は天空(のごとき輪廻界)をさまようが、全く無益である。それはこの神秘な諸法の根源である心が堅固に修められていないからである。
かようなわけで、私は心をよく支配し、よく守護しなければならぬ。心を守護する誓いのほかに、他の多くの誓いに何の用があるか。
心の落ち着かない人々の間におれば、(用心深い負傷者は)注意して傷を守る。
それと同様に、悪人たちの間にあっては、常に心の傷を守るべきである。
傷によるわずかの苦痛を恐れて、私は傷を注意して守る。
衆合地獄の山の重圧を恐れて、何故心の傷を守らないか。
悪人たちに対しても、美人たちの中でも、かような態度で振舞いつつ、堅固な修行者は、躓かない。
私の所有物は、欲するままに滅ぶも良い。尊敬も、身も、命も、滅ぶなら滅べ。
ただし「善き心」はいかなるときにも滅びてはならない。
心を守ろうと願う人々に、私は合掌をささげる。
「念と正智を、全力を挙げて守れ」と。
病に悩める人がすべての行為に不適当であるように、この念と正智の両者を欠くときは、心はすべての行為において為すに値しない。
その人の心に正智がなければ、教えを聞くこと、考えること、瞑想することは、穴の開いた瓶から水が漏れるように、念(スムリティ)としてとどまらない。
多くの教えを聞き、信仰を持ち、努力に専心しても、正智を欠くという過ちのために、人々は罪に汚されたものとなる。
無正智という盗賊--それは念の壊滅をもくろんでいる者であるが--この盗賊のために、蓄えた功徳すらも奪い去られて、人々は悪趣に赴く。
この煩悩という盗人の群は、我々への通路を探し求め、ひとたびそれを発見すれば、我々の旅費を奪い、幸福へ向かう生命を断つ。
ゆえに、念は常に心の門から遠ざけられてはならない。念が離れ去った場合には、悪道の災厄を思い起こして、元に連れ戻されねばならぬ。
師の教えによって、師を畏敬して恭敬をささげる者は幸福である。師匠のもとに住することから、正念は彼らにたやすく発生する。
「もろもろのブッダと菩薩方は、いたるところを妨げなく照覧なさり、一切は彼らの現前にある。そして私も常に彼らの前に立っている」
と、かように瞑想し、慙愧と恭敬とおそれを伴い、(自制して)あれよ。かくすれば、ブッダの念は、一瞬一瞬、彼に生ずるであろう。
正念が心の門に守護のために立つときは、正智が到来する。そして得られた正智は再び去らない。
まず第一に、この心がかように常に見守られねばならぬ。次に私は、あたかも木材のように、常に感官の無い者のごとくあらねばならぬ。
いつも無益にまなざしをうろつかせてはならない。視線は禅定におけるように常に下方に向けられるべきである。
しかし視線を休めるために、人は時折、諸方を見るべきである。また(行き会う人の)影を見たなら、その人を眺めて挨拶すべきである。
路上等においては、危難を警戒するために、時々四方を見よ。立ち止まり、後ろを振り返ったりして方角を観察せよ。
前進するにも後退するにも用心して行なえ。かようにあらゆる状態において、なすべきことを自覚してなせよ。
なお「身はかように保たれるべきである」と所作について己に指示を与えた後に、さらに途中で、身はいかに保たれているかと、省みねばならない。
心の狂象は、法の思念という大きな柱に縛り付けられて、それから離れないように、懸命に監視されるべきである。
「私の心はどこに転ずるか」と、サマーディのくびきを、瞬間といえども投げ捨てることのないように、反省すべきである。
しかし、危難とか祭礼などの場合において、それ(様々な実践規律)ができない場合には、随意に振舞ってよい。なぜなら、布施を行ずる時に、(場合によっては)戒は無視してもよいと説かれているから。
けれども、自覚して事をなし始めた場合に、それより他の事を考えてはならぬ。まずそれに心を傾倒して、そのことを完成すべきである。
かようにして、すべてはよくなされる。そうでなければ、事柄は両方とも成立しないであろう。そして、無自覚(無正智)という煩悩は増大するであろう。
種々の雑談、現に起こりつつある雑多の事柄、好奇心を誘うあらゆる現象--これらに対して生ずる興味を殺、すべきである。
土を砕き、草を刈り、畦を作る等の行いは(出家修行者になったからには)無用となった。如来の定められたおきてを思い起こし、それを(破ることを)おそれ、直ちに放棄せよ。
動こうという願いが起こり、語ろうという願いが生じたときには、自己の心を反省し、まず心しっかりと結びつけて(平静なる状態においてなせよ)。
もし自己の心が愛著に傾き、あるいは憎悪に傾くのを見たならば、その際には、行なうべからず、語るべからず、木材のようにとどまるべきである。
もし心が浮ついて、他人を嘲笑し、傲慢と固執にとりつかれ、はなはだ残忍となり、邪曲となり、狡猾となり、自慢をし、他人の欠点をあげつらい、他人を軽蔑し、論争に落ちようとする場合には、自ら木材のように処するべきである。
私の心は、所得と尊敬と名声を求め、あるいはまた従者を求め、奉仕を求める。それゆえに私は木材のごとくに処する。
私の心は、他人の利益に反対し、自己の利益を求め、あるいは取り巻きを欲し、饒舌を望む。それゆえ、私は木材のごとく処する。
忍耐心無く、怠慢で、臆病であり、向こう見ずで、罵詈雑言を好み、また自己の朋党を偏愛する。それゆえに、私は木材のごとく処する。
かように、心が煩悩に染められ、無益な企てをなすのを見るとき、勇士は常に、対治法を用いて、それを強く抑制せよ。
心を堅く決定し、はなはだ清らかに、不動に、(教えや師を)深く敬い、尊重し、(罪を)恥じ、おそれ、寂静に、(衆生を)なだめることに専心し、互いに矛盾する愚者の願望に倦んで飽きることなく、「煩悩が生ずるから彼らにこのような心が現われるのだ」と哀れんで、常に非難されない事柄に自己と衆生とを従わせ、これなる私は、化現のように、心を我執無く保ちたい。
(人間に生まれて真理を実践できるという)最上の機会が、久遠の時を経てはじめて得られたものであることを、幾度も繰り返して思い起こし、このような心を、スメール山のごとく、ゆるぎなく保とう。