~fioの旅~ the beautiful world? 【画像多め】【内容薄め】【不定期更新】
お家大好き引籠りのfioが、数少ない友人からの、半ば強引な誘いを断り切れずに外の世界と触れ合い、引籠りを脱却するまでの成長?物語です。
不定期に下手な写真と拙い説明を更新していきます。
お時間が有りましたらお付き合いくださいませ。
もし、ここを見て「行ってみたよ!」なんて報告とか貰えたら幸せ感じちゃいます。(笑)
それでは2017年fioの夏旅の始まりです。
勇者ヨシヒコが魔王ゲルゾーマと対決した場所への聖地巡りとして(笑)
(勇者ヨシヒコをご存じ無い方はコチラ)
http://www.tv-tokyo.co.jp/yoshihiko/
栃木県宇都宮市に有る、大谷資料館へ行ってきました。
http://www.oya909.co.jp/
外は30度超えの真夏日に、内部の気温は13度!
涼みに行くつもりがちょっと寒いくらいでした。
時折天井から冷たい水滴が首筋を襲います。
機械化される前は1本の石柱を切り出すのに4千回もツルハシを振るっていたとか…
昔の人の根気強さには頭が下がります。
中はライトアップされているものの、基本的に光量不足でスマホで写真撮っても真っ暗です。☝の画像はPCで目いっぱい明るく加工してます。
写真撮りたい人は三脚とバルブ開放できるカメラのご用意を。
大谷資料館の近くにある、その名も大谷寺(大谷観音)。
http://www.ooyaji.jp/
平安時代(810年)に弘法大使の作という奇岩の岸壁に掘られた千手観音が祀られています。
他説ではシルクロードの石仏と共通点が多いのでアフガンの僧侶の作という説も…
国の指定重要文化財という事ですが、上の巨大な岩の造形の方が気になります。
併設の宝物館にはここから発掘された縄文人の人骨が…
竜門の滝というと、大分のものが有名ですが、こちらは那珂川の支流江川に在る、竜門の滝、その幅は65m、高さは20mもあり大きいです。JR烏山線の滝駅という凄く小さな可愛い駅から5分程の場所で、1時間に1回滝の上を電車が通ります。
下の中州まで降りて遊べますが、滝へと降りる道が滝のしぶきでぬかるんでドロドロなので転ばない様注意が必要です。
遊歩道にはベンチも有って、木陰を涼やかな風が通り抜けて心地よいです。
ここは茨城県北部の大子町に在る月待の滝です。
http://www.daigo-kanko.jp/?page_id=2861
最近Jinponさんが跳び下り...じゃなくてバンジージャンプをした竜神峡からそう遠くない場所ですね。
滝の岩の下の窪みまで歩いて行けて、滝を裏側から見れるので、別名「裏見の滝」とも言うそう。なんだか怖そう?ですが、物凄い量のマイナスイオンがでています。
ちなみに、裏側からの雰囲気はこんな感じです。
滝の横のもみじ苑では天然氷の巨大かき氷を頂けます。
そして、ヒミツのお得情報です。
売店のお兄さんにお願いすると、無料で練乳マシマシで作ってくれます(笑)
月待の滝から日立へ向かう山間の道は、そこかしこに大小の赤い鳥居が有って、山の彼方此方に神様が居る様です。神様と言っても色々ですから、この数の多さはちょっと怖いただならぬ感じがします。
ここは茨城県日立に在る御岩神社の楼門。
http://www.oiwajinja.jp/index.html
現世と神域を分かつ門。
入る時と出る時にお辞儀をしないと魂を置いてきてしまうとか。
信じるか信じないかはあなた次第です。
冗談はさておき、楼門をくぐって少し行くと、宇宙飛行士が地上から光が伸びているのが見えたというGPS測位の場所に立つ三本杉は高さ50m以上の巨木です。参道の森の木は全てこの様な巨木で、自分が小人になったような?或いは巨大な神々の世界に迷い込んだ様な不思議な感覚に包まれます。
流石は「天地開闢の時より神々がこの地に鎮まる」と言われるパワースポットです。縄文時代の祭祀跡が発掘されていると言うから、精霊信仰の頃より何かが有るのでしょう。
三本杉を過ぎて、登っていくと、ほどなく天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)などと祀っている斎神社に着きます。ここの天井には見事な龍の天井画が有ります。この神社の横には石柱に木の車輪がはめられた物が有り、上へ回しながら祈ると現世での願いが、下へ回しながら祈ると後世での願いが叶うそうです。
何をお願いしたかはヒミツです(笑)
ちなみに記念にと思いひいた「水引の花お御籤」では愛情の花(心)を引き当てました。それによると「愛情に恵まれ、良い縁をもたらします」と有りました!
キターーーーーー!!!
でもね、個別の「縁談」のとこには「気長に待ちましょう、
良い話が来ることでしょう」ですって…
私の運命の相手はどこに??(笑)
それではみなさん、また次回お会いしましょう。









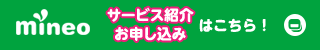


もみじ饅頭を食べながら景色を見ていると、潮が引いて浅くなった海を立派な角をもつ牡鹿が渡ってくるではありませんか!最後の最後に良い絵が撮れて大満足のfioなのでした。
夜は、広島風お好み焼きを、焼きそばVerと焼きうどんVerをで頂いて、お腹も大満足でした。
呉編につづく

2日目、早朝から電車に乗って呉にやってきました。以前、広島や四国の友人たちがこぞって「大和ミュージアムは一度は見に行った方がいい」って言っていたので、いつか広島方面へ行くことが有ったら行こうと思っていたのでした。
前日の登山でパンパンの脚を引きずりながら呉駅から連絡通路を歩く事10分。
ミュージアム前には戦艦陸奥の主砲の方針やスクリュー、舵や碇等が並べられ、奥には「てつのくじら潜水艦博物館?」が有り、色々大きくて、感覚がバグります。

海神だから?大和ミュージアムの門前には何故か大きなポセイドン像が立っています。トライデントとか筋肉ほか、色々大きくて立派です。
(〃´∪`〃)ゞ

1階でエントランスを通ると直ぐに、巨大な戦艦ヤマトの模型が目に入ります。ミュージアムの解説アプリ、折角用意して行ったのですが、iOS版の不具合で機能しなくて残念でした。
戦艦大和って、何故か後ろ姿の方が様になると思うのはfioだけでしょうか?
ピカピカだからか?宙に浮いているからか?写真に収めると急にプラモ感が強くなってしまうのがなんとも残念です。
展示室には、大和の他の戦艦の1m以上有る模型が複数展示されていて、なんというか「威風堂々?」とした姿に、当時これらの船を見た国民たちはきっと誇らしい気持ちだっただろうと思いました。
それだけに戦時中、軍事機密として多くの国民が大和を知らなかったというのはなんとも残念な気持ちにさせられます。
一方で、海戦や呉軍港と帝国海軍終焉のビデオを見ていた時はなんだか当時の人の思いが流れ込んでくる様で、とても胸が苦しくなって涙を堪えることができませんでした。

館内には魚雷とか特殊潜航艇とかの展示も有ったのですが、中でも目をひいたのが零銭です。エンジン不調で琵琶湖に不時着したものが戦後引き上げられたもので、62型という、大きな爆弾を付けられる様に改装したものだそうです。
実は前日、岩国でM6A7駐車場というのを見ていて、「変な名前」って思っていたのですが、思いがけず呉でその謎が解けました。
駐車場の名前はゼロ戦の型式M6A7が由来だったのです。
オーナーはミリオタ確定ですw

この零戦の展示室は回廊が2階3階と続いていて、上からも眺める事が出来ます。操縦席を覗き込む事ができたので、これは珍しいに違いないと、スマホを落とさないかドキドキしながらシャッターを押したのでした。
飛行機の操縦席って言うと、旅客機のものは写真を観た事が有りますが、零戦のそれは随分シンプルで簡単そう。
これなら練習したらfioでも運転できるかも?

大和ミュージアムで2時間近く過ぎてしまいました。お昼前に混雑を避けて早めのランチにしました。
お隣の「てつくじ」で潜水艦カレー🍛をいただきます。1000円也。
お店のスタッフさんの潜水艦そうりゅうTシャツがカッコよくて、ちょっと欲しくなりましたが、帰ったら絶対着ないよねと衝動買いを抑えた私、お利口さんw

「てつのくじら博物館」では、戦後の機雷除去の歴史を学んだのですが、もう海に出れば機雷に中る!というくらいの敷設数にビックリ!戦争ってあらゆる意味でイカレてると思います。
退役艦とはいえ、本物の潜水艦の発令所見学と潜望鏡を覗く体験ができ、人1人が通れる狭い通路や、何がなんだかわからない沢山の計器類、本物のリアルさと体験がるのに無料なんて!
内部撮影が禁止なのが残念ではありますが、呉に行ったら是非見学をおススメします。
”てつくじ”を後にして、大和ミュージアムの外の広場から呉港を臨みます。
じつはこの広場は戦艦大和の前甲板を模して造られていてその大きさを体感できる仕掛けになっているのです。
fioは筋肉痛で重い脚を引きずりながら、なんとか突端まで辿り着き、戦艦大和の艦首から軍港を眺める乗組員気分を味わいました。
この波型の切れ込み、大和の艦首部分の再現なんですよ!
あ、そう言えば、JR呉駅の発車チャイムの音楽は”宇宙戦艦ヤマト”の曲でしたっけ。

次の目的地は戦艦大和建造ドックを見に行くコトで、調べでは徒歩15分との事だったのですが、もう歩けない程疲弊していたfioはタクシーで移動する事にします。移動を開始すると、結構な勾配の長い長い坂を登らなければいけなかったので、タクシー乗って大正解でした!
着いたばしょは歴史の見える丘公園。
大和艦橋を模した慰霊碑と実物大の砲弾を見ることができます。

歴史の見える丘公園から延びる歩道橋を渡ると、現JMUのかつて戦艦大和を建造したドックとその大屋根(写真左端)を見ることが出来ます。そして、今回幸運な事に空母改装中のDDH184護衛艦かが(写真右端)を見ることができました。
単純に甲板を四角にするだけと思っていたのですが、スクリューや機銃なども外されて、何やら大規模な改装をしている様でした。

歴史の見える丘公園を後にして、坂を降りて少し行くと、「旧呉鎮守府司令長官官舎」が有り、現在は「入船山記念館」として見学する事ができます。右手に見える時計塔は1921年に旧呉海軍工廠造機部の屋上に設置されたもので、現在も動いている電動親子式衝動時計としては国産で最古のものらしいです。
時計塔の奥には砲台と弾薬庫等が残されていて見学することができます。
官舎の中の様子は👇をごらんください。
https://king.mineo.jp/photographies/1706

呉市では大和柄のカラーマンホール全10種があり、マンホールカードというのが配布されています。https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/52871.pdf
入船山記念館の前の坂道で8種類を見ることができ、入船山記念館でマンホールカードを貰えるのですが、既に疲労困憊のfioはここまで行きつつもカードを貰うのを忘れてしまったのでした!
しまった~

鎮守府司令長官官舎から港に戻り、高速船に乗り込んで海軍ゆかりの江田島へ渡ります。所要時間は舟で10分程。目的は海上自衛隊第1術科学校(旧海軍兵学校)の見学です。
写真は講堂の正門で、こちらは皇族や将官など身分の高い人専用の車寄せだそうです。
呉の大空襲でも被害をうけておらず、昔の写真と比較しても変化が無いのがなんとも不思議です。

昭和天皇も訪れた事があるという講堂の中。ここで軍服に身を包んだ学生たちはどんな思いでどんな話を聞いたのでしょう?
時間を超えて圧してくる厳かな空気感に我知らず背筋が伸びます。

こちらは学生たちが過ごす宿舎。レンガは全て英国からの輸入品で、通常のレンガよりもずっと高温で焼かれているため、中の空気は抜け表面はつるつるに溶けていて、ホームセンターでよく見るレンガとは全くの別物です。
当時としては大変高価なもので、レンガ1個の値段が職人の日当の何倍もの価格だったそうです。
学生たちは起床ラッパが成ると、寝床を整え、パンイチでグラウンドに3分以内に整列して朝の体操をするのが日課だそう。
寝起きの悪いfioは入学できそうにありません…
そういえば当時の兵学校はとてもレベルが高く、兵学校の滑り止めに帝国大学を受けていたのだそう。ほんとうかな?

👆の宿舎の中の一直線の廊下です。多分戦争映画とかで撮影に使われた場所で、初めての訪問なのに既視感が。
見学中も、白い詰襟の仕官候補生の制服に身を包んだカッコいい学生さん達が行き来していました。

資料館の建物の裏には、戦艦大和の砲弾や特殊潜航艇、酸素魚雷等が展示されています。魚雷に操縦席を付けたような特殊潜航艇とか回天には乗りたくないと心の底から思うのです。
こういう兵器を当時若干21歳の士官が考案して作戦実行していたなんて…
今の愛国心のかけらも無い教育もどうかと思いますが、当時の教育というのも恐ろしいと思ってしまいます。
当時の連合国が日本人の精神性と報復を極度に恐れたというのも頷けます。

教育参考館という資料館の中は撮影禁止だったのですが、日中戦争や日露戦争の頃からの軍拡の歴史に始まり、全特攻隊員の名前が刻まれた石板や血のついた外套の様な生々しいものまで様々な品が展示されています。展示品のほんの一部は👇で見ることができます。
https://www.mod.go.jp/msdf/onemss/about/facility/index-sankou.html
特に特攻隊員の親や年少の兄弟に宛てた、帝国軍人としての精神と、1人の人間としての人間らしい思いやりのないまぜになった遺書は読んでいて胸に迫るものがあり、泣きそうになりながら見てきました。
そんな中、横山大観の「正気放光」に出会ったのは思いがけない驚きでした。
なんでも展覧会終了後海軍省を通じて江田島海軍兵学校に寄贈されたものだそうです。

今回江田島に来たもう一つの目的は、太平洋戦争を生き抜いた幸運艦、陽炎型駆逐艦雪風の舵輪と主錨に会いたかったのです。雪風は大和の沖縄特攻からも無傷で帰還し、戦後は台湾海軍旗艦を務め、昭和44年に破損解体される迄活躍した凄い船です。
昭和46年に台湾から雪風保存会に舵輪と主錨と時計が変換され舵輪と時計は資料館に、舵輪は校庭に展示されています。
待受にしたら、幸運にあやかれるかも?

旅の3日目は雨予報だったこともあり、岩国市内観光です。👆は宇野千代生家の外観。
普通の住宅街の中にいきなり昔風の建物が出現。
まぁ元の住人が有名になったとは言え元々は普通の一般住宅なので当然ですが、岩国在住の友人も何度かチャレンジしていまだに辿り着けていないとか(笑)
市内ではもうこういった古風な建物はほぼ絶滅しているので貴重です。

宇野千代生家のお庭がとっても素敵でリラックス出来るので何時間でもベンチに腰掛けてぼーっとできそう。と、ぼんやりそんな事を考えていたら足首を蚊に刺されてしまいました…

中は割と小ぶりな建物なのですが、手入れが行き届いていてとっても良い雰囲気でした。ボランティアで建物の管理をしているおばさま達と、1時間もおしゃべりしてすっかり長居してしまったのでした。

宇野千代生家を後にしてトコトコ歩いて錦川を渡り、岩国城下町エリアに雰囲気のある建物を探しに行ったのですが…既に普通の住宅街と化していて、撮影を早々に諦めたfio は錦帯橋の方角へ適当に歩き始めると、偶然に?吸い寄せられる様に地元の日本酒の飲み比べが出来る「本家松がね」にたどり着きました。
https://honke-matsugane.jp/
岩国の代表的な銘柄
雁木、五橋、村重、金雀、獺祭が、それぞれ一口300円で試飲出来てオススメです。
fioのお気に入りは金雀で、「入手困難なので、もし見かけたら即買いですよ!!」って言われて探してみたのですが本当にどの酒屋さんでも売り切れ…
他には名物だけどあまりお勧めされてないw岩国寿しが1口150円で食べれたり、ちょっとずつ味見するにはとっても良い所です。
建物も外見も屋内も昔の長屋風で気分があがります♪

お酒を頂いてご機嫌のfioは有名な錦帯橋へ向かいました。有名な景色を自分のカメラに収められるのってちょっと嬉しい♪
東京の日本橋、長崎の眼鏡橋とあわせて日本三名橋に数えられる錦帯橋は、世界的にも唯一の構造で掛けられている橋だそうです。
実際に渡るとアーチ部分の勾配は見た目よりもかなり急で重ね張りされた木板が階段状になっており、歩く時には少々注意が必要でした。
8月には有名な鵜飼いが見られるそうで、橋を渡った先には鵜がいっぱい飼われた鵜小屋も有りました。
もっとも、岩国は元々鵜が多過ぎるらしく、空港近くの水場でも野生の鵜が魚を取る姿がみられました。

錦帯橋を渡ってすぐのところに、TVで紹介されて有名なソフトクリームのお店「むさし」が有ります。番組名もでかでかと看板に掲げちゃってますね(笑)
ソフトクリームの種類は今では190種類を超えるそう…
そんなに作ったって、そんなに食べられるわけじゃないのよ~

で、「むさし」のお向かいには「佐々木屋小次郎商店」があり同じ様な商品を展開しています。店名が店名だけに、刃傷沙汰になりそうで心配です。(^_^;)

でfioはどうしたかと言うと、小次郎商店の「ベリーベリーチーズケーキ」580円也をいただきました。決め手は呼び込みのお兄さんがイケボだったから(笑)
クリームがとてもねっとりしていて、ソフトクリームと言うよりはイタリアンジェラートといった感じ。
しかもコーンの一番下迄ぎっしりなのでひとつ食べたらもうお腹いっぱいで昼食どころではなくなってしまいました。
でも美味しかった〜❤️

仕方ないので腹ごなしに、山の上の岩国城へと向かったのですが、実はケーブルカーという(笑)再建なので中は近代的な作りの博物館になっているのですが、展示されている刀剣類や具足の量がものすごいです。
近くには柏原美術館もあり、大量の刀剣、鎧、火縄銃などを見る事ができるので歴史や刀剣好きの人には楽しいと思います。
ちなみに新撰組総長近藤勇も持っていたという虎徹も展示されているそうです。
https://www.kashiwabara-museum.jp/

場内展示の一部をご紹介安土桃山時代から幕末迄続いた名工兼先の作。
此方は大きさも程よく、反りも太刀ほどでも無いので江戸時代頃の刀かな?と思います。
関連があるのかわかりませんが、兼房とか、兼景とか、兼なんとかという銘柄の展示が多かったです。

fioが個人的に気になったのが此方の鉄扇。鉄で作った扇子型の武器なんて、アニメやゲームの中だけのお話と思っていたのにホンモノ登場!
この前に鎖鎌の展示もあって、汚れて使い込んだ感じに!!って驚いていたら模造品って書いてあってちょっとガッカリしたのですが、鉄扇は模造品ではない模様。
一体どんな人がどの様に使っていたのでしょう?
これって戦場で使うとも思えないし、暗器の一種なの?

岩国には古くから白蛇が多く見られるそうで、白蛇館という所で生体展示が見られます。縁起物として大事にされているそうですが、実際は青大将のアルピノ何ですって。
カメラを向けるといい感じに蛇らしいポーズで撮影に協力してくれました♪

白蛇神社というお社が有ります。御祭神は宗像三女神と宇迦之御魂神となっています。
で、白蛇館のお土産として👆のおみくじが売ってます。
550円か、高いな君たち…
白蛇は金運の神様とも言われているけど、おみくじで散財してむしろ貧乏になりそうな…
「一個くださ〜い。」
結果は「大吉」fio は550ゴールドを失った。
最近この手のおみくじ増えてホント困っちゃう。

白蛇館からの帰り道、小雨がパラつく中傘をさして歩いていると、突如ただならぬ雰囲気にギョッとして見やると、そこには時代劇で見たことの有る大きくて立派な門が!なになに?香川家長屋門とな。
なんかアレ、遠山の金さん?とかの奉行所そのまんまな感じ。
本物の迫力が凄いです。

歩いてようやくお腹もこなれてきたので遅めの昼食に、友人オススメの長州屋で瓦蕎麦をいただきました。熱く熱した瓦の上に茶そばと、錦糸卵、牛すじが乗っていて結構甘い味つけです。
麺つゆにつけて食べるんですが、瓦で熱された蕎麦は解しにくくてちょっと食べづらかったカナ。

岩国で見つけた年代物の自販機コーナー。ラーメンやおうどんの自販機って見たことありますか?
試しに買ってみると👆の様などんぶりで温かいおうどんが出てきました。
中にゆで卵やワカメがセットされたどんぶりが入っていて、注文?すると中で麺とスープとお揚げを投入して出てくるみたい。
昔の人は発想が斜め上で面白いですね。
他にロッテのガムの自販機なんてあったのですが、単価が低いから自販機の設置コストの方が掛かって不採算ぽかったです。

岩国の旅のしめくくりは酒蔵巡りです。ここは村重酒造さん
お店の裏手にはお酒造りに使っている超軟水が無料で汲める場所があって、地元の人達が車でたくさん汲みにきていました。
お店の中では試飲もすることができて、商品としては売り切れていた”8ノット”というお酒を飲む事ができました。
白はちょっとヨーグルトっぽい不思議な酸味で日本酒って感じとはちょっと違って、黄色の方は口に含んだ瞬間にふわっと芳醇な香りが広がってとっても美味しい日本酒でした。
https://www.sakagura-press.com/sake/murashigeshuzo2021/

村重酒造さんには、なんと!5mもある巨大な杉玉が!こんな巨大な杉玉は見た事がなくって、本当に圧巻なのです。
いったいどうやって作ったんでしょう?

最後に訪れたのは八百新酒造さん。https://www.yaoshin.co.jp/goods_type/season/
建物もとっても雰囲気が有るのですが、中に入ると奥にはお酒を造っているところが覗けて、事務所にちょっと販売用の冷蔵庫を置いてあるという、本当に工場直販みたいなところです。
先の村重酒造さんでは、欲しいお酒が買えなかった(11月から今年の新酒が出るので10月は一番お酒の在庫がないとのこと)ので、何か買いたいfioは社員さんに「ここでしか手に入らないお酒ください」ってお願いして美味しいお酒を頂いて帰りました。

こちらが買ってきたお酒。右はスパークリングとなっていますが、酵母の自然発酵によるガスでスパークリングになっている物。
栓を捻るとガスと一緒に堪らなく美味しそうな香りが部屋にブワッと勢いよく広がります。
でも、お酒が吹きこぼれない様に何回も栓を開け閉めしてお酒が落ち着くまで飲むことができません。早く飲みたいのに〜(笑)
味の方は若いお酒らしくピリっとした辛味が有ります。純米発泡にごり生原酒と書いてありますが、濁りと言うほど濁ってなくて、霞酒位の感じでサラッとしてました。
大きな瓶の方はラベルにprototypeと書かれている通り、試験醸造した物を詰めた物で、まだ市場に出ていないお酒です。
こんな珍しいのを入手出来ると嬉しくなっちゃいます♪
火入れされていない生原酒なので、とても柔らかで優しい飲口でイメージは湯呑でゴクゴク飲めちゃいそう。
雰囲気は上善如水と似ていて、ガツンと来るのが好きな人にはちょっと物足りないかも?
fioの秋旅は一旦ここ迄。
次は何処へ美味しい物を探しに行きましょうか?

2022fioの晩秋の旅遡る事2年前…
辛い事が続いていたfioは神仏の力を借りようと坂東三十三観音巡りの旅をしたのでした。
鎌倉のお寺で購入した専用御朱印帳には、結願御礼の寺としての善光寺、そしてその対となる北向き観音の2つのページが折り込まれていたのでした。
fioがこの旅をしていたのは悪疫の第二波と第三波のちょうど狭間の時期で、それ以後の流行は皆さまご存じの通り。
以来、この結願お礼の旅に出たいと気になっていたもののずっと引籠りを決め込んでいたのでした。
第八波が流行の兆しを見せる今、これ以上待っては居られないと、fioは思い切って出かける事にしたのでした。
ドラぷらで、ルートと渋滞予測を見ると、関越道は埼玉県の東松山辺りがかなり渋滞する模様。
5時出発と考えて早めに寝たfioは珍しく3時過ぎに目覚め、寒くて二度寝ができないので予定を早めて4時半に出発しました。
「早く着きすぎるのでは?」なんて考えていたfioですが、お寺の朝はうんと早くてfioの心配は杞憂に終わりました
山門につくと既にお店も開いていて参拝客もちらほら。

持参したマイお線香を香炉に入れ、輪袈裟をかけて本堂へ。輪袈裟をつけるなんて本格的でしょう?そう、fioは何でも形から入るタイプなのです。
その割に気弱なfioはお堂の隅っこに立って般若心経を小声で読経して、みんなの幸せと母の安寧を祈願しました。

早朝ということもあって、御朱印も待ち時間無く頂くことができました。今年は特別開帳が有ったので、御朱印も特別Versionが有ったのですが、料金も特別だったので通常版をチョイス。
納経をしてお守りを頂きました。

お守りの授与所を見て回っていると…出たな!という感じで、近頃増えている人形御神籤シリーズ!なんとここでは閻魔大王!
もうこれはやるしかありません。
亡者の生前の行いを映すという閻魔様の「浄玻璃の鏡」にかけて御神籤の内容は全て鏡文字で書かれていて、読むためには鏡に映さなくてはいけません…
面倒くさいのよ…(罰当たり?)
結果はというと…中吉
「心をひらけ!人とつながるべし。心の殻を破ってこそ真の幸せを満喫できる」と出ました。
なんと今のfioにピッタリな言葉でしょう?閻魔様おそるべし…
それにしてもこの絵面はなかなか…
授与所でもう一つ何故か気になって仕方がなかったので、1日2回御神籤をひいてしまいました。
こちらは男女別のもの(その内性別で分けるのはコンプラで無くなるかも?)で“女みくじ”をひきました。
「新たな成長と飛躍の予感。人に頼らず甘えず自分の力で道を切り拓いていこうという気持ちが大切。苦手なことから逃げず、克服するよう心がければ大きな成長が実感できる」とのこと。
こちらも、今まで「明日でいいや」と先送りを繰り返し何もしないで引籠る日々を送っていたのを、最近は投げ出そうとする考えが出た時に「今やろう」と言い聞かせて行動したり、なるべく外出する様にして鬱病克服を頑張り始めたfioになんともピッタリな言葉です。
善光寺の御神籤なんかスゴイです。
ちなみに御神籤のおまけの一文字チャームは“愛”でした。新しい愛きた~ってauか(笑)
駐車場へ向かう道を半分ほど進んだところで、「自分のお願いごとをするの忘れた!」と気づき、本堂まで戻って端っこでこっそり追加のお願いをしたのでした。
因みに善光寺は来世のご利益で、対となる北向き観音は現世のご利益があるそうです。

善光寺を後にしたfioはGoogeMapで見つけていた川中島古戦場跡に向かいました。ここには八幡社があり、誉田別尊ほんだわけのみこと(第15代天皇応神天皇)と後に合祀された諏訪大社の建御名方命が祭られています。
武人の神、弓矢八幡として全国に勧請されているとのことですが、fioは初めての出会いでした。
この地が本陣を急襲された武田信玄が采配で上杉謙信の太刀を払った場所ということで、その銅像が建てられています。

しかし、ここで、fioに一つの疑問が沸き上がります。神社の敷地内に建てられた川中島合戦布陣図に示された現在地の場所が信玄の本陣では無いんです…
これは...突っ込んじゃいけない大人の事情というやつでしょうか?
この古戦場跡には川中島の合戦で倒れた兵士を敵味方関係なく埋葬した首塚(屍塚)が2つも有ったので、fioは長
居は無用と逃げるようにこの地を去ったのでした。
”敵に塩を送る”の故事は、この敵味方の区別無い弔いに感動した謙信が「我信玄と戦うもそれは弓矢であり、魚塩にあらず」と言って送ったそうな。知ってた?

次に訪れたのは、川中島の合戦で武田勢の拠点となった松代城(海津城)跡です。天守は無いのですが、立派な石垣と再建された立派な門を見る事ができます。
なんでも今年は真田信之入部400年ということで発掘調査の為に堀の水が抜かれていたのが残念。

天守閣が有った場所は空き地なのですが、石垣に囲まれた城内に往時の雰囲気を想像しながら探検気分を味わえます。それでは暫し城内探検をどうぞ。

橋を渡ると、石垣に囲まれた50人も入ればいっぱいになりそうな小さなスペースがあり、太鼓門という門が登場します。攻め込んでここに閉じ込められて矢の雨が降ってきたら逃げられない感じです。

太鼓門をくぐると広い本丸跡で、大きな銀杏が見事に色付いていました。
銀杏と一緒にfio登場!調子にのってブイなんてしてたら、肩に“こつ~ん”ギンナンが落ちてきてきてつっ込まれました。