古代ロマン「真稲王国」
魏志倭人伝Ⅱとも呼ぶべき食糧の書物(秘伝)によれば、神代の時代、邪馬台国とともに栄えたと伝わる古代:真稲王国。
米(まい)ちゃんという巫女が女王として統治していたのだとか。
この王国、時代が余りに経ちすぎていて、何処にあったのか所在は掴めないが、先の秘伝の食糧書によれば「稲作」を行なっていたとのことなので、今の新潟あたりにあったのではと見立てられている。
大阪説もあり。
当時のお米「古代米」って、どんな味なのかな?
あなたも新米が届くこの季節、味覚の秋を楽しみつつ、田植えや稲刈り、ハザ掛けをした事を想い出しつつ、中二病的空想に浸ってみては如何?
「農園」プロジェクト
https://king.mineo.jp/staff_blogs/2024
古代:真稲王国のイメージキャラクター「米(まい)ちゃん」
杏鹿さん作成
女王が身につける装飾具(まがたま/勾玉)には、エメラルドグリーンの輝きを放つ新潟のヒスイもよく似合う。
姫川流域・糸魚川ヒスイ
https://www.xhimiko.com/邪馬台国/高志の国/翡翠と玉造/
日本のヒスイ文化を解き明かすスタート地点
https://www.asahi-tabi.com/hisuikaigan
急激な円安進行、コロナウイルスによる世界的物流の停滞、ウクライナ情勢、輸出国の不作等により、多くを輸入に頼る小麦粉の価格が高騰しています。
そこで注目されるのが、国産比率がとても高く昨今の物価高への連動に比較的鈍感な米と、パンにも加えられている(グルテンフリーな)米粉。
このような価格の地殻変動で、米(マイちゃん)へのシフトは果たして起こるのか、いや、もう起きているのだろうか!?
26 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。



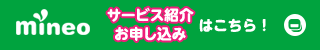

そうなると、減反政策もやめになって稲作農家も生計が立ってくるのにと思います。
食料自給率も少しは上がるでしょうね。
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
【CM】あるあるさぬきうどん【石丸製麺】もうひと月もすると年末ですね。うどん好きな人やうどん県の人たちは年越しといえば蕎麦ではなく、うどんですよね。
りんごのひとりごとさん、お久しぶりです!
小麦粉と一言で言ってもご存知の通り、たんぱく質の含有量で種類・用途が異なっていて、強力粉(パン用)、準強力粉(中華めん用)、中力粉(うどん用)、薄力粉(菓子用)に分類されます。
小麦の自給率は僅か「13%」ほどというのが悲しきかな現状ですが、「中力粉(うどん用)」の自給率に限ると6割から7割へと跳ね上がります。国産小麦といえば9割ぐらいが中力粉のようなのです。
米の消費が減ったのは、小麦製品をたくさん食べるようになったから、とよく言われますが、小麦の消費量はひとりあたり年間29.0kg(1965年)から31.7kg(2020年)へとそれほど増えてはいません。
この間に米の消費量は117.4kgから50.7kgへと大きく減少してしまっています。
ですので、米の消費大減少の原因は主食の交代ではなく、林檎とか蜜柑の果実を沢山食べるようになったということになります?
リンゴやミカンも米同様、国産比率が今なお高い頼もしい食材ですので、これからも購入を維持したいものですね。
>> 祖父と番長 さん
お元気そうで何よりです。 ^_^国産小麦でうどんなら申し分なしですね。
りんご、梨、温州みかんなどは宝です。
かく申す私はパンが大好きで一日にお米を食べるのは夕食時だけで、あとはパン、それも菓子パンが多いです。
アンパンなんかはそれこそ米粉で良さそうですがね〜。
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
りんごのひとりごとさんには勝手ながら、「リンゴまるかじり」のイメージが付きまとってしまっていますが、実情は随分と違うのですね。これからは米粉パンまるかじりの「米子さん」とお呼びしてもいいですか?
↑笑っていいとも!
←全力で拒否られそう.....
林檎は丸カジリが恰好いいスタイルなのでしょうか?
それとも、蜂蜜を掛けてテイストUP?
余ったら、ジャムにして保存すべき?
あと、薩摩芋とかのイモ類も主食だったようです。
でも今は「玄米ご飯ブーム」があるように、健康知識の普及と高まりで、雑穀も見直されたりと、風向きが変わってきていますよね。
余談ですが、秋は栗ご飯がおいらのお気に入りです。
>> 祖父と番長 さん
歳をとってから、果物の側が歯にはざかる(歯の隙間に詰まる)ようになり、丸かじりはしないようになりました。二十世紀梨だったらまだ丸かじりできるかも知れませんが、今年は果物自体をあまり食べませんでした。
先日、田舎の友人が送ってきてくれた富有柿くらいです。

おはようございます。ウクライナ情勢や円安の影響で、穀物の輸入価格は上昇しています。お金さえ出せば買える状況なら良いのですが、他国に買い負けている状況です。
内外価格差が縮まっていると思われるので、これら穀物の作付けを奨励する施策を行えばよいと思うのですが…
「米子(こめこ)さん」で調べたら、最近ニュースで見た「ジブリパーク」のある愛知県長久手市には、「長久手米粉キャンペーンママ こめこさん」がいるそうです。
(^thank^)/🦉
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
>果物の側が果物の皮が の誤変換です。m(_ _)m
>> 祖父と番長 さん
米子と言うと 👆最近は鬼太郎が付くようになったのですね〜。
米子に侵入すると迷子になります。
(私らは「しんにゅう」と学びましたが、「しんにょう」と学んだ人も多いようです。)
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
>歳をとってから、果物の皮が歯にはざかる(歯の隙間に詰まる)ようになり、丸かじりはしないようになりました。アイン歯科クリニックで診てもらうと、少しは林檎の噛みごたえが改善するのではないですかね?
それともう一つ、二十世紀梨にならって、今、丸かじりしやすいよう改良が施された新しい品種「二十一世紀林檎」がとある県の農業試験場で極秘に開発が進められているらしいです?
(機密情報なので、ご内蜜に):^)
とはいえ、丸かじりにこだわらなくても、大きな果実はナイフで切り分けて(分割して)食べればいいじゃありませんか〜、ということに今、気づきました。
(滝汗)
歯の隙間に詰まる事を「歯にはざかる」と言うのですね。初耳な言葉でしたが、収穫した稲穂を稲架掛け(はざかけ)する。ともいいますので、もしかしたら語源が同じなのかも知れませんね。
ミニトマトのように、ミニリンゴの実が店頭に出回る日も近い?
ぷちトマトは鮮度がすぐ落ち長持ちしませんし、バナナは痛み易いですが、林檎はミカンより更に日持ちする事が大いなるメリットですね。
りんごはパンと同じく、丸かじりや料理無用でそのまま生で食べられるのが、手軽でいいと思います。
その点、お米だと、火打ち石から始めて炊飯しないといけませんから。
恐くないから食べてくんしゃんせ。
「餅米」の御飯である、おこわメシは歯ごたえがあっていいものです。
オコワにも色んなバリエーションがあって、オイワイ・メシとも言うべき、赤飯もありますね。
もちもち感を謳ったパンを目にすることもあります。
米粉とか入れてもちもち感を出すんでしょうか?
餅米の米粉(白玉粉、もち粉)だったら、更にそんな弾力食感な味わいになるような気がします。
>> 弾正忠 さん
弾正忠さん、はじめまして。「こめこさん」の紹介、ありがとうございました。
米粒さんがエプロンを掛けていますね。
ご当地キャラクターって、いやぁ、色々とあるものなんですね。
米の消費拡大を願って如何に地元をアピールするか、そこの地域の方々の熱き思いが伝わってくるようです。
>> 弾正忠 さん
円高が長らく続いた影響で、円通貨の強いチカラを借りて世界中の食料を買いあさっていられたようですが、最近は状況も一変。円高時代に食糧自給率は著しく落ち込んでしまったので、円安大到来といっても、そう簡単に自給率が高められるとはにわかには思えないです。生産基盤が相当弱体化されてしまってるようなので。
円高時代中でも中国の台頭で世界中の食料が買いあさられ、日本とか他国は買い負けしているという話しをよく耳にしました。
アフリカとかが人口大爆発していますし、インドを始め東南アジアも今なお人口急増中ですから、食料は自国である程度確保しておかないと相当やばいですね。
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
そうだ、「米子」は「よなご」とも読むんだった!(忘れてた〜)
オイラの頭のなかでは「米子」の読み方は迷子か、よね子さんが大勢を占めています。
鳥取西部の中心都市、商業都市なので、お米の生産地では全然ないようです。
ゲゲゲの鬼太郎の作者、水木しげるさんは隣り町の境港市で育ったようですね。
「LEMON」を大ヒットさせた米津玄師は読み難いですけど、「よねづ けんし」と読むんだった。いつもゲンシと読み間違えしてしまう。
以前はカルフォルニア産とかイタリアあたり?南米が多かったはずですが、最近は瀬戸内とかの国産レモンも見かけるようになりました。
輸入ものは防カビ剤使わないと傷んでしまうんだったような?
とはいっても自給率は10%台みたい。
>> 祖父と番長 さん
こんばんは。こちらこそ宜しくお願いします。
> 生産基盤が相当弱体化されてしまってるようなので。
生産者の高齢化と後継者不足ですね。
第一次産業は補助金漬けで儲かる産業ではなくなりました。
外部や他業種から新規参入をしようとしても、各種の規制や排他的社会のせいで、上手く行く例は少ないようですし。
(^thank^)/🦉
>> 祖父と番長 さん
境港は大昔(まだ私が 20 代の頃)に隠岐の島に行くために、フェリーに乗船しに行ったことがあります。乗船は昼間で、お天気も良く、たくさんの飛び魚がフェリーの後を追うように海面を飛んでいたのが印象に残っています。
その頃は鬼太郎はブームではありませんでした。
>> 弾正忠 さん
図表の通り、第一次産業は1955年以降,減少が続いています。しかも急激にです。そしてまだまだ歯止めがかかっていません。特に稲作は機械化が進んだこともあり、労働集約型産業から脱して、恐ろしい程に減り続けています。
近代化、先進国化する程にこういう傾向にはなるわけですが、自給率の低下と弾正忠さんご指摘の、高齢化と儲からない農業という構造的現状は頭を抱えるばかりですね。
・参考資料
国立社会保障・人口問題研究所
https://www.ipss.go.jp › P_Detail2021
-人口統計資料集(2021)-
https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/P_Detail2021.asp?fname=T08-07.htm
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
米子さんという言葉が「よなご」へとホップし、次は「境港市」へとステップ。更には「隠岐の島」へもジャンプ。りんごのひとりごとさんから風光明媚な話しが聞けて、一緒にバーチャル船旅までしてるみたいで、オイラも嬉しいです。
旅は非日常性。移動し続けるから風景が絶え間なく変わり、大パノラマ、大迫力な光景に巡り会えて、心豊かになれるというもの。
山陰の海旅でいただく海の幸と御飯のセットもたまらなそう。
魚が飛び交うところが見られるなんて、羨ましいです。
>> 祖父と番長 さん
【お祭り屋台の定番】りんご飴の作り方【フルーツ飴】小ぶりな林檎、ガーデニング用の小玉なリンゴ(姫りんご)に、「アルプス乙女」という銘柄とかがあります。
観賞用(盆栽)にもいけてるみたい。
露店で入手する「りんご飴」は多分これなんでしょうね。
林檎パイとかにもどうでしょう。
>> 祖父と番長 さん
お米が余り気味となり、消費が大きく落ち込んで行った原因は、ズバリ、おかずをたくさん食べるようになったから!メニューが多彩化し、肉類や油脂類の消費が数倍にも増えていったこともあるようです。
おかず(主菜・副菜)が充実して主食が隅っこに追いやられる、この半世紀の食生活の急激な変化は先祖様が見たらきっとびっくりだと思います。
ですので、物価高対策はおかずを減らせば、家計はしのげれる、耐えられるのでは?という珍説をご提案です。
>> りんごのひとりごと@ぐ〜たら居士 さん
椎名林檎 - りんごのうた日本の国内で1年間に食べられている小麦のうち、国内で作られているのはわずかに13%ほど。これだとレモンの自給率と変わらないようです。
一方、水産庁によれば、2019年度の水産物の自給率(概算値、重量ベース)は、魚介類(食用)で56%(前年比-3ポイント)、魚介類(全体:非食用を含む)で52%(前年比-3ポイント)、海藻類で65%(前年比-3ポイント)となるそうです。
四方を海に囲まれた島国なのに、心もとない数値ですね。
元来、魚好きな日本人は近年、魚より肉を好むようになってきているようですし、
日本近海で魚が採れなくなって値段が釣り上がり、輸入魚も円高となると。
ぎょぎょ.....
「石、拾いました(*^^*)ヒスイでした」という
その辺でよくわからない物を拾ってはいけません
と言われそうなCMを見た気がします($・・)/~~~
>> 退会済みメンバー さん
化石のよく採れる地点でも、採掘禁止の立て看板があったりしますね。玉石混交の地面で鉱石、宝石類を見分ける知識は「ヒスイ(必須)」といえそうです。

農林水産省資料より【MV】Maxとき315号 Short ver./ NGT48[公式]
明治時代、人口が最も多かったのは江戸(東京)ではなく、大阪や京都でもなくて、新潟県だった。
現代人から見たら意外と受け取られそうですが、それだけ日本も大変化したということになります。
当時の人口4000万人のうち180万人が新潟に居住していました。
その頃の日本は9割近くが農業を営んでいた時代で、食いっぱぐれのない?米どころに人が集まっていたという図式になるようです。
だからこそ、真稲王国が新潟にあったのではないか?という仮説を立てさせていただいた訳ですが、そんな仮説も朱鷺には「まぁ、い稲」と思って下さればありがたいです。
新潟県(19位) かつて日本一の人口。NGT48で飛躍!
https://news.tiiki.jp/articles/3036
>> 祖父と番長 さん
魚は骨があるから苦手という人が多いみたいですね。で、魚を食べるとしたら刺し身か握り寿司に偏るという.........
でも、最近握り寿司で好まれているサーモンはノルウェーなどからの輸入品だし 🤣
私が子供の頃は流通や冷凍技術が発達していなかったので、刺し身なんて買えませんでした。
買えるのは冷凍クジラくらい。
塩サンマは安かったと思います。
一疋5円のサンマ、安くて美味しいサンマ♫
って歌があったような。