電力会社はこれからどうなる?
国立環境研究所の推計によると…
「住宅やビルなど市内の建物の70%に屋上パネルを設置。市内の全ての乗用車がEVになり、バッテリーに電気をためて融通し合える仕組みが整ったと仮定」すると、都市で必要な電力の多くを賄えるという結果になったとのこと。
https://news.yahoo.co.jp/articles/68fa3a236bf959b7350603d708b7353b9ea05857
年間平均自給率は最高の岡山市で95%、福島県郡山92%、仙台81%、札幌75%と、東京23区53%以外はかなりの自給率になるそうな。
まあ、市内の全ての乗用車がEVになるのを待つよりもビル設置型の蓄電池が安くなって普及するほうが早い気がしますし、東京などの大都市の場合は「屋上パネルを設置」よりも、高層ビルの「壁面やガラスを全てソーラーパネル」にしたほうが遥かに効果的だとは思います。
しかし、そんな近未来を想像すると、電力会社の主たる役割も「発電して電力を供給する」から「各所の余剰電力を融通管理する系統制御」へと大きく変わっていくことでしょう。
いずれにしても、遠方で大規模集中型発電所を建設して夥しい高圧鉄塔を建てて延々と長距離送電していた時代から、電力を消費する都市内で発電できる時代に移行していくということは色々な意味で喜ばしいことです。
関西電力も、北陸電力管内の福井県で発電した電力に頼らずに済むように頑張れ〜
30 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
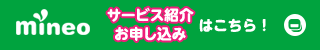

昨今は窓にも使える透明なソーラーパネルが開発されたらしいですね。
ただ太陽光発電に関しては「パネルの寿命は正直どこまで持たせられるか?」とともに「寿命を迎えたパネルの再資源化」など、色々課題は残っているものと感じます。
特にパネルの再資源化を行うには「一度半導体として作成したパネルに含まれる不純物を取り除く→再度高純度のシリコンとして作り直す(取り除いた不純物は色々あるのでどうやって精製するのか?。ちなみに不純物の中には強毒性や重金属もある)」必要が出るでしょうし。
※とはいえシリコンの材料って結局珪砂だから、
再利用しないで.....というのもあるんですけどね。
循環型社会とする場合、太陽光パネルの再資源化も重要な工程に組み込まれるでしょうね。
夜間はもちろんの事、悪天候時の電力不足に備えて蓄電しておくのは、今の技術ではコスト的に厳しいでしょうね
取りあえずは化石燃料発電/原子力発電の代替化の割合を上げるくらいかなぁ
揚水発電って手法もありますが、既存の水力発電を揚水発電に改造するのも立地条件的に無理でしょう
#てか、もうこれ以上自然破壊は止めてほしい😨
—
原発事故から10年 電力市場、自由化・脱炭素で激変
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ17A930X10C21A3000000/
そしてあらゆる河川の上流に木製水車を沢山作って回して発電するのが最もエコな環境保全と言うものでござろう。
ソーラーパネルなんて、使えなくなればただの粗大ゴミにしかすぎない。ゴミ増やして誰が始末するん?
現にそんな施設はあちこちにあり、環境問題化しているでござるよ。
太陽光って言うても、ほんまにか、みんな自分の家の屋根に置くのか?、故障したらどうするん?とか…
電気は基本的に同時同量なので、本当に貯めようと思えば、バッテリー並べるのではなく、超伝導蓄電池とかがまともに動かないとねぇ…
福井県激怒してるんですよね...
関西電力も地熱とか難しいのかな?
(無知な発言ですけど。)
だからって発電所を作ると、
環境破壊だからと言われるし難しい。

都市部にソーラー発電システムが乱立すると、熱による公害対策をしないと大変な事になりそうです。猛暑日には、ガンダムに登場したソーラ・レイみたいな兵器になりかねませんので…。(汗)
ソーラーパネルのせいで熱中症になったという事例もあるそうです。
自由化で増えたのは太陽光発電システムがほとんどで日照時間の
影響が大きい。送電設備を持たない電気事業者の送電設備を確保したいと政治的に分社化させられたとしか思えない
結局は夜間や悪天候時に電力会社から購入して消費者にかかった費用を押し付けしてるだけで、本当に安いのかと思えてきます。
日本の将来的にも四方を海に囲まれ、水源資源に困らない日本において脱炭素の本命は水素発電だと思います。 水素を燃やしても水しか出ないクリーンエネルギーだと思いますが
ソーラーパネルが増えた主な要因はFITによる固定価格買い取り価格がバカ高だったので、大儲けを考えた商社がこぞって参入し、都心ではなく、山林を切り開いてメガソーラーを設置していった流れです。
この国立環境研究所の推計は、あくまでも建物の屋根を利用して置いた場合の推計であり、基本的に自然破壊とは別物です。
また、各家庭や事業所に(EVも含めた)バッテリーが分散配置された近未来のお話という前提条件も読み落とさずに読んで下さいね。つまり、天気の良い日に過剰に発電した分をバッテリーに貯め、夜間や悪天候時にそのバッテリーから供給するという流れでしょう。
大手電力会社が「ソーラー+バッテリー」を推し進めている例として、東北電力が「太陽光発電と蓄電池の設備を各家庭に設置し、発電した電気を使えるサービスを2021年度後半に始め、主力である電力供給に次ぐ成長事業に育てる考え」という記事を貼っておきます。
関西電力も負けるな〜〜
日経「東北電、4月に新会社 ソーラー・蓄電池を設置」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO69430010V20C21A2L01000/
再生可能エネルギー発電促進賦課金
なんとかならないですかね (>_<
>> Dark Side of the Moon さん
> また、各家庭や事業所に(EVも含めた)バッテリーが分散配置された近未来のお話という> 前提条件も読み落とさずに読んで下さいね。つまり、天気の良い日に過剰に発電した分を
> バッテリーに貯め、夜間や悪天候時にそのバッテリーから供給するという流れでしょう。
従来型の二次電池(充電池)も劣化しますし、むしろソーラーパネルよりも劣化は早いものと思いますが?。
※現状の Li-ionで製品寿命(満充電認識時の容量が
新品時の半分程度になる条件)は大体 500~1,000サイクル
(充放電で1サイクル)と言われているので。
全固体電池が普及しても最終的に「化学反応で電力を蓄電する」という二次電池の構造や設計を転換できないとなかなかこの呪縛からは逃れられないと考えます。
※かと言って各ご家庭に燃料電池(FCスタック)設置するとしても
水素改質機のメンテとか色々ありますし。
電力の心配をしなくて良い一番の解決法は「そもそも電力を使わない」ってことだと思いますが、それをやると現代社会では「経済・社会体制に甚大な影響を及ぼす」ので、その選択は非現実的ですね。
追伸:
省電力化の技術開発は進んでいますけど、それでも
劇的に全ての電力消費を削減するのは難しいでしょうから、
まだまだ今後の技術飛躍が必要だろうなあと思っています。
ですから、そういう現状出回っている製品を前提に揚げ足を取るようなお話ではないのです。
早くて2050年といったタイムスパンでしょう。
「2050年までに電動自動車100%社会を目指す日本」
https://pps-net.org/column/61664

例えばこういう技術開発があちこちで進んでいることも知っておいて下さい。「リチウムイオン電池寿命を12倍に」
https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1611/24/news029.html
「リチウムイオン電池を4倍長寿命にする固体添加材」
https://eetimes.jp/ee/articles/2003/16/news029.html
>> Dark Side of the Moon さん
> ですから、そういう現状出回っている製品を前提に揚げ足を取るようなお話ではないのです。> 早くて2050年といったタイムスパンでしょう。
別に『揚げ足を取る』お話じゃないですけど?。
「2050年代」とのことですけど、それまで日本社会・経済が現状のままで持つのか?、も考えないとなりませんから。
※一応政府側は 2030年代以降、内燃機関車両の販売縮小
(実質的にHVなどへ移行)を打ち出してますけど、従来型の
内燃機関車と同程度の航続距離を出せるかどうかもありますし。
現実論として「その目標並行するまでのマイルストーンやら色々考えることが多い」ですし、理想論ではお話が進まないのも事実です。
泥臭いところを観ないわけには行かないので、いつかは覚悟しなけりゃならんでしょうけど。
追伸:
と、個人的には「どこかで腹をくくらないとならんのだろう」
なんて考えてます。
https://www.fnn.jp/articles/-/160379
世界中がそういう流れなのに、原発を辞める気が無い国は、負担を国民に押し付ける。
どんどん歪みが生じています(>_<)
電気完全に自給自足してみようかなぁ~
運動にもなり、一石二鳥!
風力とか地熱、水力も含めてあらゆる
選択肢を考慮しながら最善を目指して
頑張って欲しいですね。
EVの蓄電池を利用した余剰電力の融通も
様々な研究や実証実験をやってますね。
これも選択肢の一つと考えて研究を
進めていけばいいと思います。
再生可能エネルギーが成長産業となれば
国も嬉しいのでしょうしね。
どこかのゼネコンとJAXA当たりが技術的なブレイクスルーを目指してたような記憶が・・・。
で、実現したら、どこの電力会社がそれを買うのだろうか?
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/368549.html
要約すれば、
①部品をロケットで低軌道に打ち上げて組み立て、その後36000キロまで移動させることが想定されているが、低軌道への打ち上げは数百回必要とされ、仮に1機100億円のH2Aロケットで打ち上げるとそれだけで数兆円。なのでコスト100分の1のロケットの開発が必要。
②また低軌道から36000キロまでどうやって運ぶのか、この軌道間輸送についての研究もほとんど進んでいないのが現状。
③なので地上の太陽光や風力のコスト削減にお金をかけた方がいいという意見もある。
④では、なぜ政府は夢のような計画にこだわるのかというと、マイクロ波の技術が私たちの暮らしの利便性を高めてくれる可能性があるから。
>> 甘栗大好き さん
実現したら…J-Powerですかね…
https://www.jpower.co.jp/
そういえば、映画「太陽は動かない」でも、こんな話が出てきてました。
設備も低コストで出来ると思うのだが。特許申請しとこうかな。😁
各電力会社は、もっと多様な発電手段を、手に入れる努力をすべきだと思う。微細振動を電力に変える研究も進んでいるようだし。
炭素も系外に出さなければ、何も問題ないので。
>> 甘栗大好き さん
その手のアイデアは既に色々と実用化されています。一度検索してみることをお薦めします。
(特許出願できる余地は多分無いでしょう)
>> 甘栗大好き さん
もう一つ。「Green Heart:発電するスポーツジム」
https://wired.jp/2012/12/12/green_heart/
…利用者によって生み出された貴重な電力は、地方自治体との合意のもとに、地域の電力事業者によって集められ、電力網に組み込まれている。このようなジム2.0(夜は汗を流した人によって生み出される電力を照明に用いる)が置かれたショー・パークから、住宅のトースターまで電力が届けられるのだ。
…市民アスリートたちは、いままでに40,000kWを生み出したようだ。これによって、自分たちの住居に電力を供給している。住人5,000人の市街区にしては悪くない。もっとも、さらに向上できるだろうが。
>> corgitan さん
原発の特徴としていったん稼働を始めたら昼夜を問わず、燃料の核分裂を停止させるまで一年中ずっと一定出力
実際の電力需要は
昼間は需要が多いが夜間は需要が少ない
…というわけで
夜間は原発で発電した電力が余ってしまう
だから深夜電力の料金を安くして、深夜電力でお湯を沸かしてお風呂に使う…みたいなオール電化を電力会社が勧めたりするわけですが…
それでも余る電力を、位置エネルギーに変換するために揚水発電がある。
夜間、電力を使って下のプールから水を汲み上げて上のプールに移し、昼間の需要時に下のプールに落とすことで発電する。
いわば上げては下ろしまた上げては下ろし…発電するために電力消費している無駄。これは発電というより巨大な電池でしかない。
こうした自然破壊の仕組みを作らざるを得ないのは、原発が常に一定出力で、火力や水力のように加減を強めたり弱めたりで出力調整出来ないから。
太陽光は一定出力ではないけれど、弱めたり強めたりの調整は困難…と考えると
全ての発電方法を原子力や太陽光、風力に置き換えることは無理。
どこかで、火力や水力の、出力の微調整可能な発電方法のお世話になるしかない。
発電方法は様々あれど、需要と供給のバランスをとるのが電力会社の悩みどころなので、各家庭に巨大な電池があれば少しは自然破壊は減りそうなのだけど、その電池がゴミ問題を起こす、となると、
ホンマに悩みどころですね。
品川↔名古屋間で施工が進んでいる超電導リニアモーターカー
が消費する電力は、原発一基ぶん。
これを原発でまかなおうとすると、またまた深夜に電力が余ってしまう。
深夜にリニアが走るなら別ですが…そんな利用者はいないだろうし…
太陽光は昼間しか発電しないので、昼間の需要には貢献するだろうけれど、いかんせん出力が不安定。
電力は生み出しさえすればいいというものではなくて同時同量の「需給バランス」が保たれないと、周波数が乱れ、正常な供給ができなくなる。
この乱れで安全装置が稼働したために、北海道全域で大規模停電が起こったことは記憶に新しいニュースだと思います。
そう考えると、炭素の発生しない何かを燃やすか、水車を回すのが一番なのかな。
よっちおじさんが「水素」を提案してますが、水素だけが個体で存在していることはほぼないので、これも難しいところです。