気象庁 予測実力不足だった?
九州を中心に各地に記録的な大雨をもたらした梅雨前線は、15日も本州の南海上に停滞し、全国的に雨や曇りとなった。雨は3日から13日連続と異例の長さとなり、2年前の西日本豪雨の11日間を超えた。気象庁の関田康雄長官は定例記者会見で「(これほど長期間の停滞は)記憶にない」との認識を示した。
とのことですが、これってどう理解しますか?
確かに雨はずっと続いてはいますが、前線は日本列島からは若干南下していた時期もあります。
最近は天気予報もそこそこあてになるので、1週間前に私個人の予測ではなく天気予報を見た時に、中国は来週の週末にひと山来るのでヤバいな(つまり今日から2~3日)と思っていましたが、ほぼ予報通りに的中しています。
災害が起きたのでとりあえず言ってみました、みたいに感じます。
日本はこのまま一旦は危機から抜け出せそうな予感がしますが、中国のほうはひと山超えても問題山積で危険的状況はまだまだ長く続きそうで目が離せません。
16 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
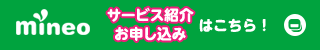

実力不足という発言はある意味「もっと予算頂戴よ」というメッセージなのかななんて
しかしこのままで良いのでしょうか?
かつて大阪では漫才師が面白くないと罵声を浴び、それで鍛えられて真剣に技能を磨きました。一方で東京では昔から面白くもないのに、とりあえず客が笑わなければならない暗黙のルールが存在します。
テレビなんて面白くもないお笑いでも後ろに多くの笑い声を入れて「面白そうな感じ」で演出してカバーしています。
日本中が東京化しつつあります。
厳しい指摘を避けることで現実から逃避してしまい、人間が弱くなってどんどん退化しているように感じます。
いわゆる「気候変動」が生じて過去の蓄積データに基づく予測に限界があるということでしょう。つまり過去に例がないから「そんなわけない」って人間(予報官)もコンピューターも考えちゃうところに限界があるのかな。
ダムも反対・遊水池も土地を取られるから嫌・堤防の嵩上げも陽当たりが悪くなるから嫌!
それでも住み続けますか?

金融ニュースを「お天気」で表するケースがありますけど、今の天候は金融市場と同じで変動幅が大きくなっているので、今後は逆に天気ニュースを「レンジ」で表す方がよいのかも知れませんね。日本の長雨予想レンジ「8日〜12日」とか。
思います。
・【しらべぇ】気象庁の予算が減り続けている衝撃
そんな中での起死回生策が話題
https://sirabee.com/2020/07/08/20162365553/
予算減少の対策として、気象庁ホームページの運営は民間業者に委託し、
広告枠を設ける様です。
…ここって割と良い枠だと思うのでmineoさんが広告を出されると良いかも
しれません。(^^ゞ
予算が削減されていくとなると「気象のインフラ整備だけを国がやって、報道部分は民間企業がやる」みたいな感じになったりするんだろうか。
すでに今もそういう形態なのかも知れないですけど、天気予報の仕組みって、自分にはよくわからないな。。。
ほとんどあてにならないので、自分で予測していましたね。
洪水警報とかはもう大爆笑モノで、大抵はやっとピークを過ぎたら警報が出るので、警報が出るとホッとしたものです。
私の目から見ると、最近の天気予報はずいぶんマシになったし見る価値もあるように感じます。
経験値が足りないのは仕方ない。
雲や風、湿度…そういう情報をビッグデータにして天候判断していたみたいな。
その人が現在得られる断片的な情報をもとに、事実と過去の経験から得られた情報をもとに短時間に導き出された高度な演算結果でもあります。
個々のパラメーターの重みづけや確率、不確定要素の取り扱いなどを数値化する作業を経ていないだけでもあります。
根拠を出せということを平気で言う人もいますが、逆に本格的に多くの人が関わってその根拠を作る作業に関わったことのある人は、その根拠の元となる数値がどういう経緯で決まったかも知っていますので、あまりそういう切り口での発言はしないように思います。
>元データもある程度(大半は?)は気象庁のデータが元になっている
その通りです。法的にも気象業務法によります(つまり国の許可が必要、逆に許可を受けずに予報業務を行うと50万円以下の罰金)。そもそもデータ収集の要である気象衛星(ひまわり)は国有であってそれしかないです。
許可の条件としては「信頼性を有し、気象庁の発表する防災気象情報と矛盾しない予報を安定的に供給できること」が条件なので、気象庁のデータを要は「どうかみ砕いて説明するか」であって、もちろん独自の解釈も付け加えてよいわけですが(だから桜の開花予報や梅雨明け時期の予想などは違ってくる)、気象警報を独自に発表することはできませんし、気象庁の注意報・警報と紛らわしい名称・内容の予報や、台風の進路予想などの災害に関連する現象についての独自の予想は制限されています。
独自に研究するのは全然OKでしょうけど。
なのでこの程度で良いのかもしれませんね。
といいたいけど「予想」じゃなくて「予報」
競馬の予想、占いとは違うんだよねぇ
気象予報士という国家資格もあるので、基本はルールに則った予報をしなくてはならないのでしょうし、ご指摘の通り、あまり独自見解で「今年は異常気象になる可能性が高い」みたいな警戒レベルの予報はだしにくいのかも知れませんね。
能力を測る指標であると同時に、単なる法的根拠のある既得権益の一面も持っています。
また、研究名目であれば多くの制限は取り外されているケースも多いですね。