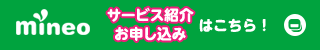[夢幻話]『元旦』
●新年にぴったりな初夢的なお話書きました。
マイネオ掲示板で不思議なお話をどうぞ、楽しんでいただけたら、幸いです。●
元旦に大晦日にいらなくなったものを
低質屋(リサイクルショップにあたる)に売って
そのぶんをお菓子をお年玉として当てて
親戚含め10人ぐらい子供に一人10種類、和菓子を配っていた。
元旦には、大人はちりめんゆたかを着て
子供は富士柄のシャツやTシャツを着ていた。
髪型は、現代人とあまり変わらない。
大家族みんなで、おせちや鍋、お雑煮を囲んで食べる。
そのまま、初詣に行き、おみくじをひいて、
大百へ(ショッピングモール)へ福袋をかいにいく。
とても広く、木造平屋であった。
プラスチックっぽいものがあったのでやはり今の時代なのだろう。
子供は、大人について行くだけ。
その後家に帰って家の前の道で遊ぶ。
大人は一年あったことをお正月休みまでずっとお酒を呑みながら家で過ごすのだ。
何年かわからないが、おそらく、今の時代だろう。
ただ、人は、機械に全く興味がなく、
部屋には何もなかった。
電気も知らないようだった。
言葉も昔のしゃべり方っぽいしゃべり方だった、
外国の貿易も江戸レベルなのかな。
わからない。
だけど、大広間の天井には大きな明かりらしきものがあったけど、夜は明かりが弱くなるので電気ではなさそうだ。
父にきいてみると、祖先の代から、神社にある、上石から、照石を切り、
家を建てる時につけられるらしい。
白板という明かりで、石のため、子に受け継げると言っていた。
つまり、太陽の光で白く光る石ということである。
石であるため、壊れることはない。
単純で、本物のエコロジーで、長持ち。
他は日を部屋に取り入れる形で、ろうそくもない感じだった。
親に聞いても機械のことは知らず、
黒鬼に言われたのかいと言われ、それ以上話してくれなかった。
その代わりお手伝いしてくれと石のことをおしえてくれた。
親は石のことを、なぜか太陽のこといって、
なまりがすごくて、何回も聞き逃した。
ひっけ、火付け石、太陽の光を石に通し、燃えるものにうつすと火をつけられる。
清石(あいげ)、水につけると泥を簡単に落とせることから厄払いとして使っているようだ。
ぼくは、それをみると、夏を思い出して
水浴びがしたいとおもった。
それを使って水をきれいにして遊んだ。
清石は夏はなぜか冷たく、冬は人肌に暖かく優しい水になる。
いつも遊ぶ子の一人が言っていた。
実はこの話は、私の夢の幻想の中の話で
驚くと思うけど
私は夢の中でそんな男の子と同化していたんだ。
機械もない世界で、同年代の子とも、
同じように遊べてほんと、楽しかった。
次の日は、いつも、神社にいってあそぶ。
元旦は、みこさんが祭りで使う御輿に向かって
何かお払いしてるみたいなことをしていて、
今日のみこさんは、薄い畳の上で墨で今年の福々の願いをかいてた。
みんながそういうからそうなのかと思うけど。
何をしてるか質問してみた。
やっぱり今年の村の幸せを願って書いてるみたいだ。
次の日から、鏡開きまで、神様のために緑の石をお供えするために、ずっと磨いたり作ってるんだって
それから、2月から、年末までぼくたちが引いてるおみくじを手書きでずっと一年中かいてるらしい。
みこさんは、みんなに幸せになってほしいと願って考えて書いてくれているようだ。
なんていいみこさんなのだろう。
それからぼくたちはみこさんに質問責めしていると、みこさんの旦那さんから、風車をもらってそれで、夕方まで走って遊んだ。
次の日は、村の木造工場に遊びに行った。
ぼくの親戚の家なので入り放題。
近所の子もついていって走り回った。
ぼくたちがくると、親戚は喜んで入れてくれる。
新年がやってきたって、笑顔だ。
そこでなにを作っていたかというと、
大百で売られていた、プラスチックみたいなもの。
半透明の石で、ひかりへんげというらしい。
簡単な、からくり仕掛けで鏡を動かして、太陽光を当てると石が変形して、ガムみたいに柔らかくなる。
それを素手で陶器の型に入れて水入れを作っていた。
それを興味津々にみていたぼくに、
説明してくれた。
『これは、ちいせいから、日に弱い。365を2通りすぎると、ダメになる。
火にも、凍(とう)になってもよい。
味噌樽は、厚くなって8りぐらいはよい』と言った。
つまり、よく使われてるものなら
基本的に凍っても火にも強いらしい。
それと日当たりのいいところは、すぐに壊れてしまうけど
日に当たらないところなら、二年持つということらしい。
さらに桶型のものなら8年は持つらしい。
他の工場にもいってみた。
保存容器で使うものばかりそれで作られていた。
形は現実のプラスチック容器からみれば
奇妙な形で少し大きい出っ張りもついている。
味噌用の桶は、まだ使いやすそうだった。
一番奥にある工場は、陶器を作るところだった。
熱いからくるなと何度も追い払われた。
親戚のおじさんひとりが集まれといって
ついてきたら、
とある、工場の一角で
親戚のおじさんのその奥さんたちが、昼ご飯もって並べていた。
ぼくたちは、おじさんと混じってご飯を食べた。
こいもと野菜の味噌汁、
しいたけと根菜の煮物とごはんだった。
たくさんあったのでほぼ食べ放題。
子供は、ご飯に夢中で大人はお酒に夢中になった。
だけど、それだけではいつもあきるので、
お腹がいっぱいになったといって、途中で元の家に帰った。
その次の日、三日、四日ぐらい村中を
わけもわからず、みんなで走りまくった。
おなかが空いたら、家に帰り、夕方になったら家に帰った。
元旦の週の週末になった頃。
怪しい人を見つけた。
フードをかぶった背の低い黒い陰の人だった。
ほとんどの子供は怖くて逃げたが
ぼくを含めて三人その人に声をかけてみた。
その陰の人は、浅いかごに小さな電化製品を入れて売り歩いていた。
『ドウ? リィ ダョ?』
と不気味な声でしゃべりかけてくる。
私は、ファミコンミニがあることに気がついた。
そのほかに、外国の日用品もあった。
電球、小型発電機、現実にある文房具の詰め合わせ、
外国雑誌、電卓、小型パソコン、車のキー。
背負いかごには、電灯、コイル、水筒、地図、でかい電話機。
今の村の環境には、オーバースペックで釣り合いがとれない、道具や機械が売られていた。
彼らには、奇妙で、恐ろしいものに見えただろう。
陰の人は、無言でどこからか、液晶テレビを取り出して、
村の天気ニュースを映して見せた。
私の知るニュースと変わりがなかった。
それをみたぼくたちは、怖くなって、逃げようとした。
私は、村に戻らないと元に戻れない気がした。
ぼくは、仲間と逃げた。
だけど、何かがおかしい、
なんだか、村が遠くなった気がした。
気がつくと村は人がいなくなっており、誰も住んでいなかった。
あんなに楽しかった、あの村はどこにいったのだろう?
空はくもっていた。
ぼくは、人がいないか村中を探した。
家の中。石が全て電気のものに変わっているようだった。
神社にいくと、神社も古くなっており、みこさんもいなかった。
木々をみてみると、年月も経っているようだった。
根元はきらきらと輝いていた。
前はここに半透明の岩があったはずなのに、
なくなっていた。そこにあったパワーもない。
おみくじを買うところも見たけれど、
おみくじの紙が散らかっていて日に焼けていた。
木造工場も、見に行ったけど林になっていてなにもなかった。
ぼくは、後悔した。
楽しかったあの『日』を返して!と何もない村で願った。