教育機会格差って
ネットを徘徊していたら以下の記事を見つけました
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/55353
自分に縁のある地方都市と、東京など大都会とを比較した教育機会格差について書かれています(と捉えました)
親の収入以外にこういうところも格差があったのかと
自分の中高生の時代を思い起こしてみて
自分が落ちこぼれた理由はこれだったか~、と妙に納得w
11 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
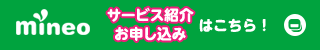


面白い記事なので記事を読んだ上で、いくつか情報をググってみました。地域格差が一番大きいのは東京と鹿児島や沖縄で倍程度の開きがあるようです。

しかし、所得の差だと400万円弱と1050万円強で2倍以上の差があるので、やっぱり所得の差の方が大きいんじゃないかな。まあ、所得そのものが地域格差があるので、ほか要因もあるだろうけど、結局、この記事の人は比較的裕福な家庭に育ったみたいだし、やっぱり経済格差の方が大きいんじゃないの?
しかも、所得の格差は政治解決できるけど、住む場所の格差は政治解決できないじゃん…。
面白い記事だけど、モヤモヤするな〜。
私は地方出身且つ地方在住者、且つ、東京にも数年住んでましたのでこの記事は身に染みてよーくわかります(特に3ページ目)。しかし東大を出てNY州立大に行ったというのはご本人の努力に他ならないが「経済的な余裕はある家庭に育った」という時点でスタートが違うんじゃないかとも思ったり。
学力そのものは秋田県だったり石川県だったり福井県だったり、ハッキリ言えば「田舎者」が上位だ、というのも事実としてはあるので、教育といっても高等教育以上のことを言っているのだとは思いますけれども、それはともかく本質的には「文化格差」の部分を言いたい記事なのではないかな、と感じました(それは結果的に教育格差にもつながっていく)。
こと、エンタメやサブカル方面のことを言い始めたらホント、それだけでは済まないわけですよ、東京と地方ではテレビのチャンネル数から違うし、地方には小劇場も寄席もありません。一番マズいのは「そういうものがある」ということにすら気が付かないことで、やっぱりそこはネットによってだいぶ緩和された面もあるかなぁとは思いますけどね。
これを大きく言えば(この方はNY在住だからたぶん次にそういうことを書くとは思うけれども)日本語圏にいることと英語圏にいることによる言語格差を知ってしまうとさらに愕然とすること、ですかね。要するに教育格差、文化格差って情報格差ですから(私は日本/日本語を否定しているのではなくて、多くの日本人が少なくとも義務教育で英語を勉強しておきながら実際には英語を使うことが出来ないことによって「知らないことが多過ぎる」ということを言いたい)。簡単に一言で言えばグローバル化ってやつですね。これもネットでだいぶ解消には向かってますが。
でもやっぱり、Google Homeの発売が日本では一年遅かったりするのって、今後「少子化=日本語話者が減ること」によって相対的に日本の国力が落ちますから、やっぱり中国語版とかの方が先に出来ちゃうようになるんだろうなぁみたいな危機感がありますね。
と、ここまで書いて答えは無いです。まぁ、最後は肌で感じることが重要でしょうね。昔の人が言った「百聞は一見に如かず」はまさにその通りでCDで100回聞く音楽より1回のライブだったりするわけじゃないですか、その後の人生に及ぼす影響の度合い、みたいなものは。
ただ、文中の指摘には同意できる部分もあります。
この理論だけではない、DNAの格差でしょうか?
地方であっても都道府県庁所在地ならば同等の県立図書館が在りますし、教育格差は殆ど無いと思います。
毎年のセンター試験会場を目にする機会の有無も、意識を変えるかも知れません。
そういう場所に1年くらいの短期間住むだけでも、教育への認識は変わるかと。
様々なご意見を興味深く読みました
紹介しておいて申し訳ないのですが、改めて執筆者のプロフィールを確認しましたら1987年生まれだそうです
あまりに記事の内容が私がいたころ(1960年代)と同じに感じたので、つい無批判で共感してしまいましたが、改めて読み返すといくつかの点で違和感を感じます
北海道にも大規模書店がいくつかあり、有名どころは札幌中心部にあって道外資本が多いのですが地元資本しかも釧路市に本社を置く大規模書店が釧路に開店したのは2001年だそうです
これは彼が14歳の時で高校受験を控えている最中であり、進学したらしい高校から極めて近い位置にあります
彼はこれを知らなかったのか、知ってて取り扱い内容に不満があったのかはわかりませんが地元の本屋さんレベルははるかに超えた規模の店舗です
また今現在の進学予備校の有無は知りませんが、2000年前後は20万人は切ったと言え地方の中核都市に学習塾がなかったというのは無理があると思います
これらの部分は文学研究者らしく誇張した表現を使ったのでしょうが、地元のエース級秀才がこういう書き方をするのはいかがなものかと思われます
私がいた当時も、彼がいた当時も、釧路では大学周辺以外のところで大学生を認識することは難しかったと思います
しかし、私の時代でも大学を具体的にイメージできていたかは別として、次のステップとして就職か進学かを選択する意識はあったように思います
そこそこできるやつは北海道大学を目指すのが一般的でした
彼が上京したり、東大に入学した時に感じた文化的ギャップは、地方から上京したもの共通のものがあるのではないでしょうか
突っ込みどころは幾つかあるものの、地域間格差を「体験する機会の格差」としてとらえたところは新しい視点ではないかと思います
この記事は解決策を示すためのものではなく、視点を一つ増やすことで何かを見出してほしいという願いをこめて一石を投じたのではないかと想像しました
格差を利用して、あるいは格差を乗り越えて最高学府で学んでも嘘つきになっちゃいけませんよね
(あ、余計なことを・・・)
ただ、東大もでて海外留学した頭のよい人が徹頭徹尾、感想文に終始していて、「なんのエビデンスも示していない」点が不思議なんですよね。
ネタ系のブロガーさんやYouTuberの発言ならともかく。
しかも、単なる個人ブログの記事ならともかく、一応は現代ビジネスという出版系のサイト記事ですし。
(まあ、出版系サイトのニュースであっても、微妙な記事があったりもしますけど)
どういう意図でこんな記事を書いたんだろ…。
九州を中心に0時限や夏休み中の課外が行れています。これは進学対応の予備校を学校が代替さぜるを得ない現状からです。また、ある県の高校で、有名国立大合格ならお金を出すというのもありました。学区の拡大で、郡部の学校より、中心部の学校へ行った方が“上級学校を目指す仲間がいる”ので、これまで進学していた地元の子が減ったことへの危惧からでした。
こうしたことを真面目に論じても読んでもらえないので、あのような記事の方が興味を惹きますね。
自分の出身校を「底辺校」だなんて、地元では炎上必至ですよね。
犯罪にかかわった同級生の話で自分は運良くそうならなかったの辺り、ちょっと読んでて大丈夫?と思いました。←母親目線。
どこに住んでても、地元愛ってあると思うんですけど「もっと意識を高く持ってほしい」というエールなのかどうなのか、たしかにモヤモヤしました笑
個人的には田舎に住む想像以上のハンディは、自宅から通える大学がないってことですね。
都会に住む友人が余裕で(そんなことないって言ってますけど少なくとも奨学金は借りずに何とかなる)子供を大学に通わせてるのを見て、どうしようもない格差を感じています。
でも子供が希望の職種に進めて、今では良い思い出です。
東京なら、良い大学を選んで目指せるけれど一戸建ての家は、持てなかった〜。