都心の人出がかなり多いんですけど.....?
ちょっと都心へ出る要件(口座がある銀行での手続き)と、確定申告の件もあって税務署へ行くついでに都心へ出てみました。(そのために有給取得)
なんだか数ヶ月前に比べて目茶苦茶人増えてない?、という感じです。特に夕方の帰宅時間帯。
東京駅から帰りましたけど、普通に乗客が増えてるんですよね。
オフィス勤務の総合職って「オフィスでお仕事しなければならない職種」でもないと思うんですけどねえ。
総合職である以上、プロとして「リモート業務できる環境整備」って必要な気はしました。
でも裏を返すと「日本の企業体制として『オフィスで顔が見える体制じゃないと仕事が進まない』等に業務形態を組み立ててきてしまった」のが、今のところ「生産性が云々」と言われる最大の弊害なんでしょうね。
※オフィス勤務なんて最悪現業(現場での業務)
じゃなくても良いと考えてます。
なんか、日本国内全体で「働き方改革」の考え方がどうも「現業が多いことに対する改善ってどうするの?」に至っていないように感じる毎日です。
追伸:
今後の「新しい日常」って結局
●セルフサービスポータル
●オンデマンドサービス
の2つがキーワードじゃないかと思いますし、
これはコロナ禍以前から「受益者が自分で動ける方式って必要」
と考えてました。
そうしないと責任の所在とか曖昧になりますからね。:(
12 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
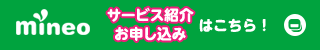

勝手に花見宴会、飲食店が早く閉まるから路上に座り込んで飲み会。等々
緊急事態があってもなくても気にしない人は気にしないんでしょうね。
解除後が怖い😓
>> akoyo@🪷。.*ෆ🪷₊✼୭ さん
スケジュールを既に提示してるので「それは織り込み済」って感覚なんでしょうね。単に店舗側だけ現状では「営業時間を制限してるだけ」って感じで、これじゃあ「何ら効果ないよね」と感じます。
ただし「個々の対応で感染拡大を抑止することは可能(基本的な防疫措置であるうがい、手洗い、こまめに消毒とか換気徹底など)」とも思うので、やはり「効果的に自重する(自粛ではないです。自重です)」のがよいのかな?、とは思います。
※自重するわけですから「空気を読んで
『こういう時はどうするべきか?』を考える」
必要あり、だと思うんですけどね。
世界的に見て「一般市民のコロナ疲れ」状態になっているの、個人的には「反動が怖いなあ」と思う次第です。この疾病をコントロールしきれない状態ですから。(確実な治療手段がないわけですし)
>> 西宮市民 さん
> 自分の勤めている会社にテレワークという文字はない。結局どの業種でも「現業前提の業務体制」というのが、リモート対応を阻んでいるようには感じます。
現業が必要な体制は重要ですけど、「それ、現業じゃなくても良いんじゃない?」という業種まで現業にしてる様に感じるというか。
他人との濃厚接触回避もありますけど、やっぱり「色々と工夫してうまく経済と防疫をバランスさせる施策」が必要だと改めて考えています。
まだ解除したないんですけどねえ
>> pmaker さん
> ええ、ええ、246も渋滞してましたよ(-_-;)> まだ解除したないんですけどねえ
ですよねえ?。
途中の移動で都営バス乗車→渋谷駅乗換え、となったんですが、実は「ICカードによるバス得の乗り継ぎ時間を超えてしまった」ので、結局2乗車分運賃を支払いました。(笑)
まあ、そこはそれとして.....。:)
なんだかこの状態だと「第4波」とかすぐに来そうで困ったもんだと思います。
→とてもじゃないけどオリンピックとか言ってられないですね。:(
追伸:
オリンピック中止を JOCと IOCのどちらから切り出すのか?、
正直「心理戦というかチキンレースでもやってるのか?」と思うくらいに
困ったものだと思います。
駄目なら駄目で「次の招致で対応」とかに切り替えないと何ともならんでしょうね。
色々と社会的にも頭が痛いお話です。
でも、現場からの「事務職だけ家で仕事するのは不公平だ」という不平不満を調整するのに手間取り、なかなか進みません。
子供を相手にするようなアホくさい状況ですが、中途半端に歴史ある中小企業の現実だと思います。
(労働組合という時代遅れの足枷…というと、色々と問題があるんだろうなぁ)
大学がオンライン対面併用制ですが、1年生(併用制しか経験せずテストの時しか出てこない人半分)と2年生(留年生以外は去年会ってる)とではやはり状況が違います。
オンラインの人の人脈がどうも…ってのをちょこちょこと聞きます。情報共有ができないとか、気軽に誰かに聞くとか、そういうのがオンラインだとできないのだろうと。
そうなると、「テレワークできるけど実質できない」は理解できます。
同じ場にいればながらで情報共有できるのが、テレワークだとそれのために時間を割く必要がありますし、その点で生産性低下は理解できます。
>> 水河 さん
でも、それを含めてのやりようだと思いますよ。同じ場に居れば情報共有できるって訳じゃないからね。なぜか隠す人もいれば、喫煙所じゃないと情報共有できないとか、会議じゃあえて誰も発言せずに会議後にコソコソ意見を言う環境(福島県の県民性らしいです。全ての人じゃないでしょうがTVでやってました。)なんてのもあるし。リモート会議だから得られるメリットも多いし、F2Fだからこそ生産性が上がる事もある。多分急激な変化に耐えられない人が多いだけだと思います。新しい環境に馴染めず辛いという気持ちはわからんでもないですが。
>> 水河 さん
> 個人事業主並みの独立性が有ればテレワークでいいんでしょうけど、組織としての> 行動を要する場合にテレワークって結構微妙というか…
それを言い出すと SNSとか、このマイネ王だって「原則オンライン」なわけで。
道具を使いこなすのは人間の頭のお話だと思います。
※つまりそういうパラダイムシフトに付いていけない方々が
「リモートだと云々」という側面もまたあるというか。
個人的には「そのために打ち合わせの数日前に資料は関係者へ公開→当日は資料の中から決定したい事項を調整」で済みますし、事実私自身はそれで業務進めてます。
全然生産性落ちてないですしむしろ向上してます。
要は「業務の進め方」とともに「今までの業務遂行がどれだけ face to faceを前提にしていたものか?」というだけ、と整理すれば分かりやすいように思います。
追伸:
業務でよく「属人化」とか言われますけど、これって「その人がいないと
業務が進まない」ってことですし、それは生産性を下げる要因でしかないので。
最悪「その人がいなくなっても業務が止まらないようにする(最終決定は
その人がいないと駄目ですけど)が重要」ですし、職務権限とか
いろいろな管理基準に依存するので、その弊害を取っ払うと
結構色々進むもんだと昨今とみに感じます。
→つまりそれだけ、日本は「縦割り社会」ですし、それを日本社会全体が
「実は望んでいる」と考えることも出来ます。
>> じんで@男女ン真っ黒改善傾向 さん
>F2Fだからこそ生産性が上がる事もある。そのうちVR会議が出てきてF2Fと変わらなくなりますよ。