NEC PC-9801F2
16ビット 8086-2 クロック周波数8Mz(5MHz)RAM 128KB
640KB FD×2 (FD×1,10MBHDD搭載モデルのF3 本体758,000円)
N88DiskBasic (別途 CPM/86 MS-DOS有)
本体のみで398000円
パソコンの歴史1983年
http://www.eonet.ne.jp/~building-pc/pc/pc1983.htm
パソコンの歴史1984年
http://www.eonet.ne.jp/~building-pc/pc/pc1984.htm
パソコンの歴史1985年
http://www.eonet.ne.jp/~building-pc/pc/pc1985.htm
パソコンの歴史1987年
http://www.eonet.ne.jp/~building-pc/pc/pc1987.htm
MacintoshⅡ HDモデル 948,000円
プロフェッショナル 仕事の流儀「家電の命、最後まで~電器店主・今井和美~」 10月22日午前0時20分 再放送
メーカーサービスでも修理ができない家電の修理をする電器店主の話でござる
持込まれた既に部品も調達できない家電の修理を一万点を超えるほど修理をしているようでござる
ネットがざわついたのが、町工場で組紐のデザインをしているPC-9801F2のお世話をしている電器店主、手持ちの電源部の電解コンデンサと交換して使える状態にした時でござる
「節子、それキャパシタや」
コンデンサとキャパシタの違いが分らないでござる
大阪の家電販売店に勤めていた頃に、修理したら使えるのに上から修理せずに新しいものを売れと言われて、メーカーで修理できない家電の修理をすることを決意したとの事でござる
番組は関係ないでござるが、起動しなくなったパソコンとか、お店に相談したら、1次電池を交換したら直るのに新しいものを買わされてしまった人も多い筈でござる
CR2032(CR2030)交換だけで数千円の修理代を払った人も多い筈でござる
(ちなみに、CR2032は、20mmφ、t=3.2mm、CR2030は、20mmφ t=3.0mmらしい、BR-とCR-は使用温度の範囲の差のようでござる)
ところで、CBT36VとかCBT45V知ってるあなた、通でござる
動いているPC-9801F2を見たい方はぜひどうぞでござる
たしか、Zaurus PI-3000の依頼もあったようでござる
がっちりマンデーでも紹介されたワープロ修理専門店「SBC修理工房」
http://www.sbc.tc/page5.html
機器の性能が上がって低価格になっても、日本の物作りが活発だった頃の製品は直してでも使いたい程のものでござる
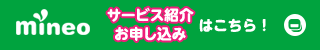

1991年からPC使いになったが、IBMコンパチでも50万円以上。NEC-PCノートや東芝Dynabookが20万円で出て、やっと月収で買えるようになった。
こりゃまた懐かしい、F2は私が所有した最初のパソコンです。
8086をV30に乗せ換えて使いました。2DDx2でのちのち苦労したんだよなぁ。
この頃のパソコンは筐体が鉄製だったのでやたらと重かった記憶があります。
BMWに乗って、BIGIのスーツ着てDynabook抱えてるのができるビジネスマンみたいな特集があったのではないでしょうか
DOS/V機では、ちょっとお安いEPSONもありました
互換機らしく鍵がついていたような
電人さん
そもそもFDは、98用とDOS/V用、APPLE用と言うそれぞれ互換性のないものが流通していたのではなかったでしょうか
フォーマットも9セクタと8セクタが混在していて、FORMATオプションを付けて一々やってたようです
3.5インチになると、セロハンテープで穴を埋めて2DDと2HDをごまかす技もできたように色々工夫できる時代だったようです
にちおしさん
2ドライブあったら、ディスクのコピーができたので便利でした
それと上にアプリケーションディスクを入れて、下にデータディスクをいれて使うと便利だったのでしょうか
9801もそうですが、当時のパソコンはスペースの問題もあったのか本体の上にモニタを乗せてもびくともしないほど頑丈だったようです
重いと言えば、PC-PR201もかなり重かったです