石炭火力の最新データから
資源エネルギー庁の最新データを基に石炭火力の二酸化炭素排出量を運用面から算出して見ました。
データとして関西電力舞鶴石炭火力発電所180万kw、超々臨界圧石炭火力で二酸化炭素排出量は一日あたり
A=0.795kg-co2/kw×24h×180万kw=3434400
石炭火力は揚水発電とセットとして運用されるため大河内ダム128万kw
運用時間は9時間
よって総発電出力は
B=180万kw×24h+128万kw×9時間=5742000
これから運用面での二酸化炭素排出量はA/B=0.627kg--co2/kwが算出される。
また、石炭ガス化発電は同様に0.56kg--co2/kwとなる。
ところで、日本の二酸化炭素削減には太陽光発電や風力発電が必要との意見がある。
太陽光パネル1枚当たり0.25kw国の定めた発電量2億kwの発電施設の10%を補うのに必要なパネルは6億4000万枚、風力は石狩グリーンエナジーにある風力発電一基1500kwで1330基が必要となる。
太陽光発電は最大電力で一日3時間、風力発電は一日24時間稼働するためこれを送電線に流すにはバックアップ電力又は蓄電池が必要となる。
バックアップ電力を使用する場合、オランダのデータから自然再生エネルギー1kw当たり火力発電又は原発1kwが必要となる。
このことを踏まえると自然再生エネルギーでは発電量が低いこと、バックアップ電力が必要なことから二酸化炭素削減効果はほとんど期待できないと思われる。
二酸化炭素削減には石炭火力の技術開発を含めた火力発電全体の二酸化炭素削減技術の向上が求められる。
また、二酸化炭素削減目標の7割から8割を占めると言われている原発は2012年IAEA年次報告から2020年代に入ると40年越えが32%となり5%が50年越えとなる。
これらを踏まえると世界の地球温暖化会議で策定された二酸化炭素削減目標は2030年には破綻へと追い込まれると見ている。

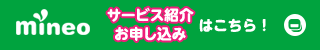

>運用時間は9時間
>よって総発電出力は
>B=180万kw×24h+128万kw×9時間=5742000
これだと石炭火力が24時間フルに発電した電力に上乗せしてダムが発電した電力が足されていますが、ダムの水を汲み上げるのに使われる電力を引かないといけないですね。
揚水発電の発電効率は約70%なので、「128万kw×9時間×10/7=1646万kWh」を総発電量から差し引いて計算する必要があります。
また、再生可能エネルギー発電のバックアップは世界的な流れとして蓄電池が採用されていくものと思われます。(コスト的に火力発電より安くなるのは時間の問題)
殆どを太陽光に頼る現状は無理があるとは思います。
太陽光パネルを製造するのに必要な電力はパネルの発電量の2年分と言われて
おり、製造に必要な電力の大半を火力で賄う現状では本末転倒な部分が
あるように感じます。
それと、山を切り崩して太陽光パネルを設置するのが環境に優しいのか
という疑問もあるので、そうした面をクリアした発電方法を模索していく
必要があるでしょう。
(A-B)+B=A
A:石炭火力の総発電量
B:揚水発電の総発電量
本来は揚水発電の揚水に必要な電力にたいして二酸化炭素が配分されるが満水時に配分された二酸化炭素の量と発電量全体に加算された二酸化炭素の量は等しいため発電時間を使用することにした。
>(A-B)+B=A
この式が成立するのは、揚水発電の発電効率が100%の時のみです。
実際の発電効率は約70%なので、世の中に供給される電力量はA(石炭火力の総発電量)より少なくなります。
一方で、排出される二酸化炭素の量は石炭火力の総発電量に比例するので、結果として、「蓄電せずに全て発電時に消費されるケース」よりも、「一部を揚水発電に蓄電して使われるケース」の方が、「g-co2/kWh」は悪化します。
石炭火力の稼働率は関西電力の場合、夏場の一時期を除くと68%で推移している。
これをベースに計算すると二酸化炭素排出量は実質は0.6kg-co2/kwを下回る数値が出てきます。
また、今回は書きませんでしたが太陽光発電や風力発電などのバックアップ電力を加算すると0.5kg-co2/kwを下回り運用面ではコンパウンドサイクル発電に肉薄する数値が計算されます。
稼働率は関係ないです。
石炭火力の「運用面での二酸化炭素排出量」を計算する際に、(揚水発電を含む全ての)蓄電池をかませればかませるほど、「g-co2/kWhが減る」ことはなく、「g-co2/kWhは増える」という当たり前のことを言っているだけです。
石炭火力が発電した電力をそのまま使うのが最も効率的であるのに対して、揚水発電を使うと、石炭火力で発電した電力の70%しか貯まらない(再利用できない)為に、「g-co2/kWhは増える」ということです。
買い入れ価格の高止まりがネック
日本は更に高い買取価格では 消費者はたまったのではない

日本国内の二酸化炭素排出量の議論よりも隣国の中華人民共和国🇨🇳の二酸化炭素排出量に日本は多大な影響を受けているのですね。環境問題を地球🌏規模で考えると、日本はとても小さな島国なので…。
これに対して揚水発電に対して石炭火力の電力を供給するわけだから
石炭火力の供給電力>揚水発電の発電量の関係が生じるのはわかります。
また、揚水発電の場合、定格出力の70%が供給されるのもわかります。
ただし、これを言い出すと石炭火力は熱効率が先進型超々臨界圧石炭火力は45%、IGCCが48%を考慮して二酸化炭素排出量を再計算する必要があると思われる。
しかし、それらの数値を考慮したとして誤差の範囲に収まるのではと見ています。
A:石炭火力が一日フル稼働した場合の二酸化炭素排出量を出す
B:石炭火力が一日フル稼働した場合に利用可能な合計電力量を出す
として、A/Bに係数を掛けることで求められます。
ここで、Aについては、ミディさんの計算式
A=0.795kg-co2/kw×24h×180万kw
で問題無いと思います。
しかし、Bについては、
①揚水発電を使わずに全て系統に繋いで消費されるのであれば、
B=180万kw×24h
②夜間に、「128万kw×9時間」分の電力を揚水発電に蓄電して翌日の日中に消費されるのであれば、その合計の電力量から、揚水に使われた電力を引く必要があるので、
B=180万kw×24h+128万kw×9時間−128万kw×9時間×10/7
になるということです。
発電機が発電した電力量の合計ではなく、最終的に系統に繋いで消費することのできる電力量の合計を求める必要があります。
いずれにしても、100の電力を利用して水を持ち上げてダムに貯めても70の電力しか発電できない揚水発電に蓄電するということは、どう考えても「B」が「180万kw×24h」より減るということです。
そこだけ理解頂ければ大丈夫です。
数字をいじくれば良くも見えるし悪くも見える。
揚水発電の蓄電により石炭火力から排出される二酸化炭素の量は変わらないが蓄電により他の火力発電の稼働率を下げること中でも石油火力から排出される二酸化炭素の量は確実に減少します。
原発が停止が続く以上ブラックアウトがいつ日本各地で生じる可能性があります。
北海道の地震でブラックアウトが起きました。
自然再生エネルギー特に太陽光発電は通電はできないどころか通電すれば再停電を起こしまた崩壊した太陽光パネルは復旧の邪魔もの。
また、自然再生エネルギーだけでは高々400万kwの供給電力さえ賄えない。
火力発電はブラックアウトさせないためには絶対必要だし二酸化炭素排出量を押さえる技術開発も必要である。
そのためには石炭火力もはずしてはならない電力システム。
コンパウンドサイクル発電が24時間稼働を前提に設計されているのかも疑問だし冷却時間が有無により耐用年数にどう影響するかも不明である。
24時間稼働の石炭火力との組み合わせが必要と見ています。
>揚水発電の減少は発電そのものから減少するものなのか
>タービンを稼働させ発電機を回す課程及び送電課程で失
>われる電力なのかによってベースとなる分母の数値が変
>わると思います。
ここに詳しく書かれていますのでご一読下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8262156.html
ちなみに、バッテリーに蓄電する場合でも、水素に変換する場合でも必ず電力は減少します。100%再生される蓄電システムはありません。ましてや、電力が増えることは理論的にありえません。
>数字をいじくれば良くも見えるし悪くも見える。
そういう数字の問題ではなく、元の石炭火力により発電された電力をそのまま送電するケースよりも、一部を蓄電したケースのほうが「総発電量が増える」ということは理論的にありえない、「総発電量は(蓄電ロスの分だけ)間違いなく減る」ということを理解して頂きたいということです。
念のために書いておきますが、ここで言っている「総発電量」というのは発電システムから外部(世の中)に供給される電力量の合計のことであり、発電システム内部にある個々の発電設備で発電された電力の合計という意味ではありません。
後者だと、一度発電された電力を蓄電して再発電すればするほど(蓄電ロスが3割あっても)増えていきますが、外部(世の中)に供給できる電力は次第に減っていきます。
エネルギーのベストミックスを目指してた、民主党政権以前の時代の電力計画に回帰して、安価で安定した電力体制を作るべきじゃないかと思います。
「エネルギー問題と原子力
エネルギーのベストミックス」
(関西電力公式サイトから)
https://www.kepco.co.jp/sp/energy_supply/energy/nuclear_power/nowenergy/bestmix.html
(べ、別に…mineo親会社に媚びてるとか…そ、そんなんじゃ無いんだからねっ!)
他方、もうひとつの論点はマクロの視点からの問題もあります。
現在日本が年間に排出する二酸化炭素は9800万トンにのぼります。
これを9000万トンに近づけるかその議論も必要と思います。
ロードベース電源として原発は60年廃炉を前提に2050年廃炉率が80%を越えるため次第にその役割を終えると思われます。
ベースロード電源として石炭火力が今後重要性が増して決ます。
今後建てられる石炭火力がUSC(先進型超々臨界圧型石炭火力)又はIGCC(石炭ガス化発電)になることが大前提として古い電力システムの更新や自家発電を石油からLNGにする場合の二酸化炭素排出量削減効果や現在規制の枠外にある11万5000kw以下の電力システムのうち石炭火力を除外するなどの検討も必要と思います。
また、自然再生エネルギーについて正しい報道がなされていない。
太陽光パネル1枚当たり0.25kwとして2000万kwの電力供給には6億4000万枚、風力発電1基1500kwとして2000万kwの発電として約1300基が必要です。
どこに配置するのかまた、配置が可能なのかの議論も必要と思います。その他送電線に流す場合のバックアップ電力から発生する二酸化炭素排出量もあります。
自然再生エネルギーが二酸化炭素9800万トンからの削減に寄与出来るのかの検討も必要と思います。
数値からの検討がなされるべきと思います。
分かりやすく書くと、石炭火力で100の電力を発電し、それを全て変換効率70%の揚水発電に変換した時、この発電システムから外部に提供可能な電力量の合計は、170ではなく、70になるということです。
従って、この電力量を使って二酸化炭素の排出係数を算出する必要があるということになります。
石炭火力バッシングの風潮に対して一石を投じたいというお気持ちは理解できますし、「数値からの検討がなされるべき」というご意見にも賛成です。
ただ、
①計算式は正しくなければ意味がないので、間違えたらすぐに修正しましょう。
②単位表記は正確に。ワットは「w」ではなく「W」
③発電量をいつも「kw」と書かれていますが、「W」と「Wh」の違いは理解されていますか?。「W」は電気の瞬間的なパワーの大きさを表し、「Wh」は電力(kW)に時間(hour)を掛けた電力量の単位です。つまり、「kg--co2/kw」ではなく、「kg--co2/kWh」です。
④計算は正確に。(B=180万kw×24h+128万kw×9時間=5742000とありますが、正しく計算すると、54720000kWhです。)
といった基本的なところをまずは押さえて下さい。
宜しくお願いします。
(私からはこれでお終いにします。)
国の二酸化炭素排出量の係数の算式は二酸化炭素排出量総計/発生電力量総計で計算されます。
石炭火力から発電する電力は送電線をを通ることにより電気抵抗Rにより減少する。
これを算式にすると
石炭火力から発生した電力Pは電流I、電圧VとするとP=IV
また、送電線で消費される電力W=I^2R
これが揚水発電の発電量に0.7となる。
しかし、供給される電力計算の場合であり二酸化炭素排出量との関係はないように思われる。
つまり、この石炭火力の夜間電力をつかい揚水発電の下のため池からダムに汲み上げる。
この汲み上げた水を放流しタービンを回し発電機を回して電力を供給する。
発電機を回し発生した石炭火力と揚水発電の電力の総量を分母として石炭火力で発生した二酸化炭素を分子として二酸化炭素を計算する計算式には影響を与えないのではないかと思われる。
すると、石炭火力で発電した電力を全て揚水発電に回せば、なんと総発電量は二倍になり、CO2排出係数は半分の0.4kg--CO2/kWhに減りますね。
さらに、揚水発電を9回繰り返して使えば合計で総発電量は10倍になり、CO2排出係数は1/10の0.08kg--CO2/kWhに減るのでそれだけで二酸化炭素削減目標を楽々達成できますね。
しかし、0.7の係数は最終的に工場や家庭、事務所で使われる電力つまり最終的に供給される電力ではその係数は必要となります。
最終的に供給される電力計算では必要ですが二酸化炭素排出量と発生した電力との関係では使わないてはいない。
石炭火力の場合、石炭の使用量が熱効率に置き換わり二酸化炭素の発生量が算出されます。
これをベースとして分子の数値がまた総発電量をベースとして分母の数値が確定します。
揚水発電の満水時に発電総量から発生する二酸化炭素(数値はゼロ)の計算式でも二酸化炭素排出量/揚水発電の定格出力で算出されています。
温暖化会議の資料を見ても定格出力で計算することをベースとして電力の二酸化炭素排出量は決定されているようです。
揚水発電は単なる「バッテリー」に過ぎません。そこに貯めたからと言って総発電量が増えるような魔法のバッテリーではありません。
…まあ、採掘コストとか度外視した上での話ですけど
でも国内炭鉱は掘れば赤字と言われ石炭掘るならまず国の金庫からと言われた昭和40年代に次々閉山しました。
採算取れないなら埋蔵量多くても宝の持ち腐れ。
海外炭に頼るしかないですね。
ただ、海外炭入れるなら防衛上の視点や国益重視を見据えた海外輸入をして頂きたいですね。

もう少し円安になれば、輸入炭と競えるかもしれないですよ。https://www.kaneko-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/event/20140225/20140225-5.pdf
日経「石炭火力 埋まる外堀 国際会議閉幕、特効薬なく」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35227110R10C18A9916M00/
…石炭は石油や天然ガスに比べて価格が安い「経済性」や、資源国が多い「供給の安定性」で優位性がある。一方で、環境への負荷の高さが致命的な弱みになっている。
…会議では弱みを克服するため、「クリーンな石炭技術の追求が必要」との声が大半を占めた。Jパワーと中国電力は石炭をガス化し、燃料電池と併用して効率を改善する発電所の実証試験を紹介。
…ただ、石炭の環境性を抜本的に改善する道筋は見えていない。実証中の高効率の発電技術でもCO2の排出量はガス火力よりも多い。地中へのCO2の埋設もコストが高く、日本では事業化する場所などのメドは立っていない。
…風力や太陽光の低価格化が進む中で、海外で石炭は経済性でも脅かされつつある。逆風が強まる中、技術革新の速度を上げて環境問題を克服できるか。石炭の生き残りへ残された時間は少ない。
「丸紅、石炭火力の開発撤退 再生エネにシフト」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35435680V10C18A9SHA000/
「Jパワー、石炭火力建て替え断念 採算見通せず 」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29975030Y8A420C1EA2000/
「銀行や生保、石炭火力の投融資に高いハードル」
https://newswitch.jp/p/13433
「西欧では既に最後の石炭火力発電所が建設済みの可能性」
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-09-27/PFOQXO6S972A01
為替は昭和40年代の1ドル360円時代でさえ国際競争力がなく赤字。
しかも、埋蔵量は世界の至るところに散らばっている。
しかも、太平洋炭鉱始め数鉱があるだけ。コストが高い、技術者はいないては勝負にならない。
で、1985年に中曽根がプラザ合意で一気に円高にしてからは、円高のために日本の炭鉱の復活の望みは絶たれたとか。
まあ、常識的に考えればとても無理ですよ。
(あくまでも、2002年時点と同じ価格で取引できれば、の話ですが。)
チャート的にはいつ円高ドル安がきても不思議ではない状況であった。
1978年7月178円をつけ中段持ち合いにはいり高値201円安値278円のボックス相場。
1985年2月262円をつけた時点で逆三像型中段持ち合いを形成
持ち合い離れを確実に示していた。
そこにプラザ合意。
120円前後までの円高は読み取れていた。

個人的見解は別にして、歴史的流れは下記の通り。①日本円の対米ドル為替レートは、第2次大戦後1ドル=360円の固定相場制が続き、1971年12月のスミソニアン協定で1ドル=308円への切り上げを経て、1973年2月に変動相場制へと移行した。
②変動相場制導入直後に260円台まで下落した後、1973年秋のオイルショックをきっかけに300円近辺までドル高円安が進行。1970年代後半から徐々に円高が進行し、1978年末には180円近辺へ。
③その後、ソ連のアフガニスタン侵攻などの地政学リスクによるドル高で1980年代前半にかけて250-260円の水準へ。
④そして1985年9月のプラザ合意でドル安誘導政策が決定すると急速に円高が進み、1986年末には160円へ。その後もドル安円高が進み、1987年2月のルーブル合意によるドル安の歯止めも効かず、1988年には当時の史上最安値となる1ドル=120円まで円高が進行した。
⑤日本では円高不況の対策として超低金利政策を推進したことでバブル期へ。1990年には160円近辺まで円安が進行。
⑥その後、バブル崩壊とともに1990年前半には円高が進行し、1995年4月には一時79円70銭台の史上最安値(円高)を更新。以降1998年にかけては円安が進行。
⑦日本のバブル崩壊以降は省略。
【参考までに、「プラザ合意」とは】
1985年9月22日、過度なドル高の是正のために米国の呼びかけで、米国ニューヨークのプラザホテルに先進国5カ国(日・米・英・独・仏=G5)の大蔵大臣(米国は財務長官)と中央銀行総裁が集まり、会議が開催された。
この会議でドル高是正に向けたG5各国の協調行動への合意、いわゆる「プラザ合意」が発表された。具体的な内容として「基軸通貨であるドルに対して、参加各国の通貨を一律10〜12%幅で切り上げ、そのための方法として参加各国は外国為替市場で協調介入をおこなう」というものであった。プラザ合意の狙いは、ドル安によって米国の輸出競争力を高め、貿易赤字を減らすことにあった。
発表翌日の9月23日の1日24時間だけで、ドル円レートは1ドル235円から約20円下落した。1年後にはドルの価値はほぼ半減し、150円台で取引されるようになった。
あなたが上げた為替の背景は歴史的真実を表すにすぎない。
後付けでいくらでも付け加えが可能な内容である。
それは素人には通用じても為替を業とするトレーダーには全く意味のない後付け講釈にしか過ぎない。
しかも、このチャートは学者さんが好きなログチャートまあ対数チャートだし為替のトレーダーからすると全体の流れはそうなの程度にしかならない。
私はただ歴史的な流れを解説したただけであって、トレーダーがどうしたこうしたって、ミディさん大丈夫ですか?
この対数チャートからわかることは1973年308円台に突入し1978年に178円の円高をつけたあと逆三尊型中段持ち合いにはいり約8年もちあったあと
1985年2月262円をつけ天井相場に
天井相場において1995年に78円と2008年に75円をつけダブル天井を形成し2015年125円まで戻しもみ合いに
予測としては三番天井をつけたのか否かがはっきりしないが時期は不確定な部分はあるが1995年78円からの戻り安値1998年147円の流れの中にあると見ている。
今のところ円安の流れは本格化していないが年内一杯見れば円安の流れはほぼみえてくる。
そう見ています。
チャートを見せられたので解説と私的な予測をさせていただきました。
悪しからず
会話が成立しないようなので、私はこれにて失礼します。
プラザ合意以前の水準とも言われています。
・「実質実効為替レートで見れば円安が進んでいる」とは?
https://www.ewarrant-sec.jp/article/実質実効為替レートで見れば円安が進んでいる/
円相場の単純な対数チャートでは昔より円高になっている様に見えますが、
これには物価上昇の数字が入っていない事に注意する必要があります。
要するにドルの実質的価値が以前より下がっているのですよね。
なので、90年代とドル円相場が昔と大きく変わっていない様に見えても
90年台の1ドルの価値よりも今の1ドルの価値は低くなっているので実質的
には円安になっています。
外国人観光客が日本に沢山来ているのも、米トランプ大統領が貿易面で
日本に対して厳しい発言が多いのもこれが原因でしょうね。
iPhoneが年々高く感じるようになるのも実質的に円安傾向だからでしょう。
という訳で、今の円安状況で海外へ輸出して価格競争力が無いものは
この先も厳しいのは間違いないかと思います。
>円相場の単純な対数チャートでは昔より円高になっている様に見えますが…
皆さん誤解されているようですが、私が貼ったグラフは対数チャートではなく、ただの長期チャートです。
また、貼った理由はミディさんのプラザ合意に対する理解が一般的な捉え方と随分異なるようでしたので、プラザ合意前後の円ドル相場の流れについて少し解説するために用いただけです。
従って、とりあえず90年代で解説を終えています。現状が円安なのか円高なのかとか、今後どう展開していくか、といったことにはここでは全く触れていませんし、あまり興味もありません。
さらに言えば、少し前に書いたように、円安がもう少し進めば輸入石炭の価格が(2002年当時の)国内石炭の価格に近付き、追い越すこともありうる、という話の流れで書いていますので、実質実効為替レートではなく純粋な為替レートが直接関係することになります。
以上参考まで。
それは失礼しました。
いずれにしても相場の世界は常識はずれが正解を導きだす世界。
チャートの世界は江戸時代の米相場が起源だしアメリカのトレンドラインはオランダのチューリップ暴落が起源とされその歴然の中で一定の法則をルールを見いだしたもの。
これに対してあなたの考え方はメディアの考え方と言った方が正しいかも知れません。
チャートに事実だけを羅列しているにすぎない。
トレーダーの世界では多種多様な考え方が混在しています。
歴然的な出来事と為替相場を時系列に並べただけ。
それだけの意味しかない。
為替の世界では、読み違いや勘違いは命取りですので、大怪我をされないよう十分お気をつけ下さい。
では、これにて。
購買力平価説にマクドナルド指数と言うのがあります。
このマクドナルド指数を使い物価水準からを各国の実質金利を割り出し金利水準との比較により為替相場の予測する。
金利を利用して価格が決まる先物取引ではよくやられている方法です。
これと同様にiPhoneも各国で使われるためiPhoneも指数化されることも十分考えられますね。
特にドイツは総電力の40%を賄っているが全廃した場合自然再生エネルギーでは発電量が少なくブラックアウトの多発が懸念されている。
しかも、原発はゼロ。
ブラックアウトが多発すれば自然再生エネルギー反対の国内運動へ発展する可能性も伝えられている。
日本でも太陽光発電の無秩序な開発に法の網がかかるようだしね。
太陽光発電はサウジなど一部の国を除くと新設は規制強化される可能性が高いと思われる。
(円安ドル高のトレンド)
円高になるには、主に下記のようですね。
・円金利上昇📈
・海外へ輸出力増強📈
・海外から輸入額の減少
・魅力的な投資先増(証券、企業、不動産)📈
・財政信頼性向上📈
・デフレ経済
・為替介入
デフレが終わると、上記円高要因が減り、
円安ドル高要因が増えそうですよね💵💰
資源輸入価格も増加傾向と思われますよね
100年後の孫の世代は、下記ですかね。
・石油、原子力資源の枯渇(希少化)
・石炭発電は継続
・自然エネルギーも継続
・個別に自然から発電して使う
石油、石炭などは生成に万年かかったのに、
それを大幅に上回る速度で使い過ぎたかも。