食卓の未来 値上がり続ける農作物にどう対処するか
連日のニュースで、厳しい暑さによってトマトが枯れたり、これまでの気候では当たり前だった農作物の収穫が危ぶまれたりする話を目にするたび、日本の食卓に大きな変化が迫っていることを実感します。
ただでさえ、暮らしを支える食べ物の値段がじわじわと上がっていると感じる昨今、この値上がりの流れは一時的なものではなく、今後、農作物の価格が常に高い状態になるかもしれない、という懸念をもつようになりました。
これまで日本は、比較的安定した気候のもと、品質が高く、手頃な価格で多様な農作物を享受してきました。しかし、その安くて美味しいという食の常識が、今、大きく揺らいでいます。背景にあるのは、次の3つの深刻な問題です。
一つ目は、容赦ない気候変動の猛威です。地球温暖化による気温の上昇は、日本の農業に壊滅的な影響を与え始めています。トマトが枯れ、リンゴやブドウの色づきが悪くなり、お米の品質が落ちつつあります。
これらは、すでに全国各地で起きています。これまで栽培に適していた地域がそうではなくなり、収穫量が減ったり、安定した生産が難しくなったりすることで、市場に出回る量が減り、価格が上昇するのは避けられません。
異常気象による災害も頻発し、一度の被害で広範囲の農作物が失われるリスクも高まっています。
二つ目は人件費の上昇です。農業は、作物を育てる段階から収穫、選別、梱包に至るまで、多くの人手が必要です。しかし、日本では少子高齢化が進み、農業の担い手が不足しています。
この人手不足を補うためには、当然、人件費を上げざるを得ません。これは、農業経営者にとって大きな負担となり、そのコストは最終的に私たちが購入する農作物の価格に転嫁されることになります。
三つ目は流通費の高騰です。収穫された農作物が私たちの食卓に届くまでには、輸送、保管、販売といった複雑な流通網が関わっています。
ガソリン代や電気代といったエネルギーコストの上昇、運送業での人手不足による賃金上昇などは、流通にかかる費用を年々押し上げています。
これらのコストもまた、私たちがスーパーで目にする農作物の価格に上乗せされ、値上がりの一因となっています。
つまり、価格上昇は恒常的な流れになりつつあります。これらの要因はそれぞれが独立しているわけではなく、複雑に絡み合っています。気候変動によって収量が減れば、希少価値が高まり価格が上がります。
人件費や流通費の上昇は、たとえ収量が安定していたとしても、生産・供給コストを押し上げます。そして、この収量減とコスト増のダブルパンチは、今後、農作物を購入する際の価格が、一時的ではなく、ずっと高い水準で推移することを示唆しています。
このような状況を考えると、暑さに強い作物の導入は、生き残りのための一つの選択肢になるかもしれません。これまで当たり前だったトマトや米の品種にこだわり続けるだけでは、安定した食料確保が困難になる時代を迎えています。
もちろん、新しい品種が既存のものと全く同じ味や風味を持つとは限りません。そこには、ある程度の味や風味の犠牲を受け入れる必要が出てくる可能性が十分にあります。しかし、食料そのものが手に入らなくなるリスクを考えれば、これは避けられない選択であり、むしろ積極的に取り組むべき課題です。
私たちは今後、多様な気候に適応した新たな品種を受け入れ、その新しい味覚や風味を楽しむ心構えが求められるでしょう。そして、農業技術の進化に期待しつつも、消費者として、この気候変動の現実と、それに対応するために農業が直面している課題を理解し、支援していくことが重要です。
日本の食卓の未来は、この厳しい現実にどう向き合い、どんな選択をするかにかかっています。
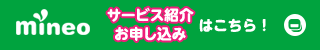

> ある程度の味や風味の犠牲を受け入れる…
ワイン🍷の世界では、オルタナティブ品種というものが導入され始めていますね😋
>一つ目は、容赦ない気候変動の猛威です。地球温暖化による気温の上昇は、日本の農業に壊滅的な影響を与え始めています。トマトが枯れ…
先日もテレビでもやってましたが、
トマト600kg“全滅”…西日本では猛暑日続出 『記録的短時間大雨情報』も相次ぐhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c6aebb32c43a2e017061790ee41f8f2f65cb24d8
ただ、こういうニュースがあると私は捻くれ者なのでいつも反対のことを考えてしまうのですが、確かに一部地域ではこういうことがあるけど、果たして日本全体や世界全体でトマト栽培に壊滅的な影響を与えているのかどうかってことで。(メディアっていうのは普通のことはニュースにしないので)
ちなみに私の家では狭い畑に一昨年中玉のトマトを植えました。そのときも夏場高温で「地球沸騰化」と騒がれたけど、私の家ではトマトの収穫量が過去最高を記録しましたよ。
ところで植えたのはデルモンテのトマト苗。抜群です。去年、今年は同じくデルモンテのゴーヤを植えていますが、これも実付きがすごい。
>> Y. Daemon@ポリアモラス さん
そうそう、初心者のプランターでもそこそこ収穫出来ますよね。↓
自分でつくるしかない😞
↓
土地が無い
↓
移住するしかない
↓
地方に人が戻る
という可能性も…
まともに野菜すら食えなくなったとき…健康を犠牲にしてでも都会にしがみつくか。それとも地方へ移住するか。
>> Y. Daemon@ポリアモラス さん
ロシア民をソビエト崩壊時の危機から食料不足を救ったのがダーチャ。日本の家庭菜園の少し規模の大きなもの。このくらいなら日本で実現可能でしょう。
画像は添付のURLから。
ロシアの「ダーチャ」に学ぶ暮らしのヒント<前編>「自分の生活は自分で守る」
https://globe.asahi.com/article/13066308
私たちの場合も ベランダのプランターとかよく言うけど一人暮らしだとベランダもないようなアパートも多いですよね
>> スパイシーニョ@300%ぶっ飛び計画 さん
土地が無い↓
移住するしかない
農地は買い叩かれ別物に変わってますよ?
このスレにも書きました。
https://king.mineo.jp/reports/303686
農協はじめてはじめて物語は戦後まもなく農作物が一般消費者に届く前に闇市に流れてた。
それを防ぐために生産農家は一括して農協に収めるようにしたわけです。
それから80年ぐらい経過して、闇市野郎が多重請負に形を変化させた結果、毒ともいえる農産物の高値になってるとも言えますね。
弱い言い方をすると流通の複雑化。
毒といえば、17年前に三笠フーズを巡る事故米不正転売事件でカビ米が食品市場に流通してしまった件。
この時も流通経路が複雑でカビ米を追う事が困難を極めた事が報道されていました。
どうなったかというと当時の農水大臣を辞めさせる事で流通経路を温存してしまい現在に至ってます。
あの時、きちんと対処すればテンバイヤーに無駄銭のくれてやる事もなかったろうに。
そしてマイネ王の面白さに関して農水大臣の一例とあげた儲けた業者を切り抜き火消を謀るアカウント達があります。
ただの与党嫌いなのかテンバイヤーなのか日銭で雇われたタダの火消屋なのか。。。
https://king.mineo.jp/reports/311042
>> がんばるじゃん@中世"JAP"ランド さん
思い描いてる地方が違うのかもしれませんね。僕は所謂ド田舎に住んでいるので、耕作放棄地は藪になってるんですよねえ。
野菜が買えなきゃつくらないと…っていうのも極端な例なことは承知しているのですが、当たり前クライシスが起きれば従来の都市生活って維持しづらくなるから、段々と人口配分も変わる(変わらざるを得ない)のかな~と🤔
>> スパイシーニョ@300%ぶっ飛び計画 さん
自給自足は一つの例で、別の例として前回レスで紹介したURLには2017年に農地転用について規制緩和が行われた事も書きました。別スレでは転用が厳しく制限されていると思ってる方がおられるようですが昔の話です。
https://king.mineo.jp/reports/308918
なお、このスレで別の方がロシアのダーチャについて都市/地方で切り分けしてますが
先に紹介した朝日新聞GLOBE+の記事には全く別の切り口となっています。
>> ジョニー23k さん
地域によりますね。また、土壌にも。どの地域で栽培されていますか。
>世界全体でトマト栽培に壊滅的な影響を与
猛暑に強く、塩害にも強いトマトがあります。味は食べた人によると全くおいしくないそうです。
>> スパイシーニョ@300%ぶっ飛び計画 さん
地方が簡単に移住者を受け入れてくれればいいですね。