マイナ保険証のスマホ利用について整理
iPhoneにマイナンバーカードが搭載されるところ、Twitter上で「また医療機関が苦労する」的な誤解されているので、それを解こうと思う。ちなみに私は医療機関で導入に手伝わされた人間。多分今回も私がいじることになるであろう。
顔認証カードリーダーについて、あのカードリーダーは
・NFCカードリーダー
・PCのサブディスプレイとしての機能
【付属のソフトを利用して】
・OCRによるカード読み取り(綺麗な顔写真データを読むのに必要)
・本人確認用の顔撮影
・顔写真データと本人顔を比較して、PINスキップ処理の開始コマンドを送る機能
・サブディスプレイにマイナ保険証用の画面を投影する機能
(例:案内・同意画面、PIN入力時のテンキー表示など)
で構成されている。
さらに、社保基金(健康保険を統括しているところという認識で良い)提供のソフトにより、
・NFCカードリーダーに置かれたマイナンバーカードと通信する機能
(例:PIN入力、PINスキップ処理により電子証明書の読み取り
マイナポータルアプリがやってることと大差ない)
・PINスキップ処理の開始指示の受付
(上記付属ソフトから送られてくるコマンドの他、
窓口係員の操作でも発動できる)
・マイナ保険証の保険証情報を取得する機能
が実現されている。
と、考えると、あのカードリーダー自体がすっごく特別なことをしているわけではない。
最小限の構成なら
・普通のカードリーダー
・テンキー
・社保基金のソフト
(あとパソコン)
でマイナ保険証に対応できる。
以上を総合すると、顔認証は(本来の仕組み的には)おまけであり、この前提でいくと、意外と医療機関が対応するべきことは少ないことがわかると思う。
つまり、iPhone搭載のマイナンバーカードをマイナ保険証として使わせたい場合、次のようになる。
・PIN入力を求める場合
→パソリみたいなカードリーダーと、テンキーさえ追加すれば良い。ソフトウェア的に何かしなきゃいけないことはない。(なお、顔認証カードリーダーの制作会社が協力的なら、テンキーだけそっちに表示することもできると思う。)
・iPhone上で認証してPIN省略する場合
→同じくカードリーダーを設置する。テンキーは任意になるかと。改修対象は社保基金のソフト。通常の設定なら勝手にアプデされる。
意外と簡単…じゃない?パソコンにUSBポート余ってれば一瞬だし。費用も5000円くらい。
ちなみに。顔認証カードリーダーが勿体無いという主張について。
カードリーダーの税法上の耐用年数は5年。マイナ保険証が始まったのが2年前、対応義務化が去年。iPhoneマイナの開始が来年。結構なカードリーダーはiPhone対応する頃には「税法上の寿命の半分近くが過ぎている」(ちなみに、我々は「税法上の耐用年数を過ぎるまでは、カードリーダーを捨てるな」と指示されている。補助金導入のパソコンも同じく)
OCR対応のため、カードを置ける範囲をカバーするカメラが必要なところ、大型化するスマホに対応するには、カード読み取り部を広くする必要がある。
カード読み取り部が広くなるなら、カメラを(マイナ保険証を使うにしては意味なく)広角にしたり、カメラを遠くしたり(≒カードリーダー自体が巨大化)しなければならず、ともすればどちらにせよOCRに対応しない開放タイプのカードリーダー部は必要だったともいうことができる。
スマート差がなくなるとはいえ、2年以上も無駄な機能を持たせておくくらいなら、増設のほうが無駄な出費ではないと考えるけども、どうだろうか。
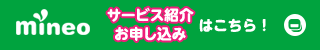

残念だか、一時的に10割払ってねとも言いづらいだろうし。
>> magrodon さん
かざして通らないときはマイナンバーカード券面記載事項を書いた書面を提出させ、合理的な推測に基づく自己負担割合を収受して対応することになろうと思われます。(現在の初診患者等で障害発生時はこの対応。請求はある意味言い値で通る)大病院の場合は、ほぼ確実にシステム担当者が1人はいます。電カルがダメになると困るので。
実際の事務員による運用は現行と変わらないはずです。運用上の原則は自律駆動ですので「勝手に電カル/レセコンに保険情報が降ってきた」が変わらない限りは一緒です。
診療所レベルの場合、シス担はおらんでしょうが、この場合補助金導入で想定されていること以上のことはしてないところが多く、USBポートの繋ぎかえで済むこと考えると、よっぽど厚労省/デジ庁が放任主義を取るか、「USBとはなんぞや」のレベルの人しかいないみたいなケースでない限り、「指示さえされればできる」が多いかと。そもそも保守契約とかで日ごろお世話になってるシステム会社はいるはずですしね。運用が変わらないのは上と同じです。
>> ホットウォーター さん
災害時だろうとなんだろうと、その時使えないときは、マイナンバーカードの表面の券面情報(裏面は使わない。いわゆる4個人情報のみ)と、わかる限りの保険証情報を「自分は保険証持ってます」っていう申立書に書いてもらい、それを医療機関に提出してもらう取り扱いです。そのあとは2つの方法があります。
一つは災害時モード。通常はマイナンバーカードの電子証明書を使って保険情報を拾いに行くか、保険証の記号番号を見て有効無効を見るかしかできませんが、後刻このモードを起動してもらう(基金への電話連絡が必要)ことで、表の券面情報で拾いに行くことができます。
もう一つは不詳請求。本来は保険証の記号番号を付けて請求するところ、券面情報だけつけて「あとはそっちで調べて」と請求先に丸投げする方法です。
「保険証持っています」の書面は書かせることになってますが、そもそもその紙は医療機関限りで、別にそれ以上提出する先なんかないですので、「表面コピー、あとは自己負担割合は書いてもらう」でもなんとかなるんですよね。
自己負担割合が誤りでも、言い値で通ります。(「高齢者だったから1割しか取ってない。本人も1割って言ってた」って言ったら9割くれる。「実は現役並み所得」って時に、差分の精算は保険者がすべきこと、という考え方)
加えて、再診患者であれば「前回の保険証が有効か無効か」であればいつでも確認はできます。
>> 水河 さん
患者の手間は、無いので安心しました。マイナンバーカードの偽造事件が起こっていますが、
スレ主様の投稿によると顔認証は結局おまけみたいな扱いとのこと。
だから偽造カードでなくても、他人や兄弟姉妹の顔情報で
パスできた事例があったわけか。
スマホにマイナンバーカードの情報を
登録できるようになった場合、気になるのは、
スマホを無くしただけで
人生終わったという中国本土の若者のルポルタージュ事例が
今後、この日本でも起きるかもしれないという不安。
中国本土では日本よりもずっと前から
スマホに様々な情報を集約する動きがあって、
そのため便利になった反面、上記のような事件も起きているらしい。
偽造カードやスマホを使った
なりすましを防ぐような仕組みについては
どのような対策が取られているのでしょうか?
セキュリティ上、お答えできる範囲で構いませんので、
よろしければご回答願います。
マイナンバーの情報も保険証の情報も(さらに医療情報や免許証も?)
すべて1つのデバイスに集約することのリスクについて
国はどのような対策によって安全を担保しているのでしょうか?
自治体がAWSを利用している時点で不安を拭えないのですが。
>> Nul さん
マイナ保険証の機能に限局した話をすると、基本的にマイナ保険証では券面よりもその中身の方が重要になります。すなわち電子証明書です。(券面は顔認証=PINスキップの自律駆動には必要だが,最終的に4桁のPINさえ入力できれば使える)したがって、券面だけ偽造できたところで問題は起こり得ないと言えます。
仮に電子証明書が偽造できるとなると、仕組み上ネット全体に対する信用性が失われますので、結局はローカル物品であるマイナンバーカードのことなんか気にしてる場合じゃないと思いますよ。
スマホを落としたらの件につては、Apple Pay同等の認証が走るとすれば、「iPhoneを落としたらクレカを無制限に使われた」という事例があるか、ということを考えれば、少なくとも現在報道発表されている中で推測できる仕様として、そのような心配をする必要がないことは自明だと思います。
>> 水河 さん
ご回答、解説ありがとうございました。おっしゃるように
某市議会議員の偽造マイナンバーカード被害例を見ても
今はまだICチップの情報までは偽造されていないようです。
今後、電子証明書のクラッキングが実現しないことを望みます。
iPhone自体のセキュリティについては私も信頼しています。
しかし現在、そのセキュリティを毀損するような計画を
当の日本政府が進めようとしていることも不安材料の一つです。
すなわち、App Store以外のサイトによる
アプリダウンロードを可能にする動きです。
政府の「デジタル市場競争会議WG」によって
画策されている動きがそれです。
今は確かに問題ないかもですが、
今後もしこのWGによってサイドローディングが実現したら、
クラッキングの憂き目に遭う恐れを拭いきれません。
まあ、これはこのスレッドの本題とは違う話なので
与太話として扱っていただいて結構です。
話は戻りますが、
このたびはいろいろと解説いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
個人番号カードのICチップは内容をサルベージしようとすると破壊される仕組みと聞いております。スマホではデータ削除で対応しているようですが、物理破壊では無いのでセキュリティ的に大丈夫なのでしょうか?
そのうち生体データも顔画像の一部ではなく、お隣の国の様に十指の指紋を記録するように成るかもしれませんね。
そうなると、お隣の国の出張犯罪者の特定が容易になると思いますが、お隣の国が日本人の為に犯人逮捕に協力してくれるかは非常に疑問ですが。
>> うめちゃん2号 さん
>保険種が変更になったので、再登録できずこれ役所に聞いたら自動的に更新されるそうです。
なので更新されないのは、健康保険組合がアナログ処理しかやらず、デジタル処理(資格抹消あるいはアカウント削除)を怠っている可能性が有ると。
厚労省も文書による通達だけではなく、今はYoutubeやニコ動があるので操作動画をアップして周知すれば良いと思います。
認識されず10割要求されたと言う噂が有りますが?
>> うめちゃん2号 さん
異字体について請求自体は保険証の記号番号でやってますから、問題はないです。加えて、マイナ保険証で降ってくる時点で代替漢字に置き換わってます。(そもそも対応していない漢字を送りつけれるわけがない)
仮に代替漢字でない別の文字を送ってしまっても、補正処理の上、「補正した」という通知が来ます。
どう頑張っても特定できない場合に限って、返戻があります。この点、むしろ紙保険証のほうが書き写しミスが起こり得ますのでリスクが高いです。また、医療機関側がマイナ保険証の内容を信用して請求している場合は、言い値通りに通ります。(あとは医療機関側の直接の請求先と、保険者との関係で処理)
認識されず10割は、過去にはあったようですが、現行は上記のとおりとなります。
反映遅れについて
本来は5日以内の反映です。この点、そもそも健康保険組合は1500程度しかなく、組合のための人員が確保できないようなレベルのところは協会けんぽですので、デジタル音痴である可能性は低いものと考えられます。むしろ、アナログによる届がどこかで滞ってる可能性のほうが想像できます。
なお、喪失の反映遅れの場合、上記の通り、マイナ保険証上は古い情報が有効ででた、というケースではそれを信用して送りますし(困るのは反映遅らせた側)、新規の反映遅れの取り扱いは災害時と同様、券面を控えて不詳請求になります。
この場合は、遡及等により加入したこととなった保険者から返金を受けるべきものです。
ただし、医療機関において柔軟に対応されることが妨げられるものでもありません。