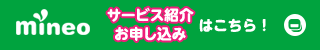甍の波と雲の波
「端午の節句」 葛飾北斎
オランダ公使がシーボルトを通じて北斎に描かせた日本の風景
ライデン国立民族学博物館蔵
愛知県高浜市やきものの里かわら美術館
http://www.takahama-kawara-museum.com/
現在、「浮世絵師の見た甍」展開催中
高浜市は淡路瓦、石州瓦と共に三大瓦と言われる三州瓦の産地
で屋根の描かれた浮世絵を数点
日本に瓦が伝来したのは西暦558年
以降江戸中期までもっぱら葺かれたのは寺社や城、武家屋敷
当初禁止していた吉宗が防火対策で町屋にも奨励するようになりました
大坂は高津神社の西北付近の土で焼いた
そのため今も周りより土地が低くなっています
瓦町という地名や地蔵坂の地形に名残があります
江戸では中之郷町、今の墨田区吾妻橋辺りが産地
「富嶽三十六景 江都駿河町三井見世略図」
北斎
寅さんの名セリフ
「見上げたもんだよ屋根屋のふんどし
田へしたもんだよイナゴの小便」
いや見えませんね 股引で
「富嶽百景 鳥越の不二」
北斎
貞享元年(1684)、従来の「宣明暦(せんみようれき)」に変わる「貞享暦(じようきようれき)」が出ると、江戸幕府は天文方(てんもんがた)を新設し(寺社奉行支配)、「貞享暦」の制作者である渋川(しぶかわ)春海(はるみ)をこの役職に就けました。こうして編暦作業は、朝廷の陰陽寮(おんみようりよう)から天文方に移りました。
翌年、渋川は牛込藁町に「司天台(してんだい)」を設置しましたが、天文方そのものは、本所・神田駿河台・神田佐久間町・牛込袋町を転々とします。天明二年(1782)、浅草鳥越(とりごえ)に「頒暦所(はんれきじよ)」が置かれてようやく落ち着くわけですが、この時、高さ九メートルに及ぶ観測施設が併設されたことから、天文台・浅草天文台と呼ばれるようになったのです。関係者には、天文方筆頭として「寛政暦」の編集を主導した高橋(たかはし)至時(よしとき)や、シーボルト事件に関わって文政12年(1829)に獄死した高橋景保(かげやす)がいます。
北斎が浅草明王院(みようおういん)地内の五郎兵衛店に転居したのは、天保元年(1830)のことです。 編暦・天文・測量・地誌・洋書翻訳を職務とする天文方は、当時の学問の最先端を行く場所でした。多くの人が出入りし、多くの珍しい道具を備えていました。
青森県立郷土館研究主幹 本田伸
屋根と言えば火消ですかね
「東京名所八代洲町警視庁火消出初梯子乗之図」
三代広重