またまた石炭火力ですが
石炭火力について語る前に原子力発電は2012年IAEAの年次報告から推計して2030年には40年越えが世界の原子力発電の80%を越えてくる。また、全体の5%は60年廃炉となる。
新規の原子力発電はアメリカボーグル、VCサマーで一基2兆円。
中国でも海陽原発、山門原発が建設されているが一基1兆円。
これから新発の原発は無理。
これから温暖化会議の二酸化炭素排出量削除計画は原子力発電の廃炉に伴い2030年代には破綻を示している。
では電力を何で補うのか。
コスト面からは石炭火力が最適。
しかし、二酸化炭素の排出量やチッソ酸化物やイオウ酸化物は多いとの問題を抱える。
しかし、最新型石炭火力(先進型超々臨界圧や石炭ガス化発電)ではイオウ酸化物やチッソ酸化物は無縁となりつつあり二酸化炭素もかなり低下してきている。
しかし、世界の潮流は未だに亜臨界圧石炭火力で煙黙々型。
これを先進型石炭火力やIGCCに変えるだけでも電力部門の20%の二酸化炭素削除が期待できる。
コスト面からは二酸化炭素削除には石炭火力は欠かせないと見ている。
48 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。

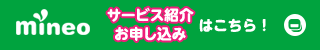

太陽光発電は昼間は良いけれど…
水力発電、日本では水利権が大きくいや、老害の頭の固さが問題です。
ああ、バイオマスも老害が反対だし。
太陽光発電も老害が先にうまく土地を……した妬みが多く転用許可が下りない。
あれ?新しいエネルギーは老害が邪魔をしている!

上図は「日本全体に占める火力発電のCO2排出量(2015年度実績値)」です。これを見ると、石炭火力のCO2排出量が日本全体の2割強、発電部門全体の5割を占めていることが分ります。(発電量シェアでは3割強なのに。)>これを先進型石炭火力やIGCCに変えるだけでも
>電力部門の20%の二酸化炭素削除が期待できる
石炭火力をIGCC等に置き換えていくことには賛成なのですが、注意しないといけないのは、あくまでも【先進型石炭火力に変えると10%、IGCCに変えると20%、当該発電所の二酸化炭素削除が期待できる】ということですので、CO2シェア50%ほどの石炭火力を『全て』IGCCに置き換えられたとしても、電力部門全体の10%(日本全体の4%)の二酸化炭素削減に過ぎないということです。
石炭火力の置き換えだけで「電力部門の20%の二酸化炭素削除」を実現するには、石炭火力『全て』の二酸化炭素排出量を40%削減する必要があります。
以上参考まで。
どこまでのスパンで見るかですが。
太陽光/風力などの自然エネルギー発電の過供給には、揚水発電や燃料電池で電力を保存するなどが必要ですね。技術革新が待たれるところです。
バイオ燃料とまだまだ価格で市場に見合うようにはなっていません。しかし、有望ではありますね。
地熱発電はお勧めなんですが、何故か進みません。おかしな国です。
未来では衛星軌道上の太陽光パネルから地上に電磁波で、電力を送っていることでしょうが、遠い未来の話ですね。
世界の亜臨界圧型石炭火力からの転換。私が出したデータでインドのデータが参考になります。
インドは亜臨界圧が多く二酸化炭素排出量は1000g-co2/kwを越えている。
日本は亜臨界圧を全廃し石炭火力全体で800g-co2/kwを平均で下回ることが重要だと考える。
他方、途上国では亜臨界圧石炭火力を旧来型超々臨界圧に変えるだけで確実に800g-co2/kw代まで下がってくる。
IGCCならベストだがコストの問題をクリアできるかが課題。
旧来型の超々石炭火力ならなんとか建設コストをクリアできる水準にある。
まず、そこからスタートすることが必要と思う。
中国やインドなどにある旧式石炭火力を日本の先進型石炭火力に置き換えられたならば…というお話でしたか、失礼しました。
資源エネルギー庁の試算によれば,石炭火力大国である中国・アメリカ・インドの3国に日本の石炭火力発電のベストプラクティスを普及するだけで,CO2排出量は年間15億2300万トン(2015年度の日本の排出量の115%に相当)も削減されるということですから、それが実現されれば二酸化炭素の削除効果は大きいと思います。
ただ、低コストであることが石炭火力を使い続けている主な理由ですから、中国やインドなどがまだまだ使える旧式石炭火力を前倒ししてリプレースせざるをえない状況に追い込んでいくことが可能なのか、ですよね。
化石燃料は発電量からは切り離せない。太陽光は1枚0.25kw.風力は一基1500kw,
これで日本に限らずの電力需用わ賄えるのか。
九州電力では太陽光発電など自然再生エネが供給過剰で発電制限を行ったがこれは休みに稼働させるバックアップ電力の処理能力を越えた場合ブラックアウトを起こすから。
自然再生エネは補助的電力に過ぎない。
その為に期待されているのが、燃料電池です。余った電力を水素で貯蔵する考えかたです。まだまだ十分に実用的な規模ではないのですが。
古くから揚水発電などもあってもっと活用されるべきなのですが、いうてもダムですから、なかなか整備されませんね。
あくまで、スパンの違いです。いろいろと技術革新や政治決断があれば少しは短めのスパンで実現するかもしれません。
未来永劫永遠に化石燃料を使い続けるとは考えておられないかと思います。
まずは、既存の技術でいうのも判りますが、先進型石炭火力やIGCCにすべてを置き換えた後に、また脱化石燃料の発電設備となると現実的ではないでしょう。燃料電池施設など、年内に本格稼働する予定のものもあります。こうしたものは、どこかでブレイクスルーがあると、一気に普及する可能性があります。
今 出来ることと、これから出来ることは平行して行われて行くのかと思います。
燃料電池を組み込んだシステムになるようです。
期待されます。
自然由来のエネルギー源でCO2排出の対象外でありながら24時間安定供給可能で、火山国の日本では全国的に電源の宝庫があり、長所ばかりのように思います。
「インド:安価な太陽光発電 石炭火力発電所プロジェクトに再考を促す」
http://coal.jogmec.go.jp/info/docs/170616_05.html
…太陽光発電は、突然、インドでは最安値の電力源になった。石炭火力発電所プロジェクトは、取引先探しに苦労するか、過剰供給力のためにプロジェクトを中止するかの様相になっている。
…国営火力発電公社は、インド最大の発電事業者だが、RattanIndia Power社の当初石炭火力発電所を予定していた敷地に、太陽光発電パネルの敷設を検討している。
…太陽光は、現在では、新設の石炭火力発電所より50%は安価であり、このコスト安が、過去3カ月間で、新規石炭火力発電所の入札が延期または中止された理由だと語った。
「陸上風力発電、太陽光発電の電源コスト、半年で平均18%も下落。新規の石炭火力等の既存電源はすでに競争力を失う。BNEFが分析」
http://rief-jp.org/ct4/78283
…BNEFは再エネ価格の着実な低下で、新規の石炭・ガス火力発電はコスト面でも競争力を失った、と評価している。
…再エネ電源の活用に影響の大きい蓄電設備のリチウム電池のコストは、2010年の1kWh当たり1000㌦から2017年は209㌦へ、79%の価格改善となっている。
…例えばインドでは、陸上風力のベンチマーク価格は1MWhで39㌦。1年前に比べて46%の改善。太陽光発電は41㌦で同45%改善と、グローバル平均より倍以上の改善率となっている。インドでは石炭火力は68㌦なので、再エネ・ベンチマークのほうがすでにコスト的に安価になっている。
…再エネ発電と蓄電設備のLCOE低下によって、新規の化石燃料発電の競争力は急速に低下しているわけだ。
(続く)
「CSIRO / AEMOの調査によると、風力や太陽光に蓄電設備を組み合わせても石炭より明らかに安くなった」
https://reneweconomy.com.au/csiro-aemo-study-says-wind-solar-and-storage-clearly-cheaper-than-coal-45724/
「中国とインドが悟る、石炭に魅力なし」
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1703/24/news110.html
…中国とインドで100以上の石炭火力発電所の開発プロジェクトが凍結。二カ国で68GW分の発電所の建設が停止。全世界でも建設の開始が62%減少――石炭火力発電所の動向を追う米End Coalが2017年3月21日に発表した内容だ
…2016年は大きな転換点だ。中国はほぼ全ての新規プロジェクトを停止した。クリーンエネルギーの驚異的な成長によって、既存の石炭火力発電所が『冗長化』されたからだ。2013年以来、新たに必要になった全ての電力は化石燃料以外から得ている
以上参考まで

自然再生エネはコストパフォーマンスは地域差がかなりある。私が記憶している記事からは
太陽光はサウジは1kw当たり1セント台まで低下の記事は読んだけど
気象条件がちがうからその他の地域では当てにならない。
ところで、世界の電力を見てドイツ、アメリカ、デンマークは石炭火力に頼る比率が50%弱。
また、オランダでは風力に頼ったため電力不足が起きている。
理由は老朽化した原発が相次ぎ停止したこと。
急遽廃炉が決まった石炭火力を総動員して電力危機を乗り切る構えだしフランスは二酸化炭素課税に反対しデモが頻発している。
鍛を誤るとブラックアウトが世界各地で多発するのではと見ています。
唯一の最適解は無く、地域状況に応じてプランを立てることが必要ということですね。
とりあず日本は国としても、地熱発電、もっと進めたらいいんじゃないかな?
いや、ホント。

ミディさんOutlook 2010 だとデータは2009年ですので、さすがに古過ぎますね。
とりあえず 2015年のデータを上にアップしておきますが、6年で石炭火力の比率はかなり減少してきています。
デンマーク:48%→24%
アメリカ:49%→34%
中国:79%→70%
増えているのはインドと日本(原発停止の影響)くらいでしょうか。
インド:69%→75%
日本:27%→33%
そのインドでも(上で紹介したように)近年は石炭火力から再生エネへのシフトが急速に進んでいるようです。
http://coal.jogmec.go.jp/info/docs/170616_05.html
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1703/24/news110.html
以上参考まで
確かにコスパが自然再生エネに有利な国はダークさんの言う通り。
しかし、問題はコスパが有利でない国。
このデータから原発か石炭火力かの選択となっている。
先進国でもフランスなど温暖化会議に異義を唱える国が一部に見られ出してきている。
また、2030年代に入ると原発60年廃止が一気に加速しその割合が2040年代には80%に達する。
その中で不足する電力供給をどう構築するのか。
課題として提起される。
また、電力使用量を減らせばとの議論がある。
しかし、今車はガソリンから電気への移行期にある。
日本だけでも原発8機(ガソリン使用量からの概算)約800万kw時は必要とされる
また、日常においても大工や左官など電動ドリルやタッカーなど電動ものなしには釘ひとつ打てなくなっている。
こんな中で電力使用量を減らすのは容易ではない。
原発、石炭火力、ブラックアウトのバラグラムをどう解決するのか。
それが問われている。
ただし、電力不足から亜臨界圧型石炭火力の再構築だけは願い下げだ。
原発の代替えとしてIGCCや先進型超々臨界圧型へ特化した石炭火力が求められる。
環境省に圧力かける以外ゴーサインはない。

Jijingさん>とりあず日本は国としても、地熱発電、もっと
>進めたらいいんじゃないかな?
世界の地熱発電の概要は上図の通りですが、日本は世界第3位の地熱資源を持ちながら、2005年以降ほとんど発電利用が進んでいません。
ここはもっと頑張って欲しいところですね。
とは言え、世界一のアメリカでも345万kWと原発3基分の発電利用に過ぎませんので、過度の期待もできないかもしれません。
「世界の石炭火力を高効率のものに置き換えることでCO2排出量を20%削減できるのでは?」という当初の問題提起と、「2030年代に入ると原発60年廃止が一気に加速しその割合が2040年代には80%に達する。その中で不足する電力供給をどう構築するのか?」という日本固有の問題は切り分けて議論されたほうが良いかと思います。
前者については、ミディさんも理解されているように、インドや中国、オーストラリアといった石炭火力大国は、コスパ的に再生エネに有利な国であり、大きく再生エネにシフトしています。
なので、「旧式の石炭火力を高効率の石炭火力に置き換える」ということは起こりにくく、再生エネに置き換わっていくものと考えられます。
特にオーストラリアでは、再生エネに蓄電池を加えても(既に)石炭火力より安くなってしまったということです。
これはもうどうしようもない時代の流れですね。
後者(日本の問題)についは、「2030年代に入ると原発60年廃止が一気に加速」という問題提起自体が無意味です。現在稼働している原発の数はその2030年代時点に残る数より少ないのですから。
ちなみに、電力需要は年々減ってきています。
それはLEDを始めとした設備機器の消費電力低下と建物の高断熱化などによる負荷の減少によるもので、この傾向は今後益々加速していくでしょう。
ご心配のEV(電気自動車)への移行にしても、現在の電気自動車で計算すると結構な電力が必要に思えますが、大きく普及する20年後30年後の電費(1kWh当たりの走行可能距離)は現在の2倍以上に改善されると考えられていますし、日本の人口も3〜4割は減っていますので、必要となる電力量はミディさん想定の1/3くらいには減ると思われます。

参考に、最近の電力需要の推移です。「震災から5年間の電力需要、全国で10%縮小するも地域で開き」
http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1608/08/news037.html
…震災直後の2011年度に大幅に減少した後、2012年度と2013年度は1%前後の微減にとどまったが、2014年度と2015年度には2%前後の減少率になっている。LED照明をはじめ電気製品の消費電力が着実に小さくなることを想定すると、今後も全国の需要電力量は年2%程度のペースで縮小していく可能性が大きい。
2040年代には正確には2040年代後半ですがIAEAの2012年の年次報告から引用しました。
2040年迄に60年廃炉で32%、2050年迄に80%の世界の原発が停止する。
この間にアメリカではボーグル原発、中国では海陽1,2号機、山門1,2号機だけが稼働が確実視されている。
日本が手掛けたイギリス、トルコは相次ぎ中止に追い込まれまた、韓国がサウジで手掛けた原発も事実上棚上げに。
これから推計して原発に二酸化炭素削除を依存していた部分は確実に世界の二酸化炭素排出量は確実に増加する。
実際、中国も石炭火力を減らす計画の背景には原発稼働の増加を見込む。
しかし、実際には山門原発や海陽原発以外は原発稼働は無理のようだ。
その中で電力供給と二酸化炭素削減をどう両立を計るのか。
ところで、オーストラリアでは北部の州や砂漠地帯中心に太陽光発電が行われており海沿いには風力発電が点在する。
しかし、南部にいくにつれ石炭火力やLNG発電に置き換わる。
また、グレードバリアリーフで有名な西海岸では海洋から一定方向から風を受けるため風力発電に適しているがロブスターで有名な東海岸では風力発電は吹く風が一定方向ではないため風力発電は発電効率は低下するらしくあまり風力発電は見られないようだ。
オーストラリアは地域の特性を利用した発電が行われている。

ミディさん>2040年代には正確には2040年代後半ですが
>IAEAの2012年の年次報告から引用しました。
そうでしたか、世界全体のデータということですね。
了解しました。
ただ、世界全体で見ても、2015年の総発電量に原発が占める割合は凡そ10%(↑)に過ぎません。
これが2050年には半分の5%まで下がると予測されていますが、仮にゼロになったとしても、たかだか10%の減です。今後30年で10%の減少分くらいは再エネの増加で十分カバー可能ではないでしょうか?。
(=現代の便利で快適な生活の一部を捨てられるか)
にも踏み込まざるを得ないと言われていますが、どうなりますことやら。
何らかの技術的ブレイクスルーが起きて、便利さ快適さを失わずに
省エネルギーに向かえば最高なのですが・・
参考までに、我が家では徹底した節電を行っています。
照明器具は電球・蛍光灯を間引きして節電
エアコンの設定温度は、冷房30度 暖房16度です
例え蓄電池が向上し走行距離が伸びたとしても日本国内に目を向けると省力化投資や無人店舗の増加、建築現場での電動器具、最近大工さんに見せてもらったがコンクリパイル打ちタッカーまで登場している。
これなどは蓄電池容量もでかく電力使用量は半端じゃないと話していた。
その他、家庭用でも暖房器具もエアコンは言うに及ばず石油暖房器からガス暖房に至るまですべて電気を使用する。
また、床暖房などもかなりの普及してきた。
他方、世界に目を向けると途上国でも電力供給が安定したところを中心に電力使用量が増加の一途を辿っている。
電灯電力に加え空調、暖房、調理、建設現場、工場、あらゆるところで電力が使われる。
日本はじめ世界の電力は増加することはあっても減少することはない。
最近古い電気料金表の束が出てきた。
あの頃家族もこどもたちも独立しておらずまだエアコンは購入していたがガラケーで電話していた。
その後、暖房は石油からガス暖房にきりかえ、床暖房もつけた。
LEDに家明かりを取り替えたが電気使用量は今のほうが多い。
さすがにテレビはあまり見なくなったが代わりにI-PATやスマホは手放せなくなった。
電気使用量は人口減少には関係なくいや人口が減少すればそれに反比例して増加する。
ましてや途上国ならこれから電力需用が本格化。
電気使用量は増加することを前提にしないと方向を誤ると思う。

ミディさん>日本はじめ世界の電力は増加することはあっても減少することはない。
「減少することはない」と言われても、私が日本の電力需要の推移グラフを示した通り、日本においては疑いようのない事実として減少しています。
この事実に目を背けずに将来予測をして頂ければと思います。
一方、世界の電力需要については、まだしばらく増加し続けるでしょう。
上のグラフはBloomberg による予測ですが、OECD諸国はほぼ増減ゼロなのに対して、非OECD諸国は大きく増加するとされています。
つまり、「日本も世界も全て増加する」ということではなく、「先進国は増加停止もしくは減少に向かい、中国やインドなど発展途上国はまだまだ電力需要を伸ばす」ということになります。
以上参考まで。
供給量をベースにロス電力を想定し待機電力を加味して使用量を決定する。
使用量はあくまで推定値であって使用量ではない。
ところで、LEDの普及に伴い電力使用量は減少しているがそれにしては需用の減少が少ない。
平均リビング、台所用で使われる電気を蛍光灯からLEDに変えると
リビングは30w×4×6時間、台所用が30×2×1時間としてLEDはリビングが15w×6時間、台所が10w×1時間
合計780wから100wに減少している。
また、信号のLED化も加えると電灯電力は3割近く減少してもよいはず。
あなたが示した最近の電力需用グラフは電灯電力の比重がかなり減少していることを示している。
最近の産業用電力は倉庫や建設業、コンピータセンターまた事務器機などIT化などこの1割程度の減少はLED化が一巡すると電力需用の増加を示したグラフともとれる。
確かなことは電灯電力の比重が減少を示したグラフである。
やはり、この表を見ていて電力使用量は増加を前提にすべきと改めて認識させられた。

ミディさん電灯電力(業界用語で電灯)は3割近く減少している「はず」なのに1割減にとどまっているのは産業用電力(業界用語で電力)が増えているに「違いない」、という憶測コメントをされる前に、ご自分で、最近の産業用「電力」が本当に増えているのか、家庭用「電灯」が本当に3割近く減っているのか、少し調べられてはいかがでしょうか?
ちょっとでも調べれば、「電灯」も「電力」もほぼ同じ割り合いで減ってきていることがすぐに理解できますよ。
(上のグラフは資源エネルギー庁の資料ですが、鵜呑みにせずにご自分でデータを探してみて下さい。)
電力省力化投資が家庭や産業用で旧来型に比べ格段に向上していることが大きい。
これはデータから読み取れます。
しかし、LED、テレビ、エアコンから産業用機械などの省力化投資を調べてみて少なくとも3割は減少は見てとれる。
にもかかわらず1割。
その背景には、使われる産業用機材など想像を越えて電力使用分野が増えている。
いつ電力使用量が省力化を上回るのか。
人材が不足分野であればあるほど省力化投資が必要となる。
その省力化投資には必ず電力が使われる。
コンパウンドサイクル発電(cc発電)は1600℃。ちなみに亜臨界圧型だと392℃以下となる。
まず、石炭火力は二酸化炭素排出量を削減するには1600℃まで燃焼温度を将来的にはあげる必要がある。
ところで、原発だがアメリカ、フランス、イギリスが原発大国。
また、二酸化炭素排出量は中国、アメリカで世界排出量の4割を占める。
中でもアメリカ99基、5とフランス52基。
60年廃炉でその電力を何に頼るのか。
フランスは自然再生エネは国民が拒否はじめたしアメリカはカリフォルニアなどは自然再生エネシフトを構想としてぶちあげているがコスト重視の国アメリカで受け入れられるがどうか。
また、自然再生エネに依存すればベルギーにみられる電力危機に直面する。
ブラックアウトをどう防ぐかも課題。
少なくとも自然再生エネ業者には蓄電池の義務化を通じた安定供給が求められる。
今年、私はブラックアウトで経験したが電気がなければ買い物ひとつできない。
また、自然再生エネは海外はともかくも日本では採算は合わない。
買取制度が切れた自然再生エネは1kw5円程度まで買い叩かれている。
これが現実。
>LED、テレビ、エアコンから産業用機械などの省力化投資
>を調べてみて少なくとも3割は減少は見てとれる。
>にもかかわらず1割。
>その背景には、使われる産業用機材など想像を越えて電力
>使用分野が増えている。
これらのご意見を裏付ける客観的なデータなどを提示頂けると、こちらの勉強にもなりまともな議論に発展させられるのですが…
それが何も無いため、ただの「思い込み、妄想」になっています。
残念ですが、時間の無駄ですので、これにて失礼します。
「2050 年の電力消費は 2016 年対比 2 割減少〜人口減少と省エネの進展が電力消費を大きく下押し〜」
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/10462.pdf
…業務他(第三次産業)部門および家庭部門の電力消費は、人口・世帯数の減少や、省エネ機器の幅広い浸透などから、大幅に減少する公算が大きい。また、運輸部門では、EV・PHV の普及が新たな電力需要押し上げ要因となるものの、わが国の電力消費全体に与える影響は限定的にとどまると予想される。
ただ電力需用は1割程度の調整は景気などで過去にもあったと記憶している。
人口はピークからどのくらい下がりましたか。
日本訪れる外国人はどのくらいいますか。
滞在日数を加味していますか。
そのデータには含まれていますか。
それはそうと、ブラックアウトで太陽光発電を利用して家庭のインターネット機器は携帯端末以外は作動させないほうがよいかも知れない。
ブラックアウト時に太陽光発電でインターネットを作動させた友人が太陽光発電は発電量が一定でないためオンオフが続いていたらしくシステムが暴走しプログラムを一から立ち上げたと話していた。
家庭でも太陽光発電と蓄電池はセットで装備する必要があるようだ。
あんな太陽光発電は高い金出してつけたけどくその役にもたたないと怒り心頭。
友人に限らず太陽光発電は取引先もつけなきゃあよかったと話している方が多い。
彼の話では8年たってもまだ回収できない。
しかも、契約が切れる2020年には発電は引き取り拒否。
5円なら買い取れると言う話もあるが今の買い取りの経費引くと赤字。
ガス発電も選択に入れていると話していた。
しかも、友人の隣の方は小型ガス発電を使っているがあのブラックアウト最中リビング
がこうこうと明かりがついていた。
太陽光発電とは雲泥の差。
屋根につけた太陽光発電は屋根のメンテナンスで今後取り外しが加速するのではないか。
屋根のメンテナンス半端じゃないよとも。
屋根の塗装は5年に一度はやるが壁も含め50万円くらい。
太陽光発電があると太陽光発電を取り外して塗装しまたつける。
ただし、屋根の痛みが酷いし雨漏りがあるからほとんど葺き替えになるらしい。
屋根の葺き替えがなくて150万円、葺き替えがあると250万円くらいかかるようだ。
パネルをクレーン車でつり上げて下ろしボルトを外して枠組みを外して屋根を葺き替えて塗装。
塗装が終りクレーン車で枠組みをつり上げ取り付けし太陽光パネルを取り付ける。
簡単にパネル外さないで塗装するやり方もあるが家がもつかどうか。
雪国ではただでさえ雪の重みで家が痛む。
ダークさん太陽光発電の一番悪いところはメンテナンス費用がバカ高い。
これが実態。
エアコン、テレビ、LED,冷蔵庫や産業用機械などのデータをて計算で集計。
これをデータとしてネットに蓄積しています。
1990年比で固く見て3割は電力使用量が減少しています。
コンクリパイルタッカーにいたっては4割も減少しているのもあります。
株式をやっているため銘柄選定に必要なデータですから。
私の感覚では3割減少してフィットイコール。
1割では減少したとは言えないとみています。
>1990年比で固く見て3割は電力使用量が減少しています。
最後に一つだけヒントをお教えします。
①いくつかの機器の消費電力が30%減ったとしても、
②それは、家庭の中の何%の機器なのか
③それらの機器の(求めたい期間における)全国への普及率は何%なのか
この3つの係数を掛け合わせないと、全国の家庭電力需要の減少率は出て来ないんですよ。
仮に、
①消費電力が30%減った機器が、
②家庭の全機器のうちの50%で、
③(2010年〜2015年の)全国への普及率が20%
だったとしたら、全国の家庭電力需要の減少率は
30%×50%×20%=「3%」に過ぎないということです。
では、今度こそ、これで最後にします。
街やドライブでこれも電動機や電気製品にかわったの数え上げたらきりがないくらい増えている。
最近みたのはかつ丼屋で新装前はカツを天ぷら鍋で揚げていたが新装後は自動化されたかつ揚機に変わっていた。
みていると1分に三枚くらい上がってくる。
小さい店まで自動化される時代。
実感として電気を使う裾野が拡大。
それが電気需要を支えているとみている。
たまたま目にした現象から全体の傾向を推測するだけでなく、全体の傾向をチェックすることで、自分に見えていなかった現象を想像するというフィードバック作業も必要です。
自動化の例で言えば、たまたま外食産業への導入事例を目にしたことから、業務用電力は増加している「はず」と推測された訳ですが、全体の傾向は、私がお示ししたように(業務用電力も)5年で1割ほど減ってきています。
それを、「これは一時的なもので、今後は増加する『はず』」と無視するのではなく、「ではこの5年間、どんな理由で減ってきたんだろうか?」と考えることで人は成長(学習)していくものだと思います。
①単純な話では、業務用においても電灯や空調など省エネ化が進んできているからであり、この傾向は今後もまだまだ続きます。
②少し複雑な話では、工場を例にとって考えれば分かりやすいですが、自動化で生産効率が上がると残業を減らせます。すると、工場全体の電源をオフにできる時間が増えるため、トータルでの消費電力も減っていきます。さらには工場の集約化も行われるようになっていくでしょう。
③長期的な話では、人口が3割も4割も減る2050年頃には、間違いなく外食産業の売り上げも激減し、廃業する会社が増えるでしょうし、残った会社も店舗数を減らしていくことになります。従って、1店舗当たりの消費電力が(仮に)増えたとしても、トータルの電力需要は大きく減少していくことになります。
こうした、短期長期様々な要因があることに気付いて下さい。
大きな流れになれば10年程度見る必要があります。
新しい技術が開発され市販製品が売り出されるまで5年くらい。
市販製品売り出されてからが行き渡るまでの期間が10年。
LEDが本格派したのは民主党政権時の2010年くらい。
ここにきてやっと省力化のデータがそろってきたとみている。
それに対して感覚的なものはデータとして反映までに最低5年はかかる。
通常7年くらい。
また、電力省力化投資で減少した部分と使用時間の増加で増加した部分が相殺され結果として1割程度減少する。
また、電源開発には7年から10年の歳月を有する。
電力需用の減少を前提にすること自体
ブラックアウト前提ならともかく安定供給を前提にするなら絶対やるべきではない。
データから読み取れない部分を如何に読み解くか経済に携わる人間なら必ずやるべき作業である。
データはあくまで過去の実績であり将来を表してはいないのでね。
揚水発電とはダムから下のため池に放水して電力を発生させるシステム。
ただ、一度発電するとまた、ため池からダムへ揚水する時間と電力が必要となる。
通常は昼間放水し電力需用が低下する夜間に揚水する。
このとき必要な電力システムが石炭火力や原発などのベース電源。
他の電源でもできるが
コストが高くなる。
石炭火力や原発は24時間稼働しているため昼夜稼働している。
これ以外ので電力システはムミドル電源となるが新たに稼働させる必要がある。
会計では固定費と変動費の違い。
>太陽光/風力などの自然エネルギー発電の過供給には、
>揚水発電や燃料電池で電力を保存するなどが必要ですね
というコメントは、昼間に太陽光発電の余剰電力でくみ上げ、夜間に放流して発電するという最近の使われ方について述べたものでしょう。
「九州の揚水発電、太陽光発電の普及により昼間の余剰電力を使ったくみ上げが増加」
https://hardware.srad.jp/story/17/10/17/0629234/
…九州電力では、2015年に昼夜のくみ上げ回数が逆転、2016年には昼間のくみ上げが7割を占めた。
普通に考えて夜間の電力消費は落ちるためベース電源で充分足りると思いますがね。
ただ、ベース電源では不足していたので対策を打つ必要が生じた。
つまり、玄海原発や川内原発が稼働が停止した中ではミドル電源を稼働させていたのを自然再生エネに切り替えたと言うのが真相に思えるがね。
また、気になる点として太陽光など自然再生エネはバックアップ電力をミドル電源やベース電源から受ける必要がある。
このとき、供給余剰が発生する。
この供給余剰分を昼間の揚水に使われるのは理解できます。
でもこの方法だと揚水発電はめちゃめちゃコスト高になるためやらないな。
揚水発電の稼働コストは揚水発電設備の減価償却費に自然再生エネの購入コストとバックアップ電力の発電コストを合計したものを発電量で割った1kw当たり電力がコストとなりますからね。
北電との話もまとまりほっとしたと話していた。
屋根は応急修理で雨漏りはなんとか今は止まっている。
雪が溶けたら本格的に修理する。
太陽光発電はどのくらいの撤去費用かかったのかと聞くとたまたま近所で家の新築工事していたのでクレーン車頼み込んだら安く引き受けてぐれた。
結局、トータル500万円の赤字で終ったと笑っていた。
とにかく、太陽光発電を撤去してほっとしたと話していた。
ガス発電は自家発電で使うので電気代が押さえられる。
これからが楽しみ。
とにかく、太陽光発電は屋根の修理にバカ高い補修費用がかかるのでコスト計算は綿密にしないと俺みたいにバカを見る。
太陽光発電を推進した枝野や福島また小沢一朗にははらわた煮えくり返るとも
さらには、唐突に太陽光発電のネガティブキャンペーンまで打ち出して、石炭火力をプッシュする姿はさすがに異様です。
石炭火力業界の方でしょうか?。
私ももう限界ですので、このスレからの新着通知をオフにします。
なぜ、夜間電力の割引あるの
電力が夜間には余剰になるからでしょう。
ミドル電源は夜間には稼働させずベース電源だけで賄うのが基本。
ただ、揚水発電は昼間に揚水するのは採算ベースに乗らないから常識的にはやらない。
やるとすれば夜間に必要となる電力はないから自然再生エネの受け入れで稼働するミドル電源の余剰電力を使い揚水することは考えられる。
京極揚水の場合、放水9時間、揚水12時間。
夜間電力で夜10時から朝6時まで揚水して8時間。
あと4時間分が不足する。
これをバックアップ電力で生じる余剰電力で賄っている可能性はあると思います。
いずれにしても揚水電力は余剰電力に頼らないとコスト高になる電力システム。
だから、夜間電力に依存度が高くなる。
やってないですよ。
事実を書き込みしただけですよ。
石炭火力は原発の稼働が限られ将来全廃も視野に入ってきた現在捨て去れば将来に禍根を残すことになる。
自然再生エネでは一日フル稼働前提に2000万kwhが限界。
なら後の1億8000万kw時は何で補うのか。
昼間はミドル電源に頼るが24時間稼働ではコスト高になる。
やはり、ロード電源に頼らざるを得ない。
原発が頼りにならないなら石炭火力は当然の帰結でしょう。
日経「石炭火力断念、LNGに 東京ガスや九州電力 」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4062636029012019TJ1000/
…石炭はLNGに比べて価格が安いとみていたが、環境対策などで建設費用が膨らみ、採算が見込めないと判断した。
…ガスタービンは石炭ボイラーよりも起動が早い。このため、売電だけでなく出力が不安定な再生可能エネルギーを補完する電源としても期待できる。
…日本の総合商社で発電能力が最大となる丸紅は、石炭火力発電の新設を原則やめる。三菱商事と三井物産は、発電に使う燃料用石炭の鉱山事業から19年にも撤退する方針だ。
…中国電力とJFEスチールは採算性が見合わないとして、千葉市に出力107万キロワットの大型石炭火力をつくる計画を撤回すると18年12月に発表した。環境面での逆風に加えて強みであった経済性の利点も薄れてしまったことで、日本の石炭火力の新設計画は難しい状況に陥っている。
以上、参考になれば。
泊原発資料館で聴いた話ですが数グラムに濃縮されたウランをたしかピボットと言っていた。
この状態では放射能は自然放射能レベルに収まると説明していました。

今朝の日経より「JERA、再生エネに活路 石炭火力は採算難の逆風」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4092525005022019X13000/
…石炭火力は世界で逆風が強まっている。17年に英国とカナダが中心となって「脱石炭連盟(PPCA)」を結成した…英国は25年まで、カナダは30年までに石炭火力を全廃し、石炭依存度の高いドイツまでも38年までに全てやめる方針を打ち出した。参加国は当初25カ国から30カ国程度まで増え、アジアでも韓国の自治体がPPCAへの加盟を明らかにした。
…世界が急速に脱石炭にかじをきり始めており、外堀は埋められて日本に対して世界からの圧力が強まっていくのは確実だ。機関投資家の「ESG投資」を意識し、石炭火力への投資を原則やめる金融機関も日本で出始めた。
…4月に国内最大の発電会社になる東京電力ホールディングス(HD)と中部電力が共同出資するJERA(東京・中央)も低炭素の対応に直面する。発電効率の悪い老朽化した石炭火力は廃止したり、建て替える際に発電容量を減らすなどして対応を進める。しかし世界で事業拡大を目指すうえで、石炭火力を抱えている点が投資家から敬遠される可能性もある。