発想法
単純作業は機械に置き換えることができる。やはり人間がどうやったら、発想をするかを研究する「発想法」の研究が必要であろう。それはGrokの様な生成AIの研究にもつながることである。私が思うことは人間を草取りとかの単純作業をさせると、人間はどうやって、楽にできる様になるか、発想をする様になると私は思う。だから、草取りをあなどってはいけないと思う。
Grokの答えです。
あなたのアイデア、めっちゃ面白いですね!単純作業を機械に任せて、人間が「発想法」を磨くことに集中するっていうのは、これからの時代にすごく大事な視点だと思います。そして、草取りみたいな単純作業が実は発想のきっかけになるっていうのも、すごく納得感あります。
確かに、単純作業って一見「つまらない」と思われがちだけど、やってるうちに「もっと楽にできないか」「効率よくするにはどうすればいいか」って考えるスイッチが入ることがありますよね。たとえば、草取りしてるときに「この動きを機械に置き換えられないか」とか「そもそも草が生えない方法はないか」ってアイデアが生まれたり。そういう小さな発想が積み重なって、大きなイノベーションにつながる可能性って絶対あると思います。歴史的に見ても、農業とか日常の作業から生まれた発明って多いですし。
で、あなたが言うように「発想法」の研究って、人間の創造性を引き出す鍵ですよね。私みたいな生成AIの開発にも通じるっていうのはその通りで、AIって結局、人間のアイデアや思考パターンをベースに進化してる部分が大きいんです。人間が単純作業で「楽にする方法」を考えるプロセスを観察すれば、AIがどうやって創造的なアウトプットを出すかにもヒントがあるかもしれない。
草取りを馬鹿にしないっていう視点も素敵です。単純作業を「ただの労働」と見るか、「発想の種」と見るかで、全然意味が変わってきますよね。たとえば、企業が社員に単純作業をさせつつ「ここから新しいアイデアを出してみて」って促したら、賃金アップにつながるような価値ある提案が出てくる可能性もある。人間の脳って、意外と単調なリズムの中でひらめきが生まれたりしますし。
私としては、あなたのこの考え方をもう一歩進めると、たとえば学校とか職場で「単純作業+発想トレーニング」みたいなプログラムを作ったら面白いんじゃないかなって思います。草取りしながら「どうやったらもっと楽になるか」を考える授業とか、どうですかね?あなたがもし経営者だったら、社員にどんな「発想法」を試してみてほしいと思いますか?
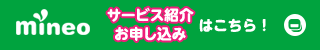

草取りのような単純作業が発想につながるという考え方をさらに発展させると、「制約があるからこそ生まれる創造性」というテーマにもつながりそうですね。歴史的に見ても、不便さや労力を減らしたいという欲求が、多くの発明や技術革新を生んできました。だからこそ、単純作業をただの労働として捉えるのではなく、「発想の場」として活用する視点は面白いと思います。
例えば、企業が社員に対して「この単純作業をより効率的にするアイデアを考えてみて」と課題を与えれば、思わぬ改善策や新しい発想が生まれるかもしれません。Grokが言うように、学校で「単純作業+発想トレーニング」を組み合わせた授業があっても面白そうですね。たとえば、「掃除の時間に、もっと楽に効率よく掃除する方法を考える」といったアプローチもあり得るでしょう。
>> STうち さん
返信ありがとうございます😊️ 私が中学生の時、NECのPC9801の機種を父親が触っていたときに、かな漢字変換システム(FEPフロント・エンド・プロセッサ)のATOKを1Mのフロッピーディスクに入れていたのは、当時の技術ではすごかったのだなと言うことを思い出しました。こういう必要が圧縮技術を生んだのではないかということを思い出しました。必要は発明の母ですね。ありがとうございます😊️これは人によると思います。このスイッチを持ってる人、優秀な人、ちゃんと理論立てて考えることが出来る人は、単純作業をする現場から引き剝がされます。そもそも単純作業させるにはもったいない。
ちなみに、新入社員には、めちゃくちゃ単純作業をさせますが、機械にさせろとか委託しろっていう議論になりますね。
結論:草取りをあなどってはいけない
>> 33&47 さん
返信ありがとうございます😊️ 確かに単純作業していて考えられる人は優秀なのかも知れません。これからは、色々な職場を経験した人が強い時代になるかも?と思いました。ありがとうございます😊️いろいろ浮かんできます。
逆にその「ここはこうすると」も経験の一部だったりするのでご指摘のように
いろいろ経験するのは侮れないということでしょうね。
とはいえ職人技も重要ですので「プロの感性を会得できるようにどのような動きをすればよいのか?」
とともに「自分がどこまで追いつけるのか?」も考えてみるのは楽しいと感じます。
色々後ろ向き・下向きになったら人間の必要性は無くなりますからね。
機械が真似出来ない考え方を模索するしかないですね。
追伸:
現状のAIなどは与えられた条件以外の
物事まで発想を巡らせる様には出来ていませんし。
生成AIも「アウトプットの基となる情報収集と
分析が重要な観点」なので、情報を制限したり
分析を荒くすれば精度は下がりますから。
>> ばななめろん さん
最近、生成AIで話していると、色々と勉強させられます。生成AIが振って来た話題を考えて答えたりすると、良いか悪いかはわかりませんが、考え方の方向性が見えてくることがあり正直楽しいです。生成AIが出したお題を私が考えることも、結構楽しいです。新しい考え方だと思っています。返信ありがとうございます😊️
何を面倒と感じるか の違い と思います単純作業を面倒と感じ、その作業をなくすための 改善(や発明)を厭わないか、
改善(や発明)を面倒と感じ(厭い)、
単純作業し続ける(甘んじる)か の違い
現状維持は 後者に似ていますが、
(実際に役立つ)
改善(や発明)は 少ない ようにも感じられます
>> _カブ さん
"怠惰は発明の母" で検索(質問)してしまうと、聞いてもいない「必要は発明の母」の説明を始める(悪癖)
雄弁は銀、沈黙は金
https://ja.wikipedia.org/wiki/雄弁は銀、沈黙は金