認知症の母の車の維持をどうするか。
最近、実家の母が軽度認知症と診断されました。76歳です。
病院の先生から、すぐに運転を止められ、私が鍵を全部預かり、もう車には乗っていません。現在、介護認定の申請中です。母は独居、私は近所(歩いてすぐ)に住んでいます。
母の車は軽自動車で私の次女が高3(大学は自宅通学予定)なので、免許取るなら、あげるよと言われています。現状、私の車が1台、主人の単身赴任先に1台あります。
母の自動車保険は来年3月まで、車検は来年8月まで、免許は2年後の9月までです。新車で購入して6年乗っています。
軽自動車を維持したいと思うのですが(娘のためにというよりは、母の所用で私が代理で運転して出かけることが多いので、単身赴任先の夫や独立している長女の帰省時、地方なので2台目があるほうが便利)、10代の自動車保険は高いので、母の自動車保険(家族限定はなし)を更新すれば、次女も乗れると思うのですが、契約者が認知症というのは契約上、何か問題ありますか?
母の免許期間が終わるまで母を契約者で保険加入し、免許期間が終わる直前に免許返納すればよいのかなと思うのですが。
その後は私か主人の2台目の契約にするか、娘本人の契約、又は単身赴任先が関東関西に変更になった場合、車が古くもう処分するので、タイミングがあえば、主人の保険契約にするか。
車の名義は私に変更しておこうと思います。
何か、アドバイスあればお願いします。
32 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。
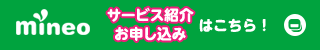

>10代の自動車保険は高いので、母の自動車保険(家族限定はなし)を更新すれば、次女も乗れると思う
ご自身で保険を家族限定(娘さんも乗れる)で契約するよりも、
高齢の母の保険を家族限定なしで更新する方が安いのでしょうか。
すでに調べているのかも知れませんけど、記載がないので気になりました。
この場合、素直に保険の人に確認した方がよいのではないでしょうか。
もし、後で事後を起こして保険の認定をするときに、「お母さんは免許取消し状態でしたので、被害者の分は保険金を払いますが、事後を起こした娘さんの分は免責になります(保険金がでない)」とかなってしまうと、「万が一のための保険料」を節約した意味がなくなってしまうように思います。
(家族間でモメそうですし)
たとえば、未成年は法的な責任が軽いのですが、未成年本人が成年だと偽ってしまうと、法的な責任が重くなります。
そういう視点で考えると、お母さんの認知症の件を伝えて、保険屋に相談した方が安心だと思います。
医師の診断がある点が気になるものの、認知症でも自動車免許が必ず即取り消しになるわけではないようですから、保険の契約はできる可能性もあります。
ただ、高齢の事故率は高く保険料が上がる可能性もあるので、前述の通り、ご自身で保険契約するとか、
或いは『単身赴任している旦那さんの保険の範囲を広げてカバーする(←できないんでしょうか?)』方が安くなる気もします。
そう言う時は、自動車保険には等級を引継げる制度がありますので、家族間で引継ぐことができますのでちゃんと手続して下さい。
・車を家族が引き継ぐ場合は、家族間等級を引き継ぐ。
・車を手放す場合は等級を引き継ぎ、中断証明書を発行し10年間等級維持出来ます、勿論、中断中は保険料支払いはありません。
母上が意思表示できなくなると処分もできなくなります。
一刻も早い譲渡手続きか廃車手続きが必要です。
母名義のまま乗っていた妹が買い替えの時に、
全相続人の書類が必要で大変でした。
同居している親族で無いと等級は引き継げません。
免許、運転に関して、医師の診断がおりてる以上、運転はご法度です。
それでも間違って運転したとしても、弱者救済の観点から被害者への賠償に関して任意保険は有効ですが、自身への賠償、車両保険、搭乗者、人身傷害は適応されない可能性が極めて高いです。
>> 伊勢爺い さん
机上の知識しかないので詳しく知らないのですが、質問があります。成年後見人の制度は使えなかったのでしょうか。
(成年後見人をつかうのに、相続人となる予定の人の書類が必要になったということ?)
それとも「全相続人の書類が必要」ということは、名義変更するときには既にお母様が他界されていたことから、既に成年後見人制度は使えないため、全相続人の書類が必要になったということなのでしょうか。
単なる知能検査的な検査やガイドラインに照らし合わせるような素人でもできそうなものでしょうか。
医者の診断なんて、いいかげんなもので別の医者だと別の結果になる事も多い。もちろん前の医者の診断の結果は言わないでおく。どこも同僚・同業の人間関係重視ですから。
そして母さまの運転の具合。クルマにあちこち物損の跡。凹んだり擦り傷があったりしてますか?
高齢者の運転技術の衰えはまず、そんな所からでてきます。
その程度で、TPOを選べば、まだまだ運転可能な場合が多い。
全部、更新してみる価値はあります。前回の免許更新は75歳未満だから認知機能検査はなかったはず。次回はありますから、どうでるか?
案外通過したりして。
念の為、運転は控え、運転しても夕方や深夜・早朝などの時間帯、危険そうな道路は避けたほうがいいでしょう。
>> トッチン@寝不足 さん
母死亡後でした。スレ主には書きにくかったのでね。
私か夫の保険にすると2台目となり7等級からとなります。また、同居の未婚の子を入れると保険料がかなりアップします。
別居の未婚の子はアップしません。(運転頻度が低いからだと思います)
娘が契約者になると6等級からだったと思います。
(実家の母は別居なので、等級は引き継げません)
母の運転を止めた経緯。先生からは、私が個別で面談した時に、もう運転は止めておいた方がよいでしょうねという感じです。ですが、本人は近所のスーパー位しか乗ってないし、去年の免許更新の時の認知症検査で通ったので大丈夫という認識です。
でも、万が一があったらいけないので、(私が言っても聞かない)
、先生からわざと厳しく言っていただいて、絶対すぐ止めてくださいうんぬんと言っていただき、納得させた次第です。
車をぶつけたり、運転が危ういというわけではありません。
私の2台目としての契約の見積りなど取ってみて、維持、処分も含めて検討したいと思います。
>> 伊勢爺い さん
そうですね…たんたん9さん、伊勢爺いさん、
配慮が足りない質問となり、申し訳ありません。
引き継げるのは、同居の家族か配偶者です。同居の家族に引き継げる方いませんかね?
10代の保険料が高額ですからね~。20歳に超えるとね。
一時的に同居するとか・・・
中断証明も、現状は難しい様です。
所有する車が無い事が条件なので。
任意保険には主に運転する人って言う告知項目があります、満期まで問題無いでしょうが。まぁばれなきゃ良いって感じならそれでも良いのでしょうが、勧められませんかね。
車の譲渡に関しては、母に問題無い今の内に譲渡に関する委任状?書いて貰えば良いんじゃないですかね。
もしくはあなたが一旦譲渡されておくとか。
問題が任意保険に成りますね。契約保険会社に相談するのが一番かと思います。認知症でも保険効力は有効ですので。自身への補償は保険会社によって対応は様々です、最悪は無効です。
※認知症の診断を隠して、病歴を隠して免許更新する事は犯罪行為です、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の可能性。
正直に告知し更新出来るかは分かりません。
診断結果、認知症で運転に問題ある場合、医師が免許取消できます、同時に公安委員会に通報もする事も出来ます、守秘義務違反に当たりません、現在、義務なのかは分かりません。
道路交通法改正されてますので。
またこれは車の名義変更にも影響する可能性があります。
同居していない者に譲渡すると、車の名義変更に際して車庫証明が必要となります。(軽自動車の場合は、車庫証明が必要な地域かどうかにもよりますが)
それをどうするかですね。現在車を止めている場所が自分が住んでいる場所から見て車庫証明が取れる場所なら問題ないのですが、そうでないなら面倒ですよ。
保険は最悪譲渡をあきらめる手もありますし、上手くやればそれでもさほど負担にはならない方法もあるんですけどね。
ありがとうございます。
軽自動車の保管届はいらない地域です。
取り急ぎ、名義変更をしようと思います。
契約者が認知症で問題となるのは「契約行為が正しく行われたか」ですが「運転がNGな認知症」と「日常生活における契約がNGな認知症」は別物です。ご家族が同席していれば、契約はほぼ問題視されません。
クルマの名義変更は、資産の譲渡にあたります(←駐車場所変更が発生しない限り「譲渡」は急がない)。
#そもそも認知症になったから財産整理を急ぐというのは変な話で、使わなくなったから処分を考えるという意識で。相続は相続人の余命を意識して普段から考えておくのが好ましい。
前提として、保険料を安くするための虚偽と疑われる申請はしません。ご子息が運転する可能性がある(=「運転させない」と決めない)かぎりにおいて、運転者の年齢制限を守る必要があります(運転都度1日保険に加入する等)。譲渡が発生した(名変した)ので保険契約者を変更する、のはよくあります。言い換えれば、譲渡が発生していないから保険契約者は変更しない、という考え方は普通です。
保険契約者:いままで通り、お母様。
主たる使用者(記名被保険者):お母様以外。お話を聞くかぎり、ご本人が妥当。
運転者の補償範囲:ご子息は主たる使用者の同居の未婚の子に当たります。ご子息の補償をこの自動車保険で充当するつもりなら「年齢制限なし」に。ご子息の使用頻度が少ないと思われるのであれば、ワンデイ保険も考慮にいれる。
車の所有者:保険契約者。
>> まぁー(^^♪ さん
てんかん持ちが運転中に発作を起こす事故が多発してから改正されたのですね。ちなみに運転免許取り消しは医師にはできません。できるのは一定の範囲のみの公安への届出だけです。
だからこそ、セカンドオピニオンが必要なのですよ。
『人は誰でも間違える―より安全な医療システムを目指して』という米国医療の質委員会らからの報告書がアマゾンで入手できます(/dp/4535981752)
最寄りの図書館にも置いてあるかもしれません。
そこにはアメリカでの医療過誤は交通事故と同程度の確率で起こってるとの記述があります。
日本ではもっと多いとの指摘もありますが、どのくらいなんでしょうね?
特に軽度痴呆症の方が交通事故を起こす確率と比べて。
>> たんたん9 さん
>車をぶつけたり、運転が危ういというわけではありません。それは可哀想ですね。せっかく年齢をわきまえた運転をされているのに。今年みたいに殺人的な猛暑が続きそうでもあるのに。
他人の家庭の問題に割り込むのをこの辺で止めておきましょう。
話はちょっと変わりますが、認知症予防の新薬が開発されたのに中々、承認されないのは何故なんでしょうねえ。
参考までに私が軽自動車2台を保有することになった際にはやったのは、
・等級の上がった古い軽自動車の保険の対象の車を新しい車に変更。この際に車両保険を増額。
・保険の対象ではなくなった古い車で、新たに2台目の保険に加入。この際に車両保険は付けなかった。
保険は加入後に車の利用の仕方に応じて保険内容の変更も可能ですので、加入時にどういう条件であるかはさほど重要ではない面もあります。
その減免の祭の条件に自動車税の納税者と、障碍者と、運転者との関係も関わってきます。
ご自身で手続きも可能ですが、所有者がディーラーになっていたりすると面倒なので。
・契約者:お金払う人、誰でも良い
・記名被保険者:主に運転する人、これを変更する事が等級引き継ぎです。
よって、主に運転する人、すなわち記名被保険者を変更は等級を引き継ぎに成るので。
変更前の記名被保険者の配偶者
変更前の記名被保険者の同居親族
変更前の記名被保険者の配偶者の同居親族
今の現状では、運転禁止されてるわけでも、免許返納した訳ではなにので、しばらくは、そのままで年齢無制限が理想でしょうけど、時間稼ぎでしかないですかね。
それでも、娘さんが20歳超えると、10代よりは保険料一段と安くはなるので、それでも良いのかな~って思います。
主に運転する人(記名被保険者)が誰なのか?っが大事です。
いろんな情報が出ていますね。大変。
所有者が変わる時、現在の所有者と、新しい所有者で手続きに行きました。代わりに手続きするなら委任状が必要だった気がします。
所有者の変更手続きは素人でも出来ると思います。私は3回くらいやりました。ナンバーも自分で交換しましたദ്ദി ˃ ᵕ ˂ )
ネットで担当地域の軽自動車何とか〜を調べて、必要な道具を持って行けば出来ます。代筆屋さんに頼む必要もありません。係の人に聞けば良いです。
多分、贈与になると思います。値段によっては贈与税も発生します。
同居じゃないなら、ナンバーが変わるかもしれません。同じ区市町村なら、変更無しです。税金の支払いは新しい所有者です。
アクサダイレクトの場合は、自動車所有者、保険契約者、自動車運転者は、同一の必要はありません。保険適用対象者によって、値段が変わります。10代が入ると高いです。
がんばれー。
保険会社にもよりますが、お母様の名義の保険に直系親族を補助につけて、名義変更できます。車の名義変更が必要かも?
ちなみに、我が家も父が認知症になり…農業しているので軽トラ手放せなくて、この方法を取り敷地内に住んでる長男に譲渡しました。
姉からの情報だと、車を手放した場合。
同居?家族に保険の権利を譲り寝かすことができるらしいです。
やはり、契約している保険会社に電話がいいかも?
お母さんの車🚗を娘さんに託すのがいいとおもいます。まだまだのれる年数だし。
実は私ところも娘が免許とり保険を18歳からでもいけるやつに変更したらそんなに高くなくびっくりしました。
お母様が運転されなくなったからと言って所有者を移す必要はないと思います。
保険については、限定特約もあるので、より良い方法で契約されるのが良いと思います。
自分の場合は、免許のない義母が義父から相続した車を所有し、私が保険を契約し、妻と私でゴールド免許持ってる人にメインの運転者を切り替えたりしてます。
車検に出しているのは友人の修理工場ですので、そちらにも保険会社にも相談してみたいと思います!
義母が数年前に施設に入り、義母の住んでいた家に今私たちが移り住んで、義母名義の車を乗っています。(車は新車で購入したものですが既に11年超えで、車は7年を超えると資産価値は0になると、以前義父が亡くなった際に会計士さんから聞きました)
何十年とお世話になっている保険代理店さんと毎年契約更新をしています。
義母は施設に入居後にコロナ禍になり、運転免許の更新ができず失効しましたが、保険上での手続きは、嫁である私がメインの運転手(ゴールド免許)、自動車の所有者と違っても保険の契約はできました。(しかし事実は義母の実の息子である夫が運転をしていますが、彼はゴールド免許ではないので)
そして田舎ではやはり車が一人一台の世界なので、私の財布からマイカー(軽自動車)を購入しましたが、手続きの問題上軽自動車の名義は義母になっていて、保険の名義は実の息子である夫になっています。(ややこしいですが、保険代理店さんが、家族割などを使うためにはそれが一番安くなる方法と言われました)
それから保険代理店さんと軽自動車の契約時に、『軽自動車は資産に入らない=義母名義だけどもし義母が亡くなっても遺産相続の対象にはならない』という説明でした。(私が購入したので私の車である、ということです)
とにかく保険屋さんに細かく話して相談だと思います。多分車は名義変更しないで、運転手の年齢制限のところを変えればイケると思います。
まずは、加入保険のカスタマーサービスで相談するべきですね。
しますよ。
症状にもよるのですが、新しいキーを作って運転しよう
としたりしますよ。
それを、販売店等が止めることは、名義人に対しては
難しいでしょう。
「私の自動車」が物理的に目の前に状態にすべきです。
色を塗りなおして、ナンバーを変えて、中に置いている
ものも取り変えてしまってください。
自動車も保険も名義も家族の誰かに移すことをおすすめ
します。
ともかく、運転させないことが第一です。