Love green!多肉ちゃん♡
キレイなお花のスレッドはときおり見かけますが、多肉植物や観葉植物の投稿はあまりないのかな?
ちょっとスレッドを建ててみました。
別にそんなに詳しくはないし、数種類しか我が家にはありませんが、小さな入れ物に植えたり、大きめの器に寄せ集めたりして観察しています。
いろんな形や色があったり、どんどん増えるのが楽しくて。
確かに、花と比べると地味ですが、多肉植物も含め観葉植物は長く楽しめるのでオススメです。
水やり、管理等もお花に比べて楽チンですよ!
🌵多肉サボ好きT君(さん)※が、多肉ちゃんとサボテン君の違いをわかりやすくまとめてくださったコメントURLです。
https://king.mineo.jp/my/NoMoistureNoLife/reports/24245/comments/617963
※現在、多肉サボ好きT君(さん)はYouTubeでも情報発信されています。
https://youtube.com/channel/UC3Z3cx8E8yWASPlQOSgIN0w
2972 件のコメント
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。

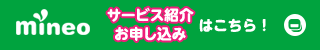


血糖値を測る機器のセンサーを腕に貼っていますが、衣類で隠れる位置にしています。珍しく他の人が付けているのを見かけましたが、肘に近くて邪魔にならないのか心配になりました。(^^;画像はチレコドン属の白象です。花が咲いていなければ、ただの枯れ木にしか見えませんね。葉の出る時期と開花期が違うので、何だか不思議です。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
株元が太ってくるコーデックス扱いの一つですが、大きくなっている気がしません。ずっと同じ姿ですね。枝先が少し伸びた程度でしょうか。あまり大きくならないのかな。
新たな100円組です。
だいぶ朝晩が涼しくなってきたので、ポインセチアというかプリンセチアを我が家も短日処理始めようかというところです。
天パさんからいただいたアガベ、一週間湿らせた土の上に置いていたのですが兆しが見られず昨日からお水につけおく形に切り替えました。

まだ昼間の気温は高いですが、そろそろ冬型の植え替えを始めたいところ。週末、土曜の夜にライブ配信を予定します。準備はこれからですが。(^^;画像はコノフィツム属、稚児の舞です。原因はよく分かりませんが、外皮が枯れたようになったのは部分的で、夏の間も青々としていました。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
秋口、気温が下がってくると動き始めます。そのタイミングで植え替えしますが、株分けにも適した時期なので、ボリュームが出過ぎていたら適度に分けます。
>> 多肉サボ好きT君 さん
我が家のリトープス、数個が溶けてしまいました。せっかく夏越しできたとおもっていたのですが水やりはまだ早かったのかも知れませんね。
この春、だいぶ分裂して数が増えていたのがせめてもの救いです。

明日、通院でお休みを取るのと、週明けに遅めの夏季休暇としているので、ちょっとした連休になります。うまく息抜きをして体を休めたいですね。(^^)画像はコノフィツム属のマウガニーです。透明感のある姿に、プニプニした触り心地が良い品種。ブルゲリー、ラツムなどの珍種仲間です。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
夏越し中は外皮を枯れたように変化させて、秋口に旧皮を破って生長してきます。この夏は何故かあまり変化が見られず、そのままの姿でしたね。

遅めの夏季休暇を取ってゆっくり出来ましたが、運動負荷検査や運動療法など通院していたので、いつもより少し長い連休と言った感じでした。(^^;画像はフォーカリア属の怒濤です。爬虫類っぽい姿が面白いですね。メセン類の中では比較的扱いやすく、割りと適当にしていても育ってくれます。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
少しずつ品種によって違いはあるのですが、差が感じにくいので好んで集める人は少数派かも知れませんね。年数が経つと株元が太って、貫禄のある姿となってきます。

秋の全国交通安全運動が今日から始まりますね。いつからか週間と言わなくなりました。以前は言っていたように思いますが、期間が伸びたからですかね。(^^;画像はエケベリア属のブルーバードです。肉厚な葉をしていてロゼットもコンパクトで綺麗ですね。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
エケベリアの仲間は一部を除き葉挿しで増やせますが、植え替えの際に下の方の葉を外す事が多いです。生産者によると、一番下の葉より少し上の葉を使うほうが失敗が少ないとか。

ベランダで使っているジョウロの水がいつの間にか減っているので、よく見たらハス口へ繋がる注ぎ口の付け根が傷んで、そこから漏れていたようです。(^^;画像はクラッスラ属の円刀です。近い品種の神刀と違い、葉が丸みを帯びた姿をしていますね。神刀に比べ少し生長が遅いように感じます。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
葉の表面はザラザラしていて硬いので、周りに触れるものを置かないほうが無難ですね。葉挿しが出来るものの、葉は取り外しにくいです。

見切り品だったパッションフルーツ、このところの気温低下でやっと花が咲きました。寒くなる前に収穫できればいいのですが。
この秋は二度目のビオラの種蒔きというか前はパンジーでダメだったのですが、今年はだいぶ発芽しています。(๑˃̵ᴗ˂̵)و ヨシ!
もう少ししたらネモフィラにも挑戦してみます。
今回の園芸談話はコノフィツムでしたね。
天パさんからいただいた
アガベがなかなか発根しない💦
また今週から土の上に置く形に切り替えてみます。

先週末は京都シャボテンクラブの例会でした。多肉植物の競作がテーマで、今年の配布苗はエケベリアのマディバ。割りと大きくなる品種のようですね。画像はクラッスラ属のプベスケンスです。産毛の生えた小葉を群生させますね。気温の高い時期は半休眠のため、赤く染まります。(^^)
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
少し蒸れやすい性質のため、風通しの良い場所へ置くように。葉挿しが可能で増やしやすいです。気温が下がってくると緑色が戻ってきますね。

ホームセンターの園芸コーナーはたまに覗くと掘り出し物があるので楽しいですね。フィロボルス属のラビエイがあったので、思わず手を出してしまいました。(^^;画像はフリチア属の光玉です。メセン類の中では珍しい夏型で、調子が良ければ不定期によく咲きますね。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
葉の先端が窓になっていて、すりガラスのような印象です。妖精の象の足、とも言われるとWikiに書かれていますがあまり聞きませんね。光玉のほうが言いやすいですし。

もう9月が終わろうかと言う時期ですが、昼間は夏日で暑い日が続いています。熱中症対策はまだまだ引き続き必要ですね。寒暖の差が激しくなってきたので体調管理には気を付けないと。画像はキリンドロフィルム属のコンプトニーです。丸い棒状の葉を左右に展開しますね。古い葉の表皮がひび割れたようになるのは、そういった性質なのかも。(^^;
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
メセン類ですが気温の高い時期に育ちます。生長は割りとゆっくりで、ジワジワと新しい葉が伸びてきますね。もう少し育ってきたら株分け出来そうです。

原因はよく分からないのですが右肩を傷めたみたいです。肩もそうですが、胸や背中の筋トレに支障が出るので、なるべく早めに回復して欲しいところ。(・・;)画像はフォッケア属の火星人です。塊根から蔓を伸ばして、細長い小さめの葉をつけます。コーデックス(塊根)としては生長が早い方で、初心者向けと言われていますね。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
蔓は勢いよく伸びるので、支柱を立ててうまく誘引します。花は小さく緑色をしているのでほとんど目立ちません。冬は葉を落とし休眠するので屋内へ退避。

週末に少しずつ植え替えをしていますが、大物の植え替えはなかなかしんどいですね。競作で大きく育ってきた株などを植え替えましたが、あまり頻繁には植え替えたくないです。(^^;画像はステファニア属のスベローサです。上下の画像は別株ですが、微妙に雰囲気が違いますね。雌雄異株で雌株と雄株の違いはあるのですが、形は株ごとに変わるそうです。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
蔓が伸びてきてあちこちに絡むため、支柱を立てて誘引します。花は春の後半から初夏に咲いていますが、あまり目立たないですね。球根部分は埋めてしまっても構いません。

運転免許証の更新案内が届いたのですが、全て予約制に変更されていますね。以前は試験場だと予約無しで行けたのですが。今回は近隣の警察で手続きしてみようかと思います。画像はアボニア属のパピラケアです。植物に見えない姿が面白いですね。鱗のようなものに覆われています。タネから育つと株元が太るとか。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
自家受粉するようでタネが自然に出来ています。発芽は気温が高い時期でも大丈夫なのですが、その後が続きません。いつの間にか消滅しているので、管理がなかなか難しいです。(^^;

クレジットカードの有効期限が来て、新しいカードが届いたのですが、カード情報を登録している箇所も更新しないといけないものの、登録箇所が把握しきれていません。画像はバンダ属のフウラン(富貴蘭)、東出都です。春の終わりから初夏あたりが本来の開花期ですが、今年は夏に咲いていました。(^^;
着生蘭なので日照は木陰、木漏れ日が当たる環境のイメージ。強い日射だと葉焼けします。植え替えのお勧めは春。水ゴケと素焼き鉢が定番ですが、植え込み材はあまり選びません。
蘭用のスリットが大きく、長い鉢も使えますね。水ゴケを炭の塊に巻きつけたり、株元に水ゴケを抱かせて板付けするなど、割りと仕立て方もバリエーションが豊富です。

仕事先の近くでカメムシが沢山落ちていて、今年は大量発生していたようです。夜間の照明に集まっているようで、場所によっては足の踏み場も怪しいくらいに。(・・;)画像はアナカンプセロス属のミニアツラです。桃色の可愛い花が咲きますね。自家受粉してタネをあちこちに落とし、芽吹いてしまうので苗が沢山出来て雑草化しがち。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
茎が柔らかく倒れやすいので高さは出ないのですが、姿は乱れやすいですね。葉挿しも出来て仕立て直しは容易なので、低い締まった姿を目指すなら定期的に仕立て直しを。

痛めていた右肩はほとんど問題無くなりました。あまり長引かないのはありがたいですね。腰を痛めたら動かしたほうが良い、とよく聞きますが他の部位でも同様なのでしょう。画像はハエマンサス属のフミリスです。花弁の無い花が不思議ですね。葉は産毛に覆われていて、厚みはありませんが触り心地は良いです。(^^)
扱いは夏型。春から秋まで日当たりから半日陰で管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
球根が育ってくると葉の幅が出てきます。花が咲いてから葉が出てくる事が多いのですが、待ちきれないのか開花を待たずに葉が出てくる事も。

週末の日曜、京都で日本シャボテン大会がありましたので足を運びました。各地の販売業者さんも来られて即売会も盛況。展示株も立派なものばかりでした。(^^)画像はビカクシダ属のステマリアです。割りとコンパクトにまとまった姿を維持しているので、置き場所には困らない品種のようですね。胞子葉も短めです。
明るい半日陰を好むので、日差しの強い時期は遮光下へ置くか、日照時間を加減します。気温の高い時は水やりをしっかりと。貯水葉の裏側へ。
株元の水ゴケは仕立ててからベースの板などをはみ出して生長が進まない限り、そのままで構いません。子株が出た場合は外して別に出来ますが、ある程度育ってから。

各地で園芸関係のイベントがあり、販売業者さんも分散する傾向があるので難しいところですが、色んな方に足を運んで貰うにはより魅力的なイベントにする必要がありますね。画像はビカクシダ属のレモイネイです。交配種だそうですが、割りと出回りやすくホームセンターの園芸コーナーに並んでいる事も。性質が強く育てやすいですね。(^^)
鉢植えになって販売されている場合、胞子葉が長く伸びてバランスが崩れて転倒しやすくなるので早めに安定させるように。貯水葉も大きく縦に広がりやすいです。
胞子で増えるので、胞子葉の先端近くの裏側に茶色の部分が出来ると、胞子を取って新たな株を作る事も出来ます。交配も出来ますが、マニアックな世界になりますね。

別店舗ですがスーツを仕立てたショップでオーダーシャツを頼んでみました。細かく採寸していたので、体に合うものが出来上がりそうです。(^^)画像はクリプタンサス属のアルギロフィラスです。赤系の派手な縞模様の品種などが目に付きますが、このようなタイプもありますね。トリコームは密で細かいです。
日当たりは半日陰程度で十分に育ちます。パイナップル科なので、葉の表面から吸水できるため、株元だけでなく全体が濡れるように水やりを。植え替えは春がお勧め。
開花すると脇芽を出してきますが、生長点近くから芽吹いてくるので外すにはある程度の時間が必要です。クリプタンサスの女王とも言われ、マニアには人気のある品種。

温室に付けていた掛時計が、ひと夏を越えたところで動かなくなりました。屋内用だったので過酷すぎたかも。この週末、土曜の夜にライブ配信を予定します。画像はアストロフィツム属のカプトメドゥーサです。細長い枝(葉?)を伸ばして、その途中に花をつけますね。丸いサボテンのイメージからはかけ離れた姿。(^^;
アストロフィツムの仲間は高めの温度を好むと言われているので、冬越しには注意したいところ。夜や明け方の気温が下がる時期になったら、屋内へ取り込むか養生を。
生長してくると太くなるそうですが、かなり時間が掛かります。なので接ぎ木をして生長を促進させたりする人も多いとか。とりあえずこのまま見守るつもりです。

週末、まとまった雨が降って気温が下がるかと思いましたが、あまり変わらず。駆け足で冬に向かう訳では無さそうですね。画像はアストロフィツム属のヘキルリランポー玉です。かなり傷んで形もいびつになっていますが、不定期によく咲いてくれますね。京都シャボテンクラブの競作苗の一つ。
兜などに比べると育てやすく、高めの温度を意識しなくても大丈夫。日の当たる方向へと歪むことがあるので、時々鉢を回して傾かないようにします。
元は紅葉するタイプでしたが、株が若いうちは染まりやすく、生長してくると色が乗りにくくなるとか。私の環境では当初からあまり染まりませんでした。(^^;

昨日は振替休日で午前は車のタイヤ交換、午後は運転免許証の更新手続きでした。タイヤの表面上のひび割れは、すぐにパンクに繋がる事は無いので慌てなくても大丈夫だそうです。(^^;画像はテロカクタス属の紅鷹です。花は大きめで色鮮やかですね。一日花なので、長く楽しめないのが残念です。
明け方の最低気温が下がってきたら、寒さに弱いサボテンは屋内へ取り込むか養生を。水やりの回数も少しずつ減らして、間隔をしっかり空けるように。
冬越し中はほとんど生長せず、動きもありません。可能なら日に当てて徒長には注意したいところ。水やり後の土の乾きも遅くなるので、鉢の重さで乾き具合を判断します。

ご近所で金木犀が咲いていて、良い香りが漂ってきます。芳香が強めなので、分かりやすいですね。画像はコノフィツム属のレコンディツムです。とても小さな株ですが、花はしっかりと開花を主張してきますね。(^^)
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
株が小さいだけあって、植え替えの際には気を遣います。割りと浅めの位置に根を張るので、培養土は鉢の上部中心でもよいくらいですね。

だんだん朝晩が寒くなってきたのでエアプランツを家に入れられるようにしなければと。色々成長したのでどうしたらいいか悩み中です。
YouTube、自慢大会、なかなか面白かったです。

自宅の近くでもフル電動自転車を見かけるようになったのですが、普通の自転車と違い原付扱いなので、ヘルメットやナンバープレートが必要なものの、自転車感覚の人が多いですね。(-_-;画像はピトカイルニア属のヘテロフィラです。こぼれダネで自然と芽吹いてきたようで、自家受粉するようですね。パイナップル科で株元に葉が落ちた後もトゲが残り、毬栗になります。
温暖な地域に自生するので、春から秋は屋外で管理して冬は屋内へ取り込むか養生を。パイナップル科の植物は葉の表面からも吸水するので、水やりは全体が濡れるように。
開花すると横から新たな脇芽が育ってきて世代交代します。株が充実すると開花しますが、葉が出るよりも先に花が上がる事が多く、目立つ花色なので楽しめますね。

今日は糖尿病の診療日。午後から雨模様で季節が進みそうです。周りに風邪を引く人が多くなったので気を付けたいですね。ここ数年、風邪らしい風邪を引いていないです。(^^;画像はEriospermum属のドレゲイです。不定形の球根から、不思議な形状の葉を立ち上げます。葉の上にモフモフの付属器と言われる器官が付きますね。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
この属は植え替えを嫌うので、植え替え後にしばらく動かなくなる事があります。なので、毎年ではなく数年に一回のペースで植え替えたほうが無難。鉢は少し大きめをチョイス。

天パさんからいただいたアガベ、ちょっと時間かかりましたが無事に発根しました。f^_^;
1ヶ月半くらいかかりましたね。
早速植え込みます。

週末の土曜日、京都シャボテンクラブの例会に参加しました。狂仙会の写真鑑賞、品評は多肉植物。来月は宇治の展示会、バスツアー、例会と忙しいですね。(^^;画像はマミラリア属の蓬莱宮です。以前はバルチェラ属とされていましたが、統廃合で今はマミラリアになっていますね。
比較的寒さに強いのですが、冬前には屋内へ取り込むか養生をして、水やりの回数を落とします。脇芽が自然と出てきて群生するので、株の大きさに合わせて鉢サイズを。
花は数日にかけて咲くので、観賞する機会は多め。通常は春に咲きますが、秋に咲くことも。トゲの先端がフックになっていて、引っ掛かりやすいのが難点ですね。

明け方の気温が10度を少し上回る程度なので、温室の空調機を20度設定の暖房運転に。温度計の記録を見ると昼過ぎのピークで29度くらいまで上がるようですね。画像はEriospermum属のパラドクサムです。霧氷玉とも。不定形の球根から不思議な形状の葉を立ち上げますね。開花してから後に葉が出てきます。(^^)
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
球根はショウガ根のようで、芽を基準に割って分ける事ができます。気温の高い時期は葉を落として休眠しているので、株分けは休眠中が無難。

週明けあたりから咲いているリトープスがあるのですが、平日は見ることが出来ず週末には花が終わってそうですね。サボテンの一日花よりは長いですが、タイミングが合いません。(T_T;画像はトリコディアデマ属の紫星晃です。短めの葉を密生させ、先端に柔らかいトゲがあります。斑入りは今のところ珍しいようですね。
扱いは春秋型ですが万能で暑さ寒さにも強いです。植え替えは春か秋に。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
紫星晃が本来の品種名ですが、紫晃星と言われる事が多く、今でも後者が通り名となっていますね。枯れた部分はトゲが硬くなり、新しい葉の生長を妨げるので時々整理します。

アガベがTwitterの草フリマで500円だったので手を出してみたら想像以上のサイズで慌てて6号のスリット鉢を買いに走りました。てっきり手のひらに載るくらいだろうと思っていたのですが。
(;;;:´;ω;`:;;;)ゞァセァセァセァセ,,,
我が家のリトープス、うまく夏越しできたと思っていたらここに来てどんどん溶けてしまってます。水遣りが良くなかったのでしょうかね。
まだまだ手探りの繰り返しです。

喪中はがきが届いて、早くも年末年始を気にする時期になってきたと思わせます。普段、あまり片付けがベランダも、時間を見つけて整理整頓したいですね。(^^;画像はコノフィツム属のウィッテベルゲンセです。昨年の秋のバスツアーで入手した株ですね。まだ数が少ないので油断しないよう育てたいところ。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
頂面の模様が独特ですね。タイプ違いがあるようで、赤く色付くものや模様違いなど。群生させて数が多くなると貫禄も出てくるので、そこまでうまく増やして行きたいですね。
>> ぴちょんくん さん
発根してよかったです!胴切りの断面から出てきた小株はけっこう発根難しいようで、私も発根率低めです…!
メセンに手を出すのは初めてなのでやや心配ですが、皆さんの投稿を参考に溶かしてしまわないように育てます!

アルミ製の花台は腐食しにくく長持ちしますが、それでも毎日のように水やりで濡れるような環境だと傷んできますね。(^_^;画像はコノフィツム属の藤壷です。頭頂部が光を取り込む窓になっていて透明感がありますね。元はオフタルモフィルム属とされていました。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
表皮が薄いのか夏の間、被っていた旧皮を取り除く際に傷めやすいので要注意。年数が経つと分頭して群生してきます。意外と日照がいるので日当たりの良い場所へ。

秋はコノフィツムやリトープスが開花シーズンなので楽しい時期ですが、前者が午前、後者が午後に咲く事が多く、確認に忙しいですね。(^_^;)画像はディオスコレア属の亀甲竜です。早ければ夏の後半、または秋になると蔓を伸ばして葉を展開してきます。誘引のため支柱を立てて、うまく誘導を。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
以前から育てていた大株は今回目覚めないので、残念ですがどうやら枯れてしまったようです。雌雄異株なので花が咲くまで、雄花か雌花かは分かりません。

サボテンの実生株が小さいながら三つほど残っていて、そのままでいいのか明け方が寒くなってきたので取り込むべきか悩みどころ。流石に冬は屋外放置できないでしょうね。(^^;画像はリトープス属の露美玉です。秋らしい気温になり、むっちりしてきました。リトープスは前シーズンの根がほぼ枯れて、秋に動き始めてから新しい根が出てきますね。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
私の栽培環境だと少し日が足りないのか、縦長になりやすいので日照を確保できるなら、なるべく長く日に当てたほうが低く締まった姿になるかと思います。

晴れた日の翌朝は放射冷却で冷え込みますね。昼間は温室内も温度が上がっているので、水やり後の乾燥も早いかと思ったら、意外と乾きが遅くて水やり間隔の見直しが必要かと。画像はコノフィツム属のtantillumです。小振りの株姿ですが、極小と言うほど小さくないので扱いやすいサイズ感ですね。(^^)
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
よく見るとタビ形。足袋(タビ)に馴染みが無い人のほうが多いでしょうから、この通称は通じなくなってきていると感じますね。いずれ呼び方が変わりそうです。

明日から三日間、宇治市植物公園で展示会と即売会です。最終日の天気がちょっと怪しいですが、前半は良い天気に恵まれそうですね。私も少しお手伝いできればと思っています。画像はフィロボルス属のテヌイフロルスです。新葉が出てくる直前の姿。この後、無事に葉が出てきましたが、モサモサになって塊根部が見えなくなるほどに。(^^;
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
秋口に植え替えて一回り大きめの鉢にしました。たぶん吊り鉢としては限界に近い大きさの鉢になるので、更に大きくなったら悩ましいところ。

金曜の祝日に宇治市植物公園へ行って、展示会と即売会に。この時期としては気温が高く、散歩がてら足を運んでくれる人も多く、特に午前中は盛況でしたね。(^^)画像はドリミア属のアカロフィラです。小型の球根植物で、地表から短めの葉を立ち上げますね。球根が充実すると開花しますが、数年に一度くらいのペースです。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
日照が弱いと葉が伸びるので、意外と日差しがいるようです。夏は葉が枯れて休眠。秋になると新しい葉が出てきます。性質は割りと強いのですが、生長がとても遅いですね。

季節外れの暖かさもあってか、風邪を引く人が周りでも多くなっているのて気を付けたいです。週末の日曜、クラブのバスツアーなので体調を整えておきたいですね。画像はアドロミスクス属の達磨クーペリーです。達磨葉とも言われますね。ノーマルより葉の幅が出やすいタイプ。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
アドロミスクスの仲間は葉が外れやすいので、周りに触れるものを置かないようにします。葉挿しで簡単に増えるのですが、意図せず葉挿し苗が増えがち。(^_^;)

植え替えたばかりのコノフィツムが荒らされていて、どうやら鳥の被害に合ったようです。あちこちかじられて、置き肥が落とされ、土が散乱していました。(-_-;画像はDelosperma属のスパルマントイデスです。短めの葉が広がる品種ですが、茎は柔らかく暑い時期に傷むところが出るので、定期的に仕立て直しが無難。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
同じ属では夏型のほうが多いものの、性質が違うので扱いには少し気を遣います。寒さにはかなり強く、屋外軒下で越冬可。花も綺麗な品種なのでお勧め。

私は外部から出向と言う形で仕事をしているので、職場の若手さんたちに知識や経験を話せても、指導とまではいきません。その辺りのさじ加減は難しいですね。画像はアエオニウム属のビッグバンです。気温の低下とともに葉を広げて、明らかに変化しているのが分かります。緑の斑入り部分はほとんど判別できないですね。(^_^;
扱いは春秋型で少し冬寄り。春や秋はよく日に当てます。植え替えは中間期に。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
真夏は葉を落とす事もありますが、萎縮していたものの葉数はほとんど変わりませんでした。寒い環境も、氷点下まで下がるようなら養生が必要です。

10月末に用事ついでに神奈川県立の植物園に行ってまいりました。一応日比谷花壇グループが管理委託されているようでした。
広場にはかぼちゃが置かれていたりコスモスやバラが見頃でしたが、温室は予算が削られているらしく通年無加温との事、そんななか、カトレアも咲いていました。
神奈川の海に近い位置とはいえ厳しい環境で頑張ってます。
温室、サボテンや多肉類はほとんどなかったのが少し残念でした。

最近の車はオートライトが増えている弊害か、ヘッドライトを点灯せず走行している車を見かけますね。(・・;) 週末、土曜の夜にライブ配信の予定です。画像はフォッケア属の火星人です。なかなか花が咲かないと思っていましたが、秋になって開花しました。春の後半に咲いている事が多いので、季節感がおかしくなりそうです。
扱いは夏型。春から秋まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは春。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
気温の高い時期は蔓性の茎を伸ばし、細長い葉を展開します。気温が下がってくると活動が緩慢になり、冬は休眠。葉を落としますが、環境が良いと葉を落とさず越冬する事も。

こんばんは!流行りモノのアガベに手を出すなと忠告受けたのに笹の雪をメルカリでポチってしまったぴちょんくんです。
送料込み1,200円程度なのでまあヨシとしますw
まだあんまりいわゆる白ペンキは見られないのでゆっくりでしょうが来年の成長に期待です。と言いながら写真は去年購入したチタノタブルー、コレは一年で大分大きくなりました。
宇治植物園で大きく咲いたのはショクダイコンニャクでしょうかね。こちらでも植物園で時々見ました。
週末はいきなりきた寒さの為、室内取り込みに大忙しでした。
f^_^;

昨日のバスツアーは当初、人の集まりが悪いと思われていましたが、飛び入り参加もありいつもと同じ位の人数でした。皆であれこれ話ながらの物色も楽しいものです。(^^)画像はリトープス属の紫勲です。良い感じに膨らんでいますね。紫勲や弁天玉、日輪玉など割りと性質が強い品種は育てやすく、ありがたい存在です。
扱いは冬型。秋から春まで日当たり良く管理。植え替えのお勧めは秋。水はけの良い用土を使い、水やりは乾湿のメリハリをつけながら。肥料は軽めに。
植え替えの際に旧皮は取り除くのですが、株本体に傷が付きやすく取り扱いは慎重に。下の方は取れにくければそのままにして、次回の植え替えで取り外すくらいで良いかと。
>> ぴちょんくん さん
お疲れ様です。そうですね、植物園の温室に展示されていたのはショクダイオオコンニャクだったかと。(^^;アガベ熱もそろそろ落ち着いてきたように感じます。欲しい人にはほどほどに行き渡って、後はマニア向けが受けるかどうかですね。
販売や生産業者にとっては、購買欲の波が長く続いて欲しいところでしょうけど、以前のハオルチアに熱気があった頃を知っているとあまり喜べた話ではありません。
多肉植物やサボテンと言うジャンルが幅広く楽しまれるのが理想かと思うので、どこかに偏った市場は個人的にはどうかと思います。
本当に好きで栽培するなら何も問題ありません、流行りに踊らされるのはヤメたほうが良いと言うだけですね。
画像はカクタスニシさんのところにあった、特大の亀甲竜です。ここまで大きくできたら満足感は高いでしょうね。(^^)